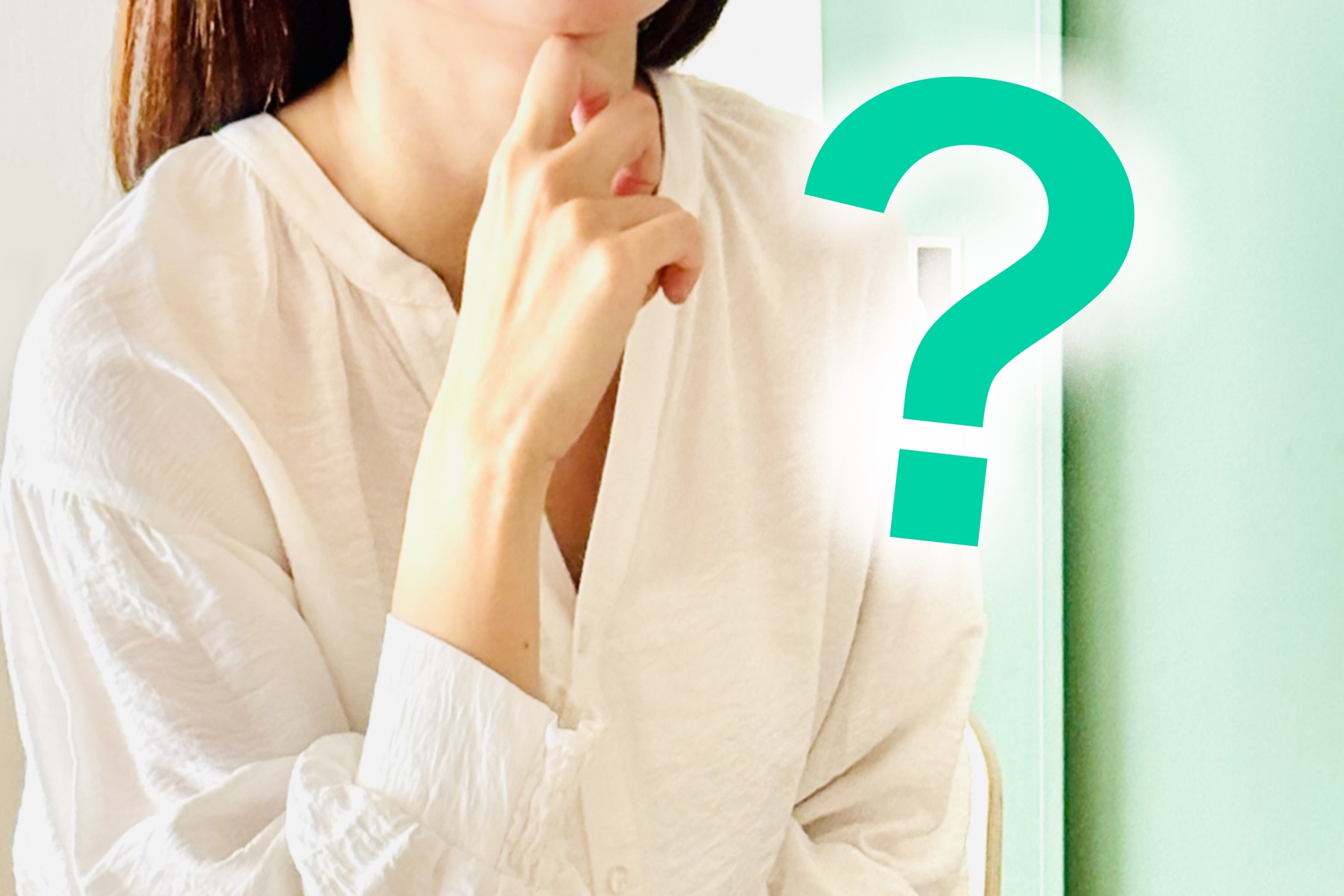介護職員がミスしてしまう主な原因
介護職に漠然とした不安を抱く理由の一つに、介護現場でのミスの発生の原因がわからない点があります。
介護職員がミスをしてしまう主な原因は大きく3つ考えられます。新人職員の不慣れな作業や人手不足による多忙な状況、経験を重ねたがゆえの慣れが引き起こす油断です。
しかし、ミスの背景には避けられない職場事情や環境なども関連しており、決して一人だけが責められる問題とは限りません。ここでは、それぞれの原因を詳しく見ていきましょう。
新人職員に多い不慣れな作業
介護サービスの利用者は心身に不自由を抱えており、介護士の仕事は利用者の健康状態や自立度に応じた生活支援です。
生活支援といっても幅広く、以下のように新人介護職員にとって不慣れな作業も少なくありません。
- 食事介助
- 排泄介助
- 入浴介助
- 移乗と移動の介助
- 介護記録
食事介助は、配膳から全介助まで、利用者の状態に応じて行います。高齢者は嚥下機能が低下している場合もあり、窒息や誤嚥に注意が必要です。個人の自立度を尊重した支援が求められ、新人には難しい場合もあるでしょう。
排泄介助は、自力で排泄できる方から全介助が必要な方までさまざまです。利用者の要介護度に応じた技術を学び、適切に使い分ける知識とスキルの習得が重要です。
入浴介助も見守り程度で済む場合もあれば、機械浴を用いるケースもあり、機器の扱いに慣れるまでは新人にとって緊張する作業の一つです。
移動・移乗の介助では、杖や歩行器を使用した歩行、車いすやストレッチャーでの移動、ベッドから車いすへの移乗などがあります。
転倒・転落を防ぐ注意が欠かせず、慣れない間は不安に感じやすい場面です。
介護記録も重要な業務で、初めは時間がかかりますが、経験を積むことでスムーズに記録できるようになります。
忙しさによるミス
介護福祉業界では人手不足が続いており、介護職員は多忙な労働環境に置かれがちです。
特に新人職員は業務に不慣れなため、焦燥感や緊張感からミスを生じやすくなります。
しかし新人職員に限ることではなく、経験を積んだ職員でも、多岐にわたる業務を抱えるなかでは注意していてもミスを起こしやすくなります。
ハッシュタグ転職介護は介護福祉業界に特化した人材紹介会社です。労働環境を熟知し、新人のサポート体制が整った職場とも幅広くつながりがあります。
介護の道を志そうとしている方の不安の深い傾聴をモットーとし、単なる転職支援ではなく、生涯のキャリアパートナーとなり寄り添ったサポートが強みです。
忙しさによるミスが不安な方は、まずハッシュタグ転職介護の専門アドバイザーにご相談ください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
慣れが引き起こす油断
業務の慣れに起因するミスは、新人職員だけでなく経験豊富な介護職員も留意すべきことです。
介護では、安全性を確保し快適な環境を提供するため、指差し確認や声出し確認、複数職員によるダブルチェックなどの手順でミス防止が求められます。
しかし業務に慣れてくると気が緩み、確認を怠ることでミスが生じる傾向にあります。
慣れから引き起こされるミスはヒューマンエラーの一つで、手順が疎かになったりリスクを軽視したりすることが原因です。
また、新人職員の場合も業務に慣れてきた安心感から油断することで、ミスを招くことがあります。
ミスの事例
新人職員が注意すべき作業は理解しても、介護現場で実際に起こりえるミスをイメージするのは簡単ではありません。
具体的には誤薬や食事介助での不注意、身体介助でのミス、記録漏れなどが挙げられます。
ミスの内容や影響をあらかじめ把握しておくと、介護職に従事するための心の準備になるでしょう。
誤薬
誤薬は利用者に内服薬を誤って与えるミスです。誤薬が起こる要因には大きく分けて人的要因と環境要因が挙げられます。
主に、人的要因は確認作業に関連したもの、環境要因は多忙な業務や業務の重複などです。代表的な誤薬の例は以下のとおりです。
- 無投薬
- 利用者間違い
- 投与時間間違い
無投薬は、配薬や与薬を忘れたり、配薬ケースや薬包に残薬が残っていたりする場合です。
多忙かつ重なる業務、ときには与薬中に作業が中断される状況などで、確認する余裕がないことが原因として考えられます。
利用者間違いは与薬すべき利用者ではなく、別の利用者に与えてしまう事故です。
薬剤の数量や形状、色が似ている場合に起こりやすく、配薬やコール対応など同時に複数の業務を抱える環境が背景にあります。
投与時間間違いは、指定時間ではない時間に与薬したり、与薬時間を間違えて過剰与薬したりする事故です。
朝の配薬が遅くなり次の時間に重なることや、介護職員間で情報共有不足が原因になることがあります。
誤薬は利用者の健康や生命に直結するため、医療者への報告と対応を第一優先とし、状況の把握と原因の検討、再発防止策を行う必要があります。
食事介助の不注意
食事介助が必要な利用者は高齢者が多く、なかには自力で食事ができず、咀嚼や嚥下機能が低下している方も少なくありません。
うまく咀嚼できず塊のまま飲み込んだり、義歯を誤って飲み込んだり、嚥下反射の機能が低下したりすると誤嚥・窒息するリスクがあります。
誤嚥は誤嚥性肺炎を引き起こし、窒息は死を招くこともあるため、食事介助中は常に注意が必要です。
しかし食事介助が必要な利用者が複数人いたり、ほかの業務と重なり介助中に目を離してしまう状況では、こうしたミスが起こりやすくなります。
身体介助のミス
身体介助のミスでは、歩行介助や排泄のための移乗介助などでの転倒・転落が多く、骨折や脳内出血につながる恐れがあり注意が必要です。
介護事業所では居室内の場合目が届きにくく、物音がして駆けつけると利用者が部屋や廊下で転倒転落していたというケースも少なくありません。
環境が原因となる場合もあり、転倒転落防止センサーを活用するといった改善策を職場全体で講じることが大切です。
また、介護者が利用者の日常生活動作レベルを適切にアセスメントできていないことも原因の一つです。
例えば、麻痺のある利用者への歩行介助の際は、介護者は麻痺側に立って麻痺側をサポートする必要があります。
しかし基本的介護知識や技術が欠けていると、健側に立ってしまい転倒を防げないことがあります。知識と技術をしっかり身につけていれば、ミスは防げる場合が多いようです。
業務が多忙な場合も、本来複数人で行うべき身体介助を一人で対応せざるを得ない状況が事故につながることもあります。
以上の介護事故のリスクを考えると、リスクマネジメントを重視する職場選びも大切だといえるでしょう。
ハッシュタグ転職介護は、介護事故へのリスク対応や新人職員に対する研修制度の充実に力を入れています。安心感のある職場への転職支援を全力でサポートします。
介護福祉業界の専門知識を持つアドバイザーが在籍し、一人の担当者が介護ミスへの不安を聞き取り、職場紹介から入社後のフォローまで一貫したサポートが可能です。
無料相談の機会も設けているため、まずは気軽に専門アドバイザーに不安やご希望を伝えてみましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
記録漏れ
介護職の業務には介護記録の入力も含まれており、介護職員間で利用者の情報を共有し、それをもとに適切な介護サービスを提供することが基本です。
介護記録は、利用者の身体状況をアセスメントしてリスクを把握し、ケアプランに反映させるために欠かせません。ミス防止の観点からも重要です。
しかし介護者による記録の記入漏れがあると、利用者のリスク対応が的確ではなく、ミスを誘発しかねません。
介護ミスが起きたときの初期対応と再発防止
介護ミスを起こしてしまったら、自分が責任を取らされるのではないかと不安を抱くこともあるでしょう。
しかし大切なのは、ミスが起きてしまったときの適切な対応です。あらかじめ具体的な対応の流れを理解しておけば、万が一のときにも落ち着いて行動でき、安心感をもって従事できます。
初期対応ではまず迅速な報告と正確な記録を行い、利用者やご家族への誠実な説明が重要です。そのうえで、再発防止に向けた検討と改善策の提示が求められます。
迅速な報告と正確な記録
介護ミスが起きたときは、まず利用者の心身の状態を確認して迅速な報告することが大切です。
誤薬・誤嚥・転倒転落などは、健康状態の異常や悪化につながる可能性が高く、早期の検査や治療など医療的介入が必要となるためです。
また、発生状況を詳細かつ正確に記録することも重要で、今後同様のミスを引き起こさないよう対策を立てる指標になります。
さらに正確な記録が残ることで、事故が故意によるものではないことや、適切な対応を取ったことの証明にもなります。介護者自身や介護事業所の信頼を守る切り札になることも事実です。
利用者やご家族への説明
介護事故を起こしてしまうと、罪悪感や責任の取り方に不安を感じ、利用者やご家族への連絡と説明に躊躇してしまうことが想像されます。
しかし起きてしまった事実は変えることはできないため、利用者とご家族には真摯に向き合い、丁寧な説明が必要です。
介護事故後にトラブルへと発展する主な要因は、介護者の姿勢や態度、報告の遅延などが挙げられます。つまり、正確で早急な連絡と説明がとても大切なことを示しています。
一方で、事故後のトラブルへ発展しなかったケースでは、介護者の礼儀正しい対応や的確なコミュニケーションが評価されていたとの調査報告もあります。
誠実な説明と心からの謝罪は、信頼関係を保つうえで欠かせません。
また、同じミスを繰り返さないよう状況を分析して改善点を提示すると、利用者やご家族の理解を得やすくなります。
ミスしたときの気持ちの切り替え
ミスを引き起こしたら精神的に大きなダメージを受け、社会生活に自信を失うのではと不安を抱く方もいるでしょう。
しかし新しい道へチャレンジするとき、失敗なくして成長なしと心に留め、失敗を前向きに受け止める姿勢が大切です。
ここでは、落ち込みやすい方の特徴や、気持ちを切り替えるリフレッシュ法を紹介します。失敗しても立ち直る心構えを持ち、ポジティブな気持ちで前進しましょう。
落ち込みやすい人の特徴
落ち込みやすい方は、ミスに対してネガティブな感情を抱きやすく、次のような背景を持つことが考えられます。
- 完璧主義
- 自己効力感が低い
- 自己肯定感が低い
完璧主義の方は失敗に対して過剰な抵抗感があり、ネガティブな感情を回避したいと感じる傾向があります。
そのような気持ちは、些細なミスでも必要以上に気にしてしまうようです。
また自己効力感とは、失敗から学びを得て成功体験につなげる体験を繰り返すことにより、自分はできると前向きな気持ちを持つことです。
自己効力感が得られないと、失敗を成功に変える経験が得られず、落ち込みやすくなると報告されています。
また自己肯定感や自己評価が低いと自分の価値を見出せず、周囲の評価を気にし過ぎるため、失敗に対して落ち込みやすい特徴があります。
引きずらないためのリフレッシュ
介護ミスを引きずらないためのリフレッシュ方法には次のような方法が有効です。
- 安心できる環境を整える
- 信頼できる方に相談する
- 好きなことに熱中する時間を作る
心身が落ち着ける環境にあると、自律神経系が作用してリラックス効果が得られます。家やカフェ、マッサージ店など、自分がゆっくりできる場所を見つけておくとよいでしょう。
また、信頼できる方に気持ちを打ち明けることも効果的です。話すことでミスをした状況を再認識し、ネガティブな感情に区切りをつけるきっかけにもなります。
さらに、好きなことや楽しいことに熱中する時間は、ポジティブな感情を引き出し、ストレスからの回復につながります。
こうしたリフレッシュの工夫で気持ちを切り替え、新たな気持ちで仕事に向き合えるでしょう。
気持ちが切り替えやすい職場環境があることも重要です。働きやすい雰囲気の職場は、たとえ介護ミスが起きても周りのサポートがあるため立ち直りやすくなります。
ハッシュタグ転職介護では、介護ミスに不安を抱える方に寄り添い、働きやすい環境のある職場を紹介します。
介護職に関する専門知識を有するキャリアアドバイザーが在籍しているため、介護職にまつわるさまざまな心配を相談できます。
まずはハッシュタグ転職介護の無料相談でご希望を話し、理想の職場を一緒に探しましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
新人介護士に多いミス
介護職未経験の方は、ミスを起こしやすいのではと不安に感じるかもしれません。しかし、前もって新人介護士に多いミスを理解しておくと不安が軽減されます。
新人介護士が起こすミスには、研修不足や他職員との連携不足が関係しています。
研修不足による不安から起こるミス
新人介護士が基本的な介護知識や技術の研修を十分に受けていない場合、現場でのリスクアセスメントや適切な対応が難しくなります。その結果、ミスにつながる可能性があります。
研修不足による不安から焦りを生じ、思わぬミスを引き起こすことも少なくありません。
そのため、定期的な研修で介護知識やスキルを確認でき、マニュアルの見直しも行う職場を選ぶことが大切です。
ハッシュタグ転職介護には、介護業界の転職事情を熟知するエージェントが在籍しており、一般的な人材紹介会社以上に現場に即した転職支援ができます。
研修制度が整い、介護知識やスキルの向上、介護事故防止のマニュアル整備に力を入れている職場の紹介も可能です。
まずは無料相談で、研修制度や職場環境が充実した職場への希望を専門アドバイザーに相談してみましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
ほかの職員との連携ミス
介護現場で質の高い介護サービスを提供するには、介護職員間の連携やコミュニケーションが欠かせません。特に介護職未経験の新人介護士にとって、ほかの介護者との連携はとても重要です。
多忙な業務のなかで職員と報告・連絡・相談を行うことは新人には簡単なことではありません。しかし、職員間の連携がしっかり取れていると、介護ミスを未然に防ぐことにつながります。
介護事故の法的責任について
実際の介護事故事例を検討すると命に関わる重大な事故はないとは言い切れず、法的責任への不安を感じることもあるでしょう。
しかし、職員個人に課される責任と介護施設が負う責任は異なり、個人が守られる仕組みも整っています。
法的責任を正しく理解することで不安が和らぎ、介護職に前向きに取り組む気持ちを持ちやすくなります。
職員に対する責任
職員が介護事故を起こした場合、個人に対して問われるのは損害賠償(民事上の責任)や刑事罰(刑事上の責任)です。
損害賠償に関しては、たとえ職員個人のミスでも、施設の管理体制が不十分で安全配慮義務を怠ったと判断される場合が少なくありません。
そのため、個人に直接請求が及ぶことはほとんどないといわれています。
また損害賠償が高額になる場合、賠償能力のある施設が対応することが一般的で、職員個人は法的に守られる面があります。
刑事罰は業務上過失致死傷罪や虐待など、ミスにより利用者に重篤な影響を与えた場合や、故意で悪質な介護事故で問われる責任です。
介護施設に対する責任
介護施設が問われる責任は、行政処分(行政上の責任)で、施設が所管の行政機関から業務や運営の改善命令や、介護施設指定の解除処分を受けることです。
職員個人が介護事故を引き起こした場合でも、施設の労働環境や業務体制、研修制度などが監査されます。
介護事故は職場環境が影響する場合もあるため、行政からは改善勧告・業務停止・指定取り消しの順で処分が下されることがあります。
施設は法令を順守した運営管理が求められるため、職員は個人として法的に守られる環境のもとで働くことが可能です。
介護ミスに対する不安を解消しよう
未経験で介護業界に挑戦したい気持ちがあっても、介護ミスや責任への不安の払拭ができない方もいるでしょう。
しかし、介護の現場でのミスは誰にでも起こりうるものです。大切なのは、ミスを防ぐ工夫や起きた後の対応策を知り、周囲のサポート体制を活用することです。
環境を確認し、安心感を持って働ける準備を整えることで、不安は少しずつ軽減されるでしょう。
また、転職相談やエージェントの活用も効果的です。専門のアドバイザーに悩みや不安を相談することで、自分に合った職場環境を見つけやすくなり、安心感を持って介護のキャリアをスタートできます。
ハッシュタグ転職介護は医療・介護・福祉業界に広範なネットワークを持つ人材紹介会社です。介護現場の労働条件や環境、研修などのサポート体制に精通し、介護の道へ進もうとしている方に幅広い選択肢を提供できるのが強みです。
介護ミスに対する不安を一人で抱え込まず、まずはアドバイザーに不安な気持ちを打ち明けてみましょう。言葉にすると、気持ちの整理がつき挑戦する意欲が高まることがあります。
興味を持っているけれど、なかなか転職する勇気が出ない方は、ハッシュタブ転職介護の専門アドバイザーに相談してみることから始めてみましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼