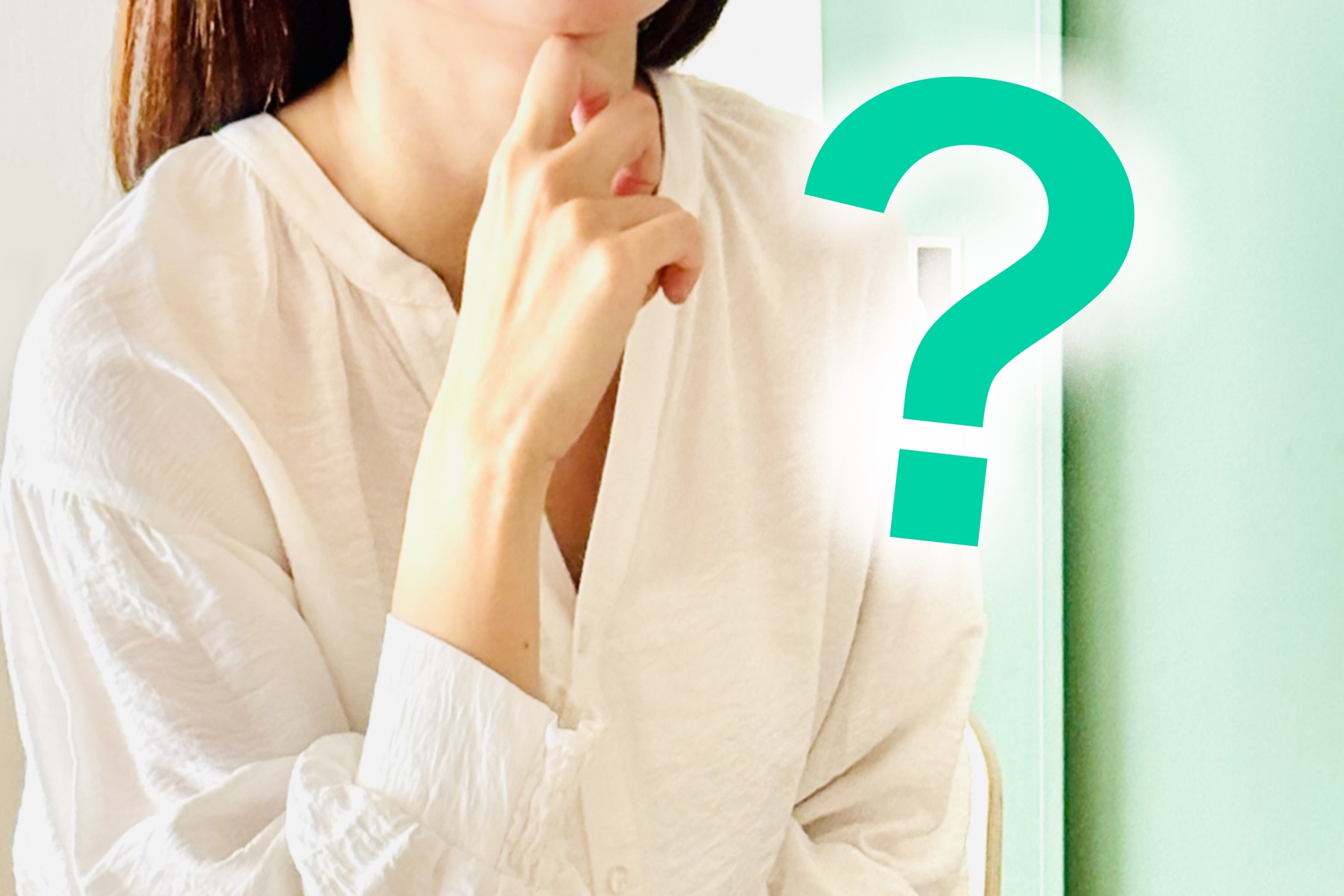介護におけるアセスメントとは

アセスメントとは利用者の身体や生活などを理解し、生活上の課題と必要な支援を明確にすることです。
つまり、利用者によりよいケアを提供するための土台となります。アセスメントなしでケアの内容を決定すると、実際の生活にそぐわず無駄になってしまうからです。
ここでは、アセスメントの重要性と、アセスメントと混同されがちなモニタリングの違いについて掘り下げてみましょう。
アセスメントの重要性
アセスメントとは、利用者がその人らしい生活を送るケアプランを決めるための重要な土台です。
アセスメントでは表面的な情報だけでなく、本当の希望や生活上の不安をすくい上げ、それらをもとに考えられる利用者固有の課題からケアプランを作成します。
意識しておきたいのは、ただの聞き取り作業ではなく、利用者を広く深く知る大切なプロセスということです。
そのため、たとえ未経験でも、丁寧に利用者と向き合う姿勢が、質の高いアセスメントにつながります。
利用者のケアに対する満足度や、生活の質を向上させるためにも、アセスメントは重要です。
モニタリングとの違い
アセスメントと混同されやすい業務の一つにモニタリングがありますが、行うタイミングや目的が異なります。
アセスメントは、ケアプランの作成前に、利用者の生活上の課題や、解決に必要なケアについて情報収集して考えるプロセスです。
一方モニタリングは、ケアプランの実施期間中に、その効果を検証する工程です。
両者は連続して切り離せないプロセスであり、どちらも利用者に適したケアの提供に欠かせませんが、異なるものだということを理解しておきましょう。
介護におけるアセスメントの流れ

アセスメントは事前準備から面談、ケアプラン作成と段階的に進められ、その後にケアの提供へと移行します。
ここではそれぞれの段階について解説します。流れを理解しておくことで、未経験者でも自信を持って取り組めるでしょう。
事前準備
事前準備とは、面談の前に利用者の医療情報や家族構成などを確認する、アセスメントの第一段階です。
面談前に情報を収集・整理することで、面談で利用者の負担を軽減しながら必要な情報を引き出せます。
他職種の情報の把握も大切です。介護だけでなく多面的な視点を持つことで、より的確なアセスメントにつながるでしょう。
そのため事前準備は、面談当日に向けた大切な業務といえます。
面談当日

面談当日は、利用者本人との会話を中心に情報を収集します。
ケアプランを利用するのは、周りではなく本人だからです。本人から、こだわりや困っていることを聞くことで、個別性のあるアセスメントができるでしょう。
家族と面談する場合、本人と家族の意見が食い違っていないか注意しましょう。
利用者に必要な課題を分析してケアプランを作成するためにも、面談当日に具体的な情報を収集しながら利用者の意向や生活情報を網羅することが大切です。
ケアプラン作成とケア実施
面談で得られた情報をもとに、ケアマネジャーを中心としたチームでケアプランを作成し、実際にケアが実施されます。
チームには介護士だけでなく、看護師や栄養士、リハビリスタッフなど多職種がいます。それぞれの専門性を活かして意見を出しあい、プランを練るためです。
ケアプラン完成後は実際にケアを行います。さらにその実施状況はモニタリングされ、次回のアセスメントやケアプラン修正に反映されます。
そのためアセスメントは、単発の作業ではなく、ケアを提供する連続したプロセスの一部といえるでしょう。
この章では、アセスメントの流れを解説しました。
ケアの内容を決めるうえで、アセスメントは重要な工程の一つです。アセスメントを含む各プロセスは、連続性を保ち、チームで連携しながら進めることが求められます。
利用者との一対一だけでなく、他職種との連携などチームで動く介護業界の仕事に興味を持ち、挑戦してみたいと考える方もいるかもしれません。
ハッシュタグ転職介護のアドバイザーが自信を持つのは、興味や疑問にきめ細やかに寄り添う姿勢です。経験や資格の有無を問わず、求職者一人ひとりの悩みや不安にじっくり耳を傾け、理想の働き方や職場探しを徹底的にサポートします。
「何から始めたらいいかわからない」という段階からでも大丈夫。まずは無料相談で、介護業界に関心を持つあなたの声をお聞かせください。とことん寄り添う支援で、安心感を持てる一歩を一緒に踏み出しましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
介護現場でアセスメントを行う際のポイント

アセスメントを行う際には専門知識や技術的に上手な聴取の仕方のほかにも、利用者に興味を持ち、尊重しながら寄り添う姿勢が大切です。
具体的な注意点をそれぞれ詳しくみていきましょう。
多方面から情報収集する
情報収集には、利用者以外からの情報や介護業務以外の情報も取り入れることが求められます。
利用者本人の話を聞くことが優先されますが、家族などからの情報も生活上の課題の発見につながるからです。
複数の情報を統合して利用者を正確に理解することで、適切なケアプランを立案できるでしょう。
具体的にヒアリングする

アセスメントでの情報収集では、具体的な質問を投げかけることで利用者の生活に対する解像度を高めましょう。
抽象的な質問からは、明確な回答を引き出しにくくなります。
例えば「お風呂で困ったことはありますか?」ではなく、「どの部分が洗いにくいですか?」など、具体的に答えられるような問いかけです。
具体的な情報を得ることで、本当に必要な支援が見えてくるでしょう。
利用者と一緒に考えることを意識する
情報収集などで質問を投げかけると一方的になりがちですが、生活を利用者と考える姿勢が大切です。
一般的、客観的に必要な支援を提供するだけでは、利用者が主体的に生活を営む機会を失ってしまうからです。
一方的なサービスの押し付けではなく、利用者が生活するうえで大切にしていることや理想の暮らしを共有したうえで、満足度の高いケアを利用者自身と考えましょう。
専門職と連携する

アセスメントは介護士だけではなく、医療職員や福祉職員などチームで取り組むものです。
それぞれの専門性を活かした情報や意見の共有が、よりよいケアプランの作成に活かせるからです。
また一人で結論を出さず、選択肢や考えを共有することで、より効果的な意見や答えが導き出されます。
利用者のケアプラン作成に関わる職員と意見や提案を積極的に交換し、利用者に合ったアセスメントを行いましょう。
マナーに気を付ける
利用者との信頼関係を築くために、基本的なマナーを守ることもポイントです。
信頼を損ねると、利用者などから正しい情報を得られないだけでなく、実際にケアを実行する際にもスムーズに行えない場合があるからです。
挨拶をはじめとする礼儀作法、視線の合わせ方など、細かな言動が相手に与える印象を大きく左右します。
情報集めに躍起にならず、利用者を尊重する姿勢が大切です。
この章では、アセスメントのポイントを解説しました。利用者との信頼関係の構築は、聞き取り技術と同様に重要な要素です。
そのため介護業界が未経験の場合でも、それまで培ったコミュニケーション能力を活かす場面は少なくありません。
「自分の能力を発揮できそうな介護業界へ一歩踏み出したいけれど、一人では情報の選択が難しい」と感じている方には、ハッシュタグ転職介護の専門アドバイザーとの無料相談がおすすめです。
医療・福祉業界に特化した知識と経験を持つアドバイザーが、あなたの強みや希望にしっかりと寄り添い、適切な職場や働き方をご提案します。
信頼される介護職員への第一歩として、まずはお気軽にご相談ください。
あなたの可能性を最大限に活かせる職場探しを、全力でサポートします。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
介護におけるアセスメントシートとは

アセスメントシートは、利用者の状態を記録し、共有するために大切なツールの一つです。ここでは以下の3点について解説します。
- 作成の目的
- アセスメントシートの様式
- アセスメントシートに記載する23項目
整理された情報を共有し、利用者のケアに活かすため、それぞれ詳しくみていきましょう。
作成の目的
アセスメントシートを作成する目的は、利用者やご家族から聞いた内容をまとめ、利用者に合ったケアを考える参考資料にすることです。
アセスメントシートは、読むだけで利用者本人の身体状態や生活歴、ご家族を含めた生活環境など暮らしている状況を詳しくかつ早く知ることができます。
また、利用者に関わるチーム全員の共通理解を促進し、職種の異なるスタッフ間でもスムーズに情報が共有される基盤になりえます。
アセスメントシートの作成は、チームで利用者の適切なケアを考える土台の形成といえるでしょう。
アセスメントシートの様式

アセスメントシートの様式は事業所によって異なりますが、基本となる項目は、厚生労働省から示された23の標準項目で構成されています。
標準項目は、情報の偏りや抜けを防ぐ目的で示されています。
しかし、すべての項目を埋めることに集中しすぎて、相互のコミュニケーションが目的の面談が一方的な尋問にならないよう注意が必要です。
アセスメントシートに挙げられている項目を少しずつ埋め、広く深く利用者の生活を把握して、適切な課題の分析へつなげましょう。
アセスメントシートに記載する23項目

標準項目には基本情報に関する項目と、課題分析に関する項目で構成されています。
基本情報に関する項目は、以下の9点です。
- 基本情報(氏名や受付日時など)
- これまでの生活と現在の状況(生活歴など)
- 利用者の社会保障制度の利用情報(介護保険や生活保護の有無など)
- 現在利用している支援や社会資源の状況
- 日常生活自立度(障害)
- 日常生活自立度(認知症)
- 主訴・意向
- 認定情報(要介護状態区分、支給限度額など)
- 今回のアセスメントの理由(アセスメント実施に至った理由など)
また、課題分析(アセスメント)に関する項目は以下の14点です。
- 健康状態(身長や健康に対する理解や意識の状況など)
- ADL(寝返りや階段昇降など)
- IADL(電話や金銭管理など)
- 認知(認知機能の程度)
- コミュニケーションにおける理解と表出の状況
- 生活リズム(1日の過ごし方など)
- 排泄の状況(排泄のタイミングなど)
- 清潔の保持に関する状況(入浴や整容の状況)
- 口腔内の状況(歯の状態やかみ合わせの状態)
- 食事摂取の状況(食事量や摂食嚥下機能の状態)
- 社会との関わり(家族などとの関わりの状況)
- 家族などの状況(支援への参加状況など)
- 居住環境(住宅改修の必要性や危険個所など)
- その他留意すべき事項・状況(経済的困窮、医療依存度など)
ケアを考える際に必要な基本項目が網羅されています。様式に沿って書くことで、利用者の状況を広く、深く把握できるように構成されています。
内容は定期的に更新される可能性があるため、新しいものを利用するとよりよいアセスメントができるでしょう。
介護におけるアセスメントシートの書き方

アセスメントシートを書く際のポイントは以下の2点です。
- 誰が見てもわかるように記載する
- 利用者中心の内容を記載する
それぞれ詳しくみていきましょう。
誰が見てもわかるように記載する
アセスメントシートは、誰が読んでも内容が理解できるように記載します。
なぜなら、介護職員だけではなく、医療職や家族の目に入る場合もあるからです。
そのため、専門用語や略語の使用は避けましょう。むしろ平易な言葉で具体的に状況を記載している方が、読み手にとってわかりやすい場合があります。
また、時間・場所・人物などを省略せずに記載すると、情報が正確に伝わります。
記載した内容を読み直して修正するなど、スムーズな情報共有のためには丁寧な記載が大切です。
利用者中心の内容を記載する
多面的な情報を盛り込む必要はありますが、利用者本人の情報を充実させることも重要です。
ケアを受けるのは利用者のため、可能な限り、本人の意向や本音を汲み取って記載しましょう。
利用者以外の方からの情報を記載する場合は、主語を明確にする必要があります。
生活の中心である利用者に焦点を当てることで、本人の視点に基づいた情報収集ができるでしょう。
聞き役が得意と考えるあなたは、利用者の意向や本音を聞き出す力を持っているかもしれません。人に寄り添うことは、介護業界で求められている力です。
あなたの理想の働き方を、ハッシュタグ転職介護のアドバイザーと一緒に考えてみませんか。
ハッシュタグ転職介護では、医療・福祉業界に特化した専門知識と豊富なネットワークを活かし、あなたの希望にぴったり合った職場をご提案します。経験やスキルだけでなく、価値観やライフスタイルも丁寧にヒアリングし、適切なキャリアプランを一緒に描いていきます。
以下のリンクより無料相談を実施中です。
あなたが考える働き方や、介護業界での活躍の仕方について、まずはお気軽にお話しください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
適切なアセスメントを行うために必要なスキル

適切なアセスメントに必要なのは、特別な資格ではなくコミュニケーション能力です。そのなかでも、特に重要なスキルは以下の3点です。
- 質問力
- 情報収集力
- 洞察力
一点目の質問力とは、具体的な情報を引き出す質問を適切に行う力です。
また、相手の立場に立って理解しやすい言葉で話すことで、利用者が意見を言いやすい雰囲気を作る力のことでもあります。
質問力がある職員は利用者との信頼関係を築きやすく、深い内容の話ができるため、必然的にアセスメントの質も高められるでしょう。
二点目の情報収集力とは、多方面から情報を集める力を指します。一つの項目だけに偏らずに広く情報を得る力です。
利用者本人の話を中心としたうえで、家族や他職種の意見や情報を得ることで利用者の生活の全体像がよりクリアになるでしょう。
情報収集力が高まれば、主観的にも客観的にも情報が得られ、多くの情報をもとにした利用者に適したケアの選択肢を提案できるといえます。
三点目の洞察力とは、相手の態度や話し方から、情報の背景にある理由や感情などを読み取る力です。
質問によって得られた回答や一言の裏には、精神的なものをはじめ、身体的な状態の悪化や環境の変化などの要因が隠れている可能性があります。
見聞きできる事実の背景や理由を考える意識を持つと、利用者の本音や隠れたニーズを引き出せるため、より適切なケアを提供できるでしょう。
利用者との活発なコミュニケーションが、適切なアセスメントにつながります。これらのスキルは未経験者にも磨ける能力です。
「未経験だけれど、人をサポートできる介護業界に挑戦したい」と考えるあなたには、ハッシュタグ転職介護の無料相談がおすすめです。
ハッシュタグ転職介護では、医療・福祉に特化した専門アドバイザーが、丁寧なヒアリングを通じてあなたの想いや希望をしっかりと受け止め、的確なマッチングで未経験からの一歩を全力でサポートします。
「まずは話を聞いてみたい」「自分に合う職場があるのか知りたい」という段階でも大歓迎です。
以下のリンクより、ぜひ無料相談にアクセスしてみてください。
あなたの新たなスタートを、一緒に考えていきましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
適切な介護アセスメントで利用者に寄り添ったケアプランを作成しよう

本記事では、一人ひとりに合ったケアプランを作成し、多様な暮らしを支えるために必要なアセスメントについて解説しました。
利用者の本音や希望を把握し、結果としてその方らしい生活を支えるケアプランの作成につながる大切な業務がアセスメントです。
そのため、利用者への関心や本人に寄り添う姿勢があれば、経験の有無に関係なく取り組める業務です。
相手に寄り添い、誰かを支える介護の仕事に興味がある方は、まずハッシュタグ転職介護の無料相談をご利用ください。
ハッシュタグ転職介護では、医療・福祉業界に特化したアドバイザーが、あなたのこれまでの経験や希望にしっかり寄り添いながら、今後のキャリアを一緒に考えます。
ただ求人を紹介するのではなく、将来を見据えたキャリア設計や、あなたに合った職場環境を丁寧にご提案。
高いマッチング率と入社後のフォロー体制も特長のひとつです。
「まずは話だけでも聞いてみたい」という方も歓迎です。あなたの一歩を、私たちがしっかり支えます。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼