生活支援員とは

生活支援員は、障害のある方の自立した生活を支える専門職です。日常生活では、食事・入浴・排泄などの身体的なサポートに加え、掃除や洗濯など暮らしの支援も行います。
さらに、就労支援事業所では利用者の健康状態の見守りや働くための支援も担当します。施設や事業者によって業務内容はさまざまで、就労支援員や職業指導員など、ほかの専門職との連携が欠かせません。
生活支援員は、利用者一人ひとりの生活の質を高めるために、福祉の現場で重要な存在です。
生活支援員と介護職員の違い

生活支援員は、主に障害がある方が自立した日常生活を送れるよう、相談や支援を行う役割を担っています。一方、介護職員は要支援・要介護の認定を受けた高齢者に対し、安心感をもって生活できるようにサポートすることが特徴です。
どちらも福祉や介護の現場で活躍する職種である点は共通していますが、仕事内容や働く場所に違いがあります。具体的な違いを確認してみましょう。
対象者の違い
生活支援員と介護職員では、支援の対象となる方に違いがあります。生活支援員は、障がい者施設の入所者や障がい福祉サービスの利用者を支援することが主な役割です。
一方、介護職員は要支援・要介護の認定を受けた介護を必要とする方が対象です。このように、関わる相手が異なることで支援の内容や関わり方にも違いが生まれます。
勤務先の違い
先述したとおり、生活支援員は、障がいのある方の相談対応や生活指導の支援を行います。そのため、知的障害者支援施設や就労移行支援事業所、介護サービス包括型のグループホームなどに配置されるケースが一般的です。
一方、介護職員は特別養護老人ホームや介護老人保健施設、デイサービスをはじめ、サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム・介護付き有料老人ホームなどさまざまな介護施設で働くことが一般的です。
仕事内容の違い

生活支援員は、障がいのある方が快適で自立した生活を送れるよう、障がい者やその家族の相談に応じながら行政や関係機関とも連携して支援にあたります。
日常生活での判断や選択が必要な場面で、適切に行動できるよう、障がい者やその家族に対して相談・指導・助言を行うことが特徴です。
また、資格の有無に応じて身体介護を含む生活援助や困っていることを解消するための支援も行います。
介護職員は、食事・排泄・入浴・移乗の介助・オムツ交換・施設内の環境整備に加えて、事務作業や行政・医療機関との連携業務など仕事内容はさまざまです。
キャリアパスの違い

生活支援員と介護職員は、どちらも働くうえで必須の資格はありませんが、経験を重ねることで将来的に目指せる役職やキャリアパスには違いがあります。
生活支援員は、一定の実務経験を積んだうえで、研修を受講することでサービス管理責任者を目指すことが可能です。具体的には、生活支援員は相談援助業務に従事し、必要な実務年数を満たした後、相談支援従事者初任者研修およびサービス管理責任者研修を受講します。
さらに、サービス管理責任者研修の実践研修を修了すると、サービス管理責任者として施設に配置されることが可能になります。なお、資格の維持には、5年ごとの更新研修の受講が必要です。
介護職員のキャリアパスでは、最終的に介護業界で唯一の国家資格である介護福祉士を目指す道があります。その流れは、まず介護職員初任者研修を終了し次に介護福祉士実務者研修を受講することで、国家試験の受験資格を得ることが可能です。
その後、試験に合格すれば介護福祉士として認定されます。介護福祉士の資格を取得することで、現場のリーダーや責任あるポジションを任される機会が増え、キャリアの幅も広がります。
もっと成長できる環境があるなら知りたい、そう思った今がチャンスです。ひとりで悩まず、専門家と一緒にこれからのキャリアを考えてみませんか。
ハッシュタグ転職介護では、あなたの成長をしっかりサポートできる職場探しを、業界に精通した専任アドバイザーが全力でお手伝いします。
理想とするキャリアや働き方を丁寧にヒアリングし、一人ひとりに合った職場環境をご提案。
スキルアップやキャリアアップを目指せる環境を一緒に見つけていきましょう。
まずは無料相談で、あなたの想いや希望をお気軽にお聞かせください。
理想の未来に向けた第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
生活支援員の仕事内容

生活支援員の仕事は、調理や掃除など日常生活のサポートにとどまらず、外出支援や就労支援・相談対応・行政との連携などさまざまです。その幅広い業務内容を確認してみましょう。
障害者の日常生活の支援
生活支援員は、食事・着替え・排泄・入浴などの介助を通じて、利用者の日常生活をサポートします。さらに、利用者が生活習慣を身につけて自立した生活ができるよう、金銭管理や家事に関する支援も仕事の一つです。
障害者の身体機能向上のための支援
基本動作のサポートを通じて、身体機能向上のための支援を行います。立ち上がりや歩行、移動などの動作を繰り返し一緒に行うことで、筋力やバランス感覚の維持に効果的です。
必要に応じてストレッチや軽い体操を取り入れることもあります。
障害者の生活能力向上のための支援
コミュニケーション能力の向上支援として、会話の仕方・挨拶・相談の方法など社会生活を送るうえで必要な対人スキルを身につけられるよう、日常的なやり取りのなかで支援を行います。
できることを一つひとつ増やしながら、障がい者が不安を軽減して生活できるよう、実践的で寄り添ったサポートが重要です。
人間関係の悩みや不安などへのアドバイス

利用者から寄せられる相談に耳を傾けることは、生活支援員の欠かせない職務です。
食事や金銭管理など日常生活での困りごとへのアドバイスはもちろん、施設内での人間関係の摩擦、将来の自立に対する不安など、内容は多岐にわたります。
生活支援員は、必要に応じて面談を重ねながら課題を整理することが大切です。心理的負担が大きいケースでは、相談支援専門員や医療の専門職と連携しカウンセリングや診療につなげます。
また、就労に関しては、ハローワークや就労支援事業所と協力して職場見学や面接練習を調整し具体的なステップを示すことで不安を軽減します。
このような相談対応を通じて、利用者の自己理解と自己決定をうながし、精神面の安定と前向きな生活の実現をサポートすることが生活支援員の役割です。
関係機関への連絡や事務手続き
利用者の入退所に関する事務手続きに加え、通院先の医療機関や行政機関との連絡や調整をサービス管理責任者と連携して行うことも生活支援員の重要な役割です。
さらに、支援に関する各種書類の作成や手続きも欠かせません。一人ひとりの利用者にあわせた計画書に基づき、日々の支援内容を記録し、適切な支援が継続して提供されるようサポートします。
生活支援員の主な勤務先

生活支援員として働く場合、具体的にどのような施設で活躍できるのだろうかと疑問を抱えている方に向けて、生活支援員が活躍する主な職場を紹介します。
障がい者支援施設での総合ケアや家庭的な雰囲気のグループホーム、就労を後押しする就労支援事業所や地域とのつながりを育む地域活動支援センターなど、勤務地の選択肢はさまざまです。
どのような施設があるのかを知ることは、自分に合った働き方や将来のキャリアを考えるうえで重要です。それぞれの職場の特徴や役割を確認しながら、自身のライフスタイルに合う働き方を見つけてみてください。
ハッシュタグ転職介護では、あなたの思いや希望を丁寧にお聞きし、今後のキャリアパスを一緒に考えるサポートを行っています。
「自分に合った職場がわからない」「今の働き方に迷いがある」といったお悩みにも、業界に精通したアドバイザーが寄り添い、あなたに合った理想の職場探しをお手伝いします。
まずは無料相談で、お気軽にご相談ください。
あなたの未来に向けた一歩を、ハッシュタグ転職介護がしっかりとサポートします。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
障害者支援施設

障がいのある方が安心感をもって生活できるよう、住まいや栄養バランスの取れた食事を提供するだけでなく、日常生活に必要な介助・創作・生産活動の機会・就労や自立に向けた訓練など幅広い支援を行う多機能型の施設です。
また、発達段階や興味関心にあわせて個別支援計画を作成し、理学療法士・作業療法士・看護師などの専門職と連携してチームで寄り添いながら、心身の機能向上と自己表現の場を提供します。
入所型で24時間体制のため、生活支援員は日中の支援に加え、夜間の見守り・服薬管理・緊急時対応・季節行事の企画運営・家族や行政との連絡調整などの生活全般のサポートを担当します。
利用者の地域での自立や就労につなげる橋渡し役として重要な役割を果たす施設です。
グループホーム
障がい者グループホームは、障がいのある方が必要な支援を受けながらほかの利用者とともに共同生活を送る入居型の施設です。これは障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つで、正式には共同生活支援とよばれます。
グループホームでは、生活支援員が利用者の暮らしを支える役割を担っており、食事の準備・入浴・排泄の介助・服薬管理などの日常的なサポートが一般的です。
加えて、利用者の健康状態を見守り、必要に応じて医療機関との連携も図ります。また、日常生活に関する相談にも対応し、利用者が安心感をもって過ごせる環境づくりにも努めています。
なお、共同生活援助における生活支援員配置は、利用者の障がい支援区分によって条件が異なり必ずしも常勤である必要はありません。
生活介護事業所

生活介護事業所は、日常生活の介助や職業訓練・健康の維持と増進を目的としたプログラムなど、日中を中心に多面的な生活を支援するための施設です。
入所型の施設では、この生活介護に加え、夜間も含めた24時間体制で利用者の生活全般をサポートしています。
さらに、個々のニーズにあわせた機能訓練やレクリエーション、創作活動を取り入れ生活能力の維持と向上を図ることが特色です。
家族や地域との連携にも力を入れており、定期的な面談や情報共有を通じて、利用者が不安なく地域社会とつながりをもち続けられるよう支援を行っています。
通所型の事業所では、自宅と施設間の送迎サービスを提供し、移動の負担を軽減しています。季節行事や地域イベントへの参加も積極的に企画し、社会参加の機会を作っています。
利用者同士の交流を深めるクラブ活動やボランティア受け入れも行い、充実した一日を過ごせる環境を整えています。
就労継続支援事業所
就労継続支援事業所は、就労を希望する障がいのある方に対して、働く機会や職業訓練を提供する支援施設です。生活支援員は、利用者の健康管理や日常生活に関する相談対応、作業活動のサポートなどを通じて、就労に向けた支援を行います。
この事業所には、A型とB型の二つのタイプがあり、その違いは利用者と事業所の間に雇用契約があるかどうかです。A型では、利用者は事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われる仕組みになっています。
一方、B型では雇用契約は結ばずに心身の状態に応じて無理のない範囲で作業を行い、成果に応じた工賃が支払われます。それぞれの型に応じて、利用者のニーズや状況に合った柔軟な就労支援が可能です。
地域活動支援センター

地域活動支援センターは、障害者総合支援法に基づき障がいのある方に対して創作活動や生産活動、社会との交流の機会を提供する支援機関です。
国が実施する地域生活支援事業の一環として位置付けられており、障がいのある方が地域で安心感をもって暮らせるよう支える役割を担っています。
もともと各地域にあった小規模作業所を引き継いで設立されたケースが少なくありません。その活動内容や利用方法は地域の実績に応じて異なり、提供する支援も多岐にわたります。
福祉ホーム
福祉ホームは、高齢者や障がいのある方、また経済的な理由により家庭での生活が困難な方に住まいと日常生活の支援を提供する施設です。
ある程度自立した生活が可能な方が対象であり、家庭のような環境で安心感をもって暮らせる生活の場を提供しながら、地域での生活を後押しする役割を担っています。
福祉ホームは小規模で運営されており、低価格で利用できる点が特徴です。そのため、地域の実情や個人の状況に応じた柔軟な支援が可能であり、入居者が地域で自分らしく生活を送るための支えの場といえるでしょう。
生活支援員の給与の目安

厚生労働省が公表しているデータによると、常勤の生活支援員の平均年収は約3,900,000円、非常勤の場合は平均時給が約1,431円とされています。
ただし、給与水準は勤務先の施設の種類や規模、介護職員処遇改善加算の取得状況などによって変動します。介護職員処遇改善加算とは、一定の要件を満たした事業所に対して介護職員の給与を引き上げるための、国から支給される補助金制度です。
介護職員の業務をかねている生活支援員も、この加算制度の対象となる場合があります。ただし、事業所が加算の届出をしていない場合は支給対象外となるため、事前に確認しておくことが大切です。
ハッシュタグ転職介護では、給与や勤務条件だけでなく、職場の雰囲気や人間関係といった“働きやすさ”にもこだわったご提案を行っています。
「もっと居心地のよい職場で働きたい」「人間関係に悩まない職場に転職したい」——そんなお悩みにも、専門のアドバイザーが丁寧にヒアリングを行い、あなたの希望に合った職場をご紹介します。
理想の働き方を叶えるために、今の悩みや理想の環境を私たちにお聞かせください。
まずは無料相談から、お気軽にご相談いただけます。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
生活支援員として働くには資格が必要?
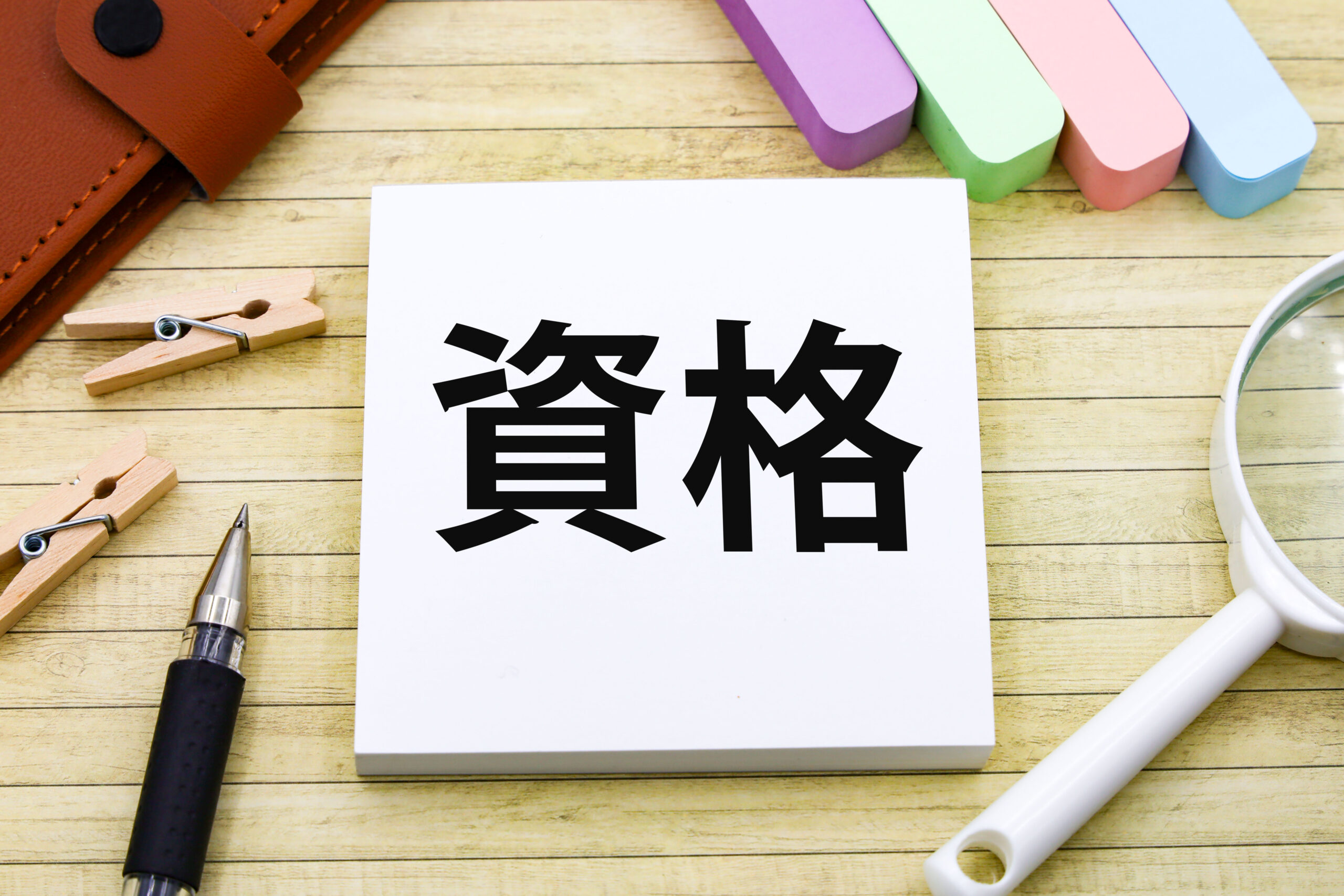
生活支援員として働くために、必ずしも資格が必要なわけではありません。事業所では、無資格や未経験者の採用も行っており、実務を通じてスキルを身につけていくことが可能です。
ただし、一定のキャリアを積んだ後、国家資格を取得することで職域の拡大や待遇面での優遇が見込まれるのも事実です。例えば、以下の資格があります。
- 介護福祉士:身体介護に強く現場リーダーを目指せる
- 社会福祉士:相談援助の専門家として幅広い福祉業務に対応
- 精神保健福祉士:精神障がいのある方への支援に特化
これらの資格を目標に、まずは現場での経験を重ねることで、より安定したキャリア形成が可能です。
ハッシュタグ転職介護では、あなたのライフスタイルや理想の働き方に合わせた職場探しを、とことん寄り添いながらお手伝いしています。
「家庭と両立したい」「自分のペースで働ける職場を探したい」など、どんな希望や不安も遠慮なくお聞かせください。
私たちは一人ひとりに向き合い、時間をかけて丁寧にヒアリングを行いながら、安心感を持って長く働ける職場をご提案します。
まずは無料相談で、あなたの理想や条件をお聞かせください。
ハッシュタグ転職介護が、あなたの「こう働きたい」を実現するために全力でサポートします。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
生活支援員を目指すなら、まずは無料でキャリア相談してみよう

生活支援員の仕事に興味はあるけれど、自分に向いているのかわからず迷っていませんか。福祉の仕事は、やりがいのある分野ですが現場の雰囲気や仕事内容、自分の性格との相性など実際に働いてみないとわからない不安もあります。
そこでおすすめしたいのが、福祉業界に詳しいアドバイザーのサポートを活用することです。
転職活動を一人で悩まず、まずはハッシュタグ転職介護のキャリア相談から一歩を踏み出してみませんか?
私たちは、SMSやメールを通じて1日5〜6回のこまめな連絡体制を整え、求職者の不安にとことん寄り添います。
孤独になりがちな転職活動をしっかり支えながら、面接の通過率アップにもつながる具体的なサポートを行っています。
「将来の働き方を見直したい」「安心できる転職活動をしたい」
そんな方にこそ、ぜひご利用いただきたいサービスです。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼






