常勤換算とは

常勤換算の言葉を聞いたことはあるけれど、どのような仕組みなのかよくわからない方がほとんどではないでしょうか。ここでは、常勤換算を解説します。
常勤換算の概要
常勤換算とは、介護施設で働いている職員の労働時間を基に算出した、常勤職員としての換算人数を表す指標です。介護施設ではフルタイムで働く正社員だけでなく、パートタイムやアルバイト、夜勤専従などのさまざまな働き方の職員がいます。
週20時間しか働かないパートと、週40時間働くフルタイムの職員を同じ1人として数えてしまうと労働力を正確に把握できません。
そこで登場するのが常勤換算です。すべての職員の労働時間を常勤の職員が何人働いているかに換算して、労働力を数値化する仕組みです。
常勤換算により、介護施設は労働力を正確に把握し、適切なサービス提供体制を維持できます。常勤換算は介護保険制度の根幹を支える重要な概念です。
常勤換算が必要な理由
常勤換算が必要な理由は、介護保険法で定められた人員配置基準を守るためです。介護保険制度では、利用者に質の高いサービスを提供するために、職種ごとの必要な職員数が決められています。
もし常勤換算の仕組みがなかったらどうなるでしょうか。例えば、週20時間勤務のパート3人と週40時間勤務のフルタイム1人を単純に4人と数えられてしまいます。しかし実際の労働力は、フルタイム換算で2.5人分に過ぎません。
差が積み重なると、表面上は基準を満たしているように見えても、実際には人手不足でサービスの質が低下してしまう可能性があります。そのため正確な労働力を把握する常勤換算が不可欠です。
人員配置基準とは

人員配置基準をなんとなく聞いたことはあるけれど、具体的にはよくわからない方も少なくないです。ここでは、人員配置基準を解説します。
人員配置基準の定義

人員配置基準とは、介護施設と事業所を運営する際に満たすべき職員の配置人数の基準です。厚生労働省が、安全性を重視し質の高いサービスを提供するために、サービス種別ごとに必要な配置人数を定めています。
この基準は、利用者の安全性を考慮し、質の高いケアを提供するための下限ラインです。人員配置基準は介護保険法に基づいています。
現場で起こりうる想定外のトラブルや、万が一事故が発生した際にも、早期発見と迅速な対応ができるよう設定されています。対象となる職種は以下のとおりです。
- 管理者
- 介護職員
- 看護職員
- 生活相談員
- 機能訓練指導員
- 栄養士
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)
それぞれの職種に対して、常勤や専従、常勤換算などの条件が細かく設定されています。適切な人員配置があると、一人ひとりの負担が過度にならないような働ける環境が整います。
人員配置基準の例外
人員配置基準は原則として厳守すべき基準ですが、一定の条件下では例外的な取り扱いが認められる場合があります。例外が認められる主なケースは以下のとおりです。
- 関連法の改正で制度移行中の場合
- 新型コロナウイルス感染拡大のような緊急事態
- 産前産後休業や介護休業取得時の代替職員配置
2021年度の介護報酬改定では、新しい取り扱いが導入されました。本来常勤として勤務していた職員が産前産後休業や介護休業を取得した際に、同様のスキルを持つ複数の非常勤職員を常勤換算します。非常勤職員の常勤換算によって、人員配置基準を満たせるようになりました。
人員配置基準を正しく理解して、安心感のある職場を見つけませんか?
ハッシュタグ転職介護では、各施設の人員配置状況を丁寧に確認したうえで求人をご紹介しています。
介護業界に精通した専門アドバイザーが、配置基準に関する疑問にもわかりやすくお答えし、安心感を持って働ける職場探しをしっかりとサポートします。
また、スピード感のある一気通貫型の人材紹介を採用しており、キャリア相談から面接対策、入社後のフォローまで同じ担当者が対応するため、転職活動もスムーズに進められます。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
介護施設ごとの人員配置基準

施設によって忙しさが違うのはなぜかと疑問に思ったことはありませんか。介護施設の種類によって人員配置基準が大きく異なります。ここでは、介護施設ごとの人員配置基準を解説します。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム(特養)は、要介護度の高い方が多く入所される施設です。そのため、手厚い人員配置が求められています。基本的な人員配置基準は以下のとおりです。
- 管理者:1人(常勤または専従)
- 介護職員:入所者3人に対して1人以上(常勤換算)
- 看護職員:常勤1人以上
- 生活相談員:入所者100人までは1人以上
- 機能訓練指導員:常勤1人以上
- 介護支援専門員:常勤1人以上
特養では3対1の配置基準が基本です。入所者3人に対して介護職員1人以上の配置が義務付けられています。
特養では、日常生活全般にわたって支援が必要な方がほとんどのため、24時間体制でのケアが必要です。夜間帯も一定の職員配置が維持され、緊急時にも迅速な対応ができる体制が整えられています。
介護老人福祉施設

介護老人福祉施設は、特別養護老人ホームとほぼ同様の人員配置基準が適用されます。入居者3人に対して常勤介護職員1人以上の基本的な配置比率は変わりません。
介護老人福祉施設では、入居者の自立支援と在宅復帰を目指したサービスが提供されます。そのため、機能訓練や生活指導にも重点が置かれ、多職種連携による包括的なケアが特徴です。
介護老人保健施設
介護老人保健施設(老健)は、医療ケアやリハビリに重点を置いた施設です。そのため、医療寄りの人員配置が特徴となっています。基本的な人員配置基準は以下のとおりです。
- 管理者:1人(常勤または専従)
- 介護職員や看護職員:入所者3人に対して1人以上
- 医師:常勤1人以上
- 理学療法士や作業療法士:必要数
- 介護支援専門員:入所者100人までは1人以上
注目すべきは、看護職員の配置割合が高い点です。介護職員や看護職員の配置のうち、看護職員は7分の2程度確保される必要があります。
老健では、医療的ケアが必要な方や、リハビリテーションを通じて在宅復帰を目指す方がほとんどです。医師や看護師、リハビリ専門職の配置が充実しており、医療と介護の両面からのアプローチが可能な体制が整えられています。
認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症の方を対象とした小規模な施設です。家庭的な環境でのケアが特徴で、1ユニットの人数は9人までとなります。基本的な人員配置基準は以下のとおりです。
- 管理者:1人(常勤または専従)
- 介護職員:利用者3人に対して1人以上(常勤換算)
- 計画作成担当者:1人以上
グループホームでは、認知症ケアの専門性が重視されます。そのため、スタッフには認知症介護に関する研修の受講が義務付けられています。
またグループホームでは少人数でのケアが行われるため、職員と利用者の距離が近く、個別性を重視したケアの提供が特徴的です。家事活動への参加や役割分担など、残存機能を活かした支援がされています。
短期入所生活介護
短期入所生活介護(ショートステイ)は、特別養護老人ホームに準じた人員配置基準が適用されます。利用者の短期的な滞在を前提としているため、一部の職種では兼務が認められています。
ショートステイは、在宅介護を支援するサービスです。家族の休息や急用時の一時的な利用から、定期的な利用まで、さまざまなニーズに対応できる柔軟な体制が求められます。
通所介護

通所介護(デイサービス)は、日中のみのサービスであり、夜間の人員配置基準はありません。基本的な人員配置基準は以下のとおりです。
- 管理者:1人(常勤または専従)
- 生活相談員:1人以上(専従)
- 看護職員:1人以上(専従)
- 介護職員:利用者数に応じて配置(常勤換算)
- 機能訓練指導員:1人以上
デイサービスでは、利用者数に応じて介護職員数が変わるのが特徴です。15人を境に配置基準が変わるため、施設の規模によって働く環境も大きく異なります。
デイサービスは、利用者の社会参加促進や機能維持および向上が目的です。レクリエーション活動や機能訓練プログラムが充実しており、利用者の生活の質向上に重要な役割を果たしています。
配置基準を知ることで、「なぜこの施設は忙しいのか」「どの職場が自分に合っているのか」といったことを客観的に判断できるようになります。
ハッシュタグ転職介護では、各施設の特徴や人員配置状況を熟知した介護業界専門のアドバイザーが、あなたの希望や働き方に合った職場をご提案します。
特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)、グループホームなど、「どの施設が自分に合っているのかわからない」と悩んでいる方も、まずはお気軽にご相談ください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
常勤換算を計算するための手順と計算方法
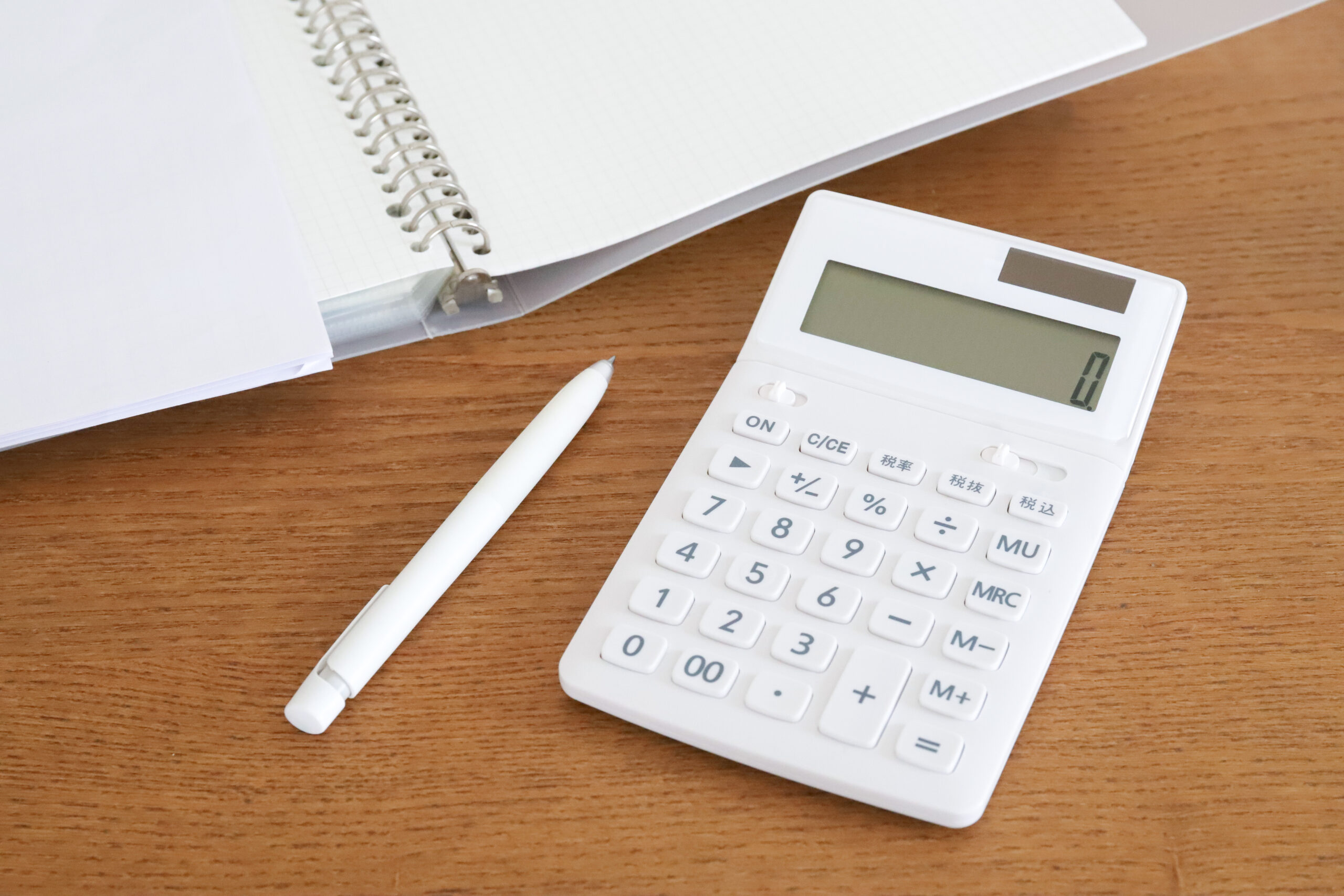
自分の職場は本当に基準を満たしているのかという疑問を解決するために、常勤換算を計算してみましょう。
常勤スタッフ数と週あたりの労働時間を把握する
まず、施設の所定労働時間を確認しましょう。一般的には1日8時間×週5日=週40時間が標準です。
ただし、就業規則によっては所定労働時間が異なる場合があります。週32時間に設定している施設もありますが、常勤換算の計算では少なくとも週32時間として計算する必要があります。
次に、常勤職員の人数のカウントです。常勤職員は1人=1.0人として計算します。例として、所定労働時間が週40時間の施設で、常勤職員が10人いる場合は常勤職員10人(10.0人として計算)です。
重要なポイントは、常勤職員の有給休暇や出張は勤務時間として計算されることです。実際に現場にいなくても、労働契約上の時間としてカウントされます。
非常勤スタッフの労働時間を計算する

常勤スタッフ数を算出した後、非常勤職員の労働時間を計算しましょう。これが常勤換算の難しい部分です。所定労働時間が週40時間を例として、非常勤職員3名の週労働時間を以下のとおりに設定します。
- Aさん:週20時間
- Bさん:週24時間
- Cさん:週28時間
計算方法は、72時間(非常勤の合計週労働時間)÷40時間(所定労働時間)=1.8人(常勤換算上の人数)となります。つまり、上記3名の非常勤職員は、常勤換算で1.8人分に相当します。
計算を行う際は各職員の勤務時間を正しく把握しましょう。シフト表や勤務記録をもとに、1ヶ月間の平均的な勤務時間を算出し、週単位に換算して計算します。
常勤スタッフと非常勤スタッフの平均人数を合算する
常勤と非常勤職員の常勤換算人数を合計します。上記の例で計算すると、以下のとおりです。
- 常勤職員:10.0人
- 非常勤職員(常勤換算):1.8人
- 合計:11.8人
計算結果11.8人が、当該事業所の常勤換算上の人数です。単位は人数とし、小数点以下第2位は切り捨てます。
常勤換算は毎月の実施が推奨されます。職員の入退職や勤務時間の変更により、常勤換算人数は変動するためです。また、人員配置基準を満たしているか継続的にチェックすることで、基準違反のリスクを未然に防げます。
常勤換算をするときの注意点
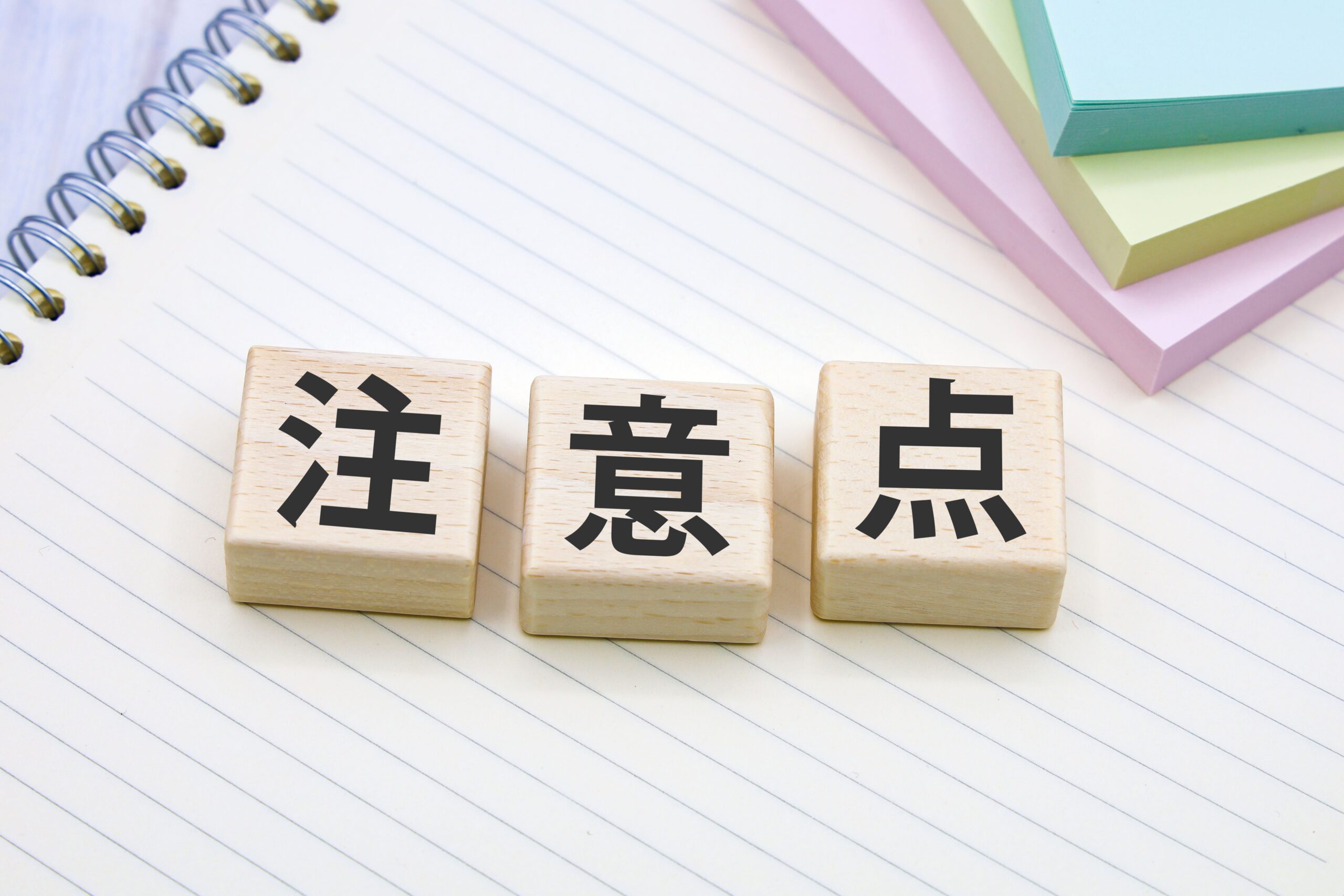
常勤換算の計算は、一見シンプルに見えますが、細かな注意点があります。ここでは、常勤換算時の注意点を見ていきましょう。
有給休暇や出張の扱い
常勤換算では、有休や出張の取り扱いは常勤者か非常勤者かで大きく変わります。
常勤の場合は有休や出張も勤務時間として計算に含みます。これは、労働契約に基づいた所定労働時間がベースになっているためです。
しかし、非常勤の場合は計算に入れることはできません。非常勤職員は、働いた時間のみが計算対象となります。ただし、常勤者でも長期出張や休暇が暦上で1ヶ月を超えたときには計算から除外します。
育児休暇の扱い
育児休暇は特に注意が必要です。産後休暇や育児休暇は基本的には1ヶ月を超える長期休暇になるため、常勤換算の計算には含まれません。
ただし、育児休業明けで短時間勤務をしている常勤職員は、特別な取り扱いがあります。以下の3つの条件をすべて満たしている場合に限り、常勤の所定労働時間数を週30時間として計算できます。
- 就業規則に育児短時間勤務職員の勤務時間が明確に定められている
- 勤務時間が週30時間以上ある
- 利用者の処遇に支障がない体制を整えている
この特例により、週30時間勤務の育児短時間勤務職員は、常勤換算で1.0人として計算できます。
兼務の扱い
複数施設や複数職種を兼務する場合は、慎重な取り扱いが必要です。1つの法人が同一敷地内で運営する施設で、並行的に業務を行っても差し支えがないと判断される場合は、常勤換算が可能です。
一方で、事業所間の距離が離れている場合や並行して行うことが困難な業務は、それぞれ時間を分けて計算しなければなりません。
注意点を理解することで、常勤換算の計算もより正確にできるようになります。適切な人員配置がされている職場で働きたいと考えている方は、専門のアドバイザーに相談してみてはいかがでしょうか。
ハッシュタグ転職介護では、労働条件や人員体制などの詳細を丁寧にご説明し、不安の少ない職場環境をご紹介しています。
求職者一人ひとりの希望や悩みにとことん寄り添い、納得のいく職場選びをサポートしています。
まずは無料相談で、あなたの理想の働き方についてお聞かせください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
介護施設が人員配置基準に違反するとどうなる?

勤務先が基準を満たさない可能性に不安を覚えたことはありませんか。人員配置基準違反は、介護施設にとって、深刻な問題です。
監査の流れとして、6年以内に1度行われる施設の実施指導で、人員配置基準違反が疑われた場合、監査が入ります。監査では、勤務表や労働契約書などの詳細な確認が行われます。主な処分内容は以下のとおりです。
- 人員基準欠如減算:基本報酬が70%に減額される
- 改善勧告:期限付きでの改善指導
- 新規受け入れ停止:一定期間の新規利用者受け入れ停止
- 事業の停止:事業の一部または全部の停止
- 指定取り消し:5~10年間の再指定禁止
重い処分は、指定取り消しです。介護事業は都道府県知事の指定を受ける必要があるため、取り消し処分となると、5〜10年は再度指定を受けられません。
職員への影響も考えられるでしょう。違反が発覚した場合に給与の遅配や減額、雇用の不安定化、転職を余儀なくされる可能性があります。利用者へのサービス低下も避けられません。そのため、適切な人員配置が守られている職場を選ぶことが大切です。
また、処分を受けた施設は社会的な信用を失うことになり、新規職員の採用や利用者の確保が困難になるケースも少なくありません。施設が信用を失うと、立て直しには長期間を要します。
人員基準違反のリスクがない、しっかりとした運営体制の施設で働きたいとお考えの方は、ハッシュタグ転職介護にご相談ください。
私たちは法令を遵守した安心感のある職場にこだわり、長期的に働ける環境をご紹介しています。
介護業界に精通した専門アドバイザーが、一人ひとりの希望や不安に丁寧に寄り添いながら適切な職場をご提案します。
働き方や職場の雰囲気、制度面など、求人票だけではわからない情報も詳しくお伝えしています。
まずは無料相談で、あなたの理想の働き方をお聞かせください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
介護施設の常勤換算を正しく理解しよう

ここまで、常勤換算の計算方法や人員配置基準などを詳しく解説してきました。常勤換算の知識を身につけると、自身の職場の状況を客観的に判断できるようになったのではないでしょうか。常勤換算を理解するメリットとして、以下が挙げられます。
- 職場の適正性を判断できる
- 転職時の職場選びに活用できる
- 職場での提案ができる
人員配置基準は、利用者の安全性を重視し、職員の働きやすさを守るための基準です。基準ギリギリで運営している施設では、職員の急な退職や体調不良で、気づいたときには基準違反になってしまう可能性があります。
転職を考えている方は、適正な人員配置がされている職場を選ぶことで安心感を持ち、長期で働くことができるでしょう。面接時には、以下のような質問がおすすめです。
- 人員配置基準は満たしていますか
- 常勤換算での職員数はどのくらいですか
- 職員の定着率はどうですか
これらの質問により、施設の運営状況や働きやすさを事前に把握できます。人員配置に関する質問に明確に答えられる施設は、適切な管理体制が整っていると期待できるでしょう。
ハッシュタグ転職介護は、医療・福祉業界に特化した転職支援サービスとして、各施設の人員配置状況や労働環境を事前にしっかり確認したうえで求人をご紹介しています。
一人の担当者が最初の相談から求人提案、面接対策、内定後の調整まで一貫してサポートするため、スピード感をもった対応が可能です。
「人手不足で毎日バタバタする職場は避けたい」「法令違反のない安心できる施設で働きたい」という方に向けて、専門アドバイザーがとことん寄り添いながら適切な職場をご提案します。
不安を抱えたまま働き続けるのではなく、まずは無料相談であなたの理想や悩みをお聞かせください。納得感のある転職を一緒に実現しましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼






