福祉用具専門相談員とは

福祉用具専門相談員は福祉用具を取り扱う事業所に勤務し、利用者や家族へ用具の使い方や選び方などをわかりやすく説明する福祉用具のスペシャリストです。
取り扱う用具には介護ベッドや車いす、歩行器やポータブルトイレなどさまざまなものがあります。また在宅介護に使用する手すりやスロープなども対象内です。
ここでは福祉用具専門相談員における役割や配置の義務付けを確認してみましょう。
役割
福祉用具専門相談員は利用者の介護度や居住環境に応じた福祉用具の選定や使用方法の説明、アドバイスなどを行っています。
利用者と相談をしながら福祉利用計画書を作成し、計画書に基づいて適切な器具を選定します。また用具の提供後も定期的に訪問し、使用状況の確認や調整を行うなど幅広いサポートを通して自立しやすい環境を作っていくことも大切な役割です。
配置の義務付け
福祉用具専門相談員は介護保険制度に基づき、福祉用具のレンタルや販売を行う事業所で配置が義務付けられています。
具体的には一つの事業所あたり常勤換算で2名以上の配置が義務付けられています。
事業所が福祉用具事業の販売やレンタルを行うためには都道府県からの指定を受ける必要があり、その際に福祉用具専門相談員の配置が必須要件となっているためです。
福祉用具専門相談員の仕事内容

福祉用具専門相談員の役割や配置の義務付けについて解説しました。では福祉用具専門相談員の仕事内容には、どのような業務があるのでしょうか。
福祉用具専門相談員の仕事は、単に福祉用具を提供するだけではありません。具体的には以下のような業務を実施しています。
- 利用者に合った福祉用具の選び方をアドバイスする
- 福祉用具の利用計画を立てる
- 利用者に合わせて福祉用具の調整を行う
- 福祉用具の取り扱いを説明する
- 定期的に福祉用具の点検や使用状況の確認を行う
ここでは福祉用具専門相談員の行う具体的な仕事内容を順番に解説します。
利用者に合った福祉用具の選び方をアドバイスする
福祉用具は利用者自身が使うため、一人ひとりの介護度や生活環境に応じた的確な用具の選定が必要です。
具体例を挙げると、自立歩行が難しい方には歩行器や杖を、屋外での移動が多い方には車いすを提案します。
利用者や家族から身体的な状況や居住環境、使用目的などを丁寧に聞き取り、転倒リスクなども考慮したうえで適切な福祉用具の提供が望まれるでしょう。
福祉用具の利用計画を立てる
福祉用具を提供する際には、介護保険制度に基づき事前に福祉用具利用のための計画書を作製します。この計画書は利用者が福祉用具を安全かつ有効に使うために必要な書類です。
具体的な例として、寝たきりを予防するために起き上がりやすいベッドを導入する、誤嚥リスクを軽減するためにベッドの角度を調整しやすいタイプを検討してみるなどわかりやすく記載します。
計画書の作製はケアマネジャーや関係するスタッフと情報を共有しながら進めることが大切です。また、ケアプランとの調整を図りながら利用者へ適切な介護支援を提供するうえでとても重要な業務となります。
利用者に合わせて福祉用具の調整を行う
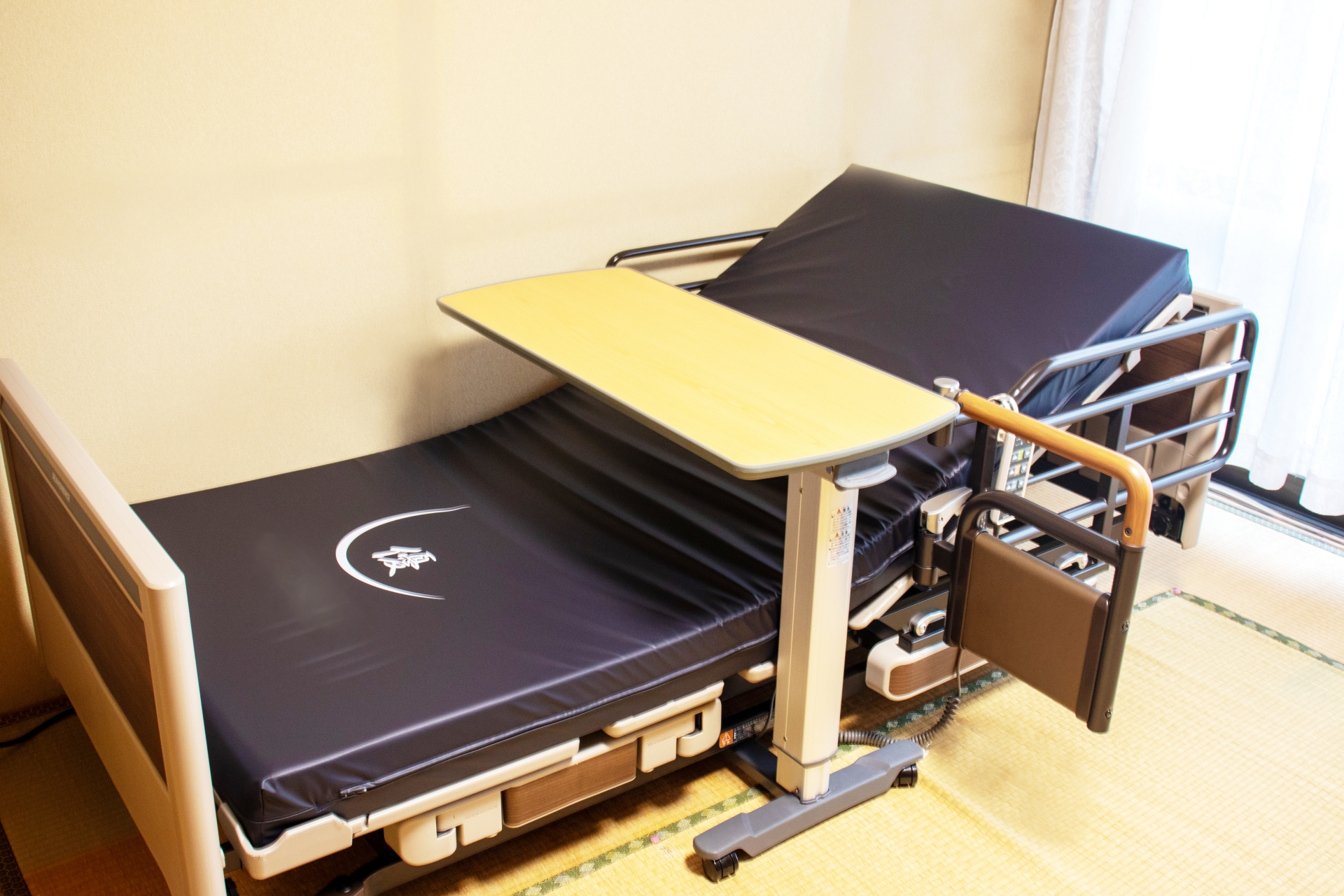
用具を導入したら終わり、というわけではありません。導入後は利用者が正しく用具を使えているか、不具合はないかなど細やかに使用状況をチェックします。
車いすの座面を調整したり、自宅での手すりの位置を調整したりするなど、利用者の状況に応じて使いやすい状態に用具を調整していく必要があるのです。
導入後も定期的に利用者のもとへ訪問し使用状況を確認することで、用具を快適に使い続けられ、転倒などの事故予防にもつながるでしょう。
福祉用具の取り扱いを説明する
利用者や家族が福祉用具を正しく使用するために、取り扱い方法の説明も福祉用具専門相談員として大切な業務です。
介護ベッドの角度調整の方法や車いすのブレーキ操作など用具を安全に使うために、わかりやすい説明が求められます。
また、言葉による説明だけでなく、実演を交えて教えることで利用者の理解も深まりやすいでしょう。
誤った使用方法で事故を起こさないためにも、利用者が正しく使えるよう丁寧な説明を心がけましょう。
定期的に福祉用具の点検や使用状況の確認を行う
福祉用具は頻繁に使用されているため、定期的なメンテナンスが必要です。例えば歩行器のブレーキが甘くなっていないか、ベッドのリモコンが正常に作動するかなど、定期的な確認が必要です。
また利用者自身の身体状況も日々変化していくものです。以前は自立できていた動作も次第にできなくなることも十分に考えられるでしょう。
介護度が進行しているのであれば利用者や家族、ケアマネジャーなどに相談し、別の用具への変更を提案します。
ハッシュタグ転職介護では、介護業界に精通した経験豊富なアドバイザーが、転職活動を全面的にサポートしています。
同じ専門アドバイザーが担当する一気通貫型の仕組みを導入しているため、面接対策や履歴書の書き方アドバイスなど、一人ひとりに寄り添った就職支援が実現可能です。
さらに、福祉用具専門相談員に関する相談も随時受け付けており、業務に関する詳細な情報やアドバイスを提供しています。
「福祉用具専門相談員として活躍したい」
「福祉用具に関する専門知識を深めたい」
など、気になることがあれば、いつでもハッシュタグ転職介護の無料相談であなたの想いをお聞かせください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
福祉用具専門相談員の要件を満たす資格
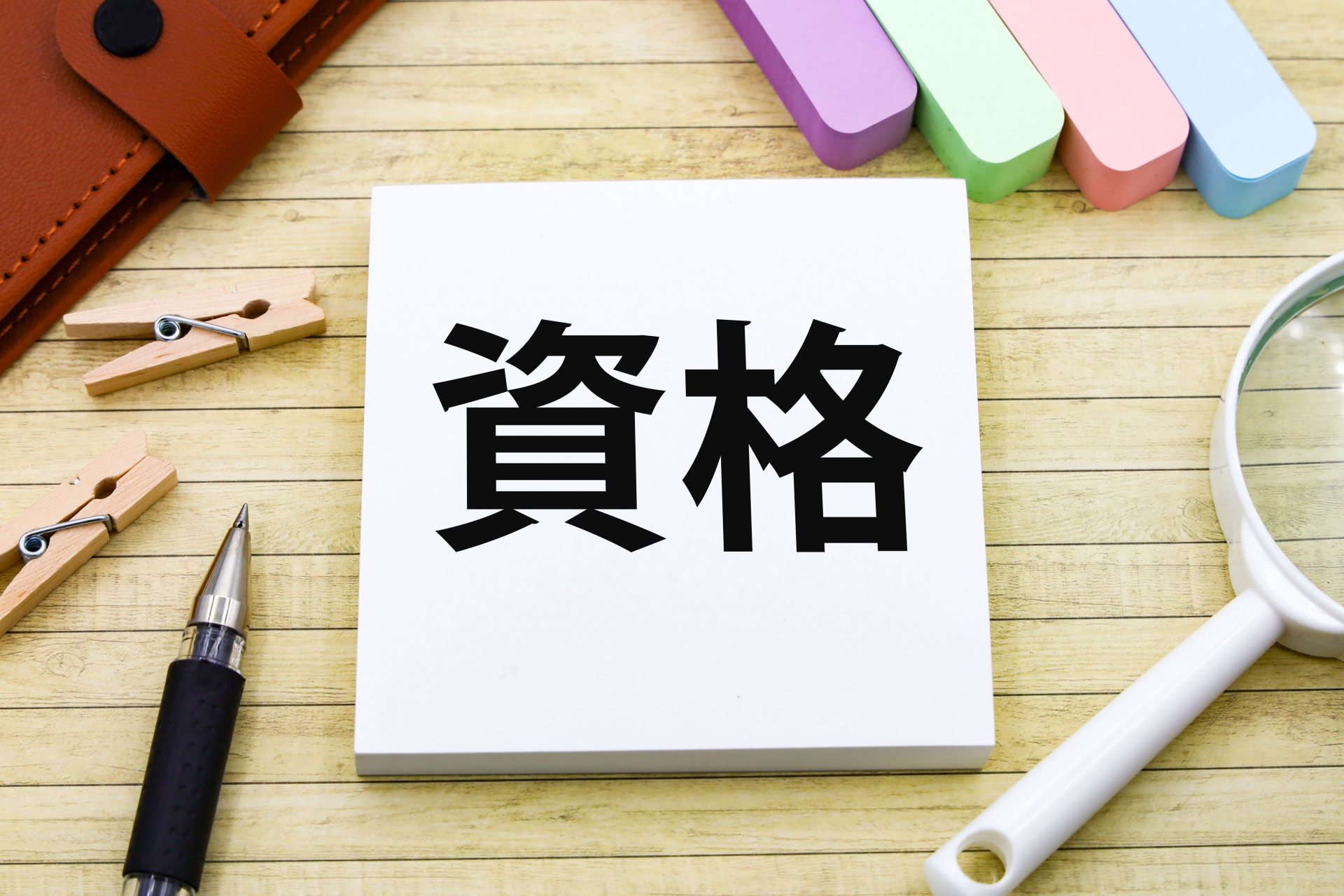
福祉用具専門相談員の仕事内容を解説しました。では、実際に福祉用具専門相談員を目指すには、どのような方法があるのでしょうか。
福祉用具専門相談員は特定の国家資格ではありませんが、所定の要件を満たすことで相談員としての業務を行えます。
具体的には以下の2つの方法があるでしょう。
- 介護福祉士や看護師、理学療法士などの国家資格保有者であること
- 福祉用具専門相談員指定講習の修了者であること
介護福祉士や看護師、保健師・理学療法士・義肢装具士など介護保険法施行規則によって定められた国家資格を有する方は特別な講習を受けなくても福祉用具専門相談員の業務に携われます。
実際にこれらの国家資格を持つ方が、現場で培ってきた経験を活かし、福祉用具専門相談員として活躍の場を広げています。
ただし、国家資格がない方でも所定の講習を修了すれば福祉用具専門相談員の業務に就くことは可能です。
福祉用具専門相談員として業務を行うためには、都道府県知事などの指定を受けた講習機関が行う福祉用具専門相談員指定講習を受講するのがよいでしょう。
福祉用具専門相談員の資格取得方法

福祉用具専門相談員になるためには一部の国家資格保持者の方を除いて、都道府県知事などが指定する機関で講習を受ける必要があることを解説しました。
ここからは一部の国家資格を有していない方を対象にした、福祉用具専門相談員になるための資格取得方法や流れを解説します。
受講までの流れを把握し、資格取得への積極的なチャレンジにつながると幸いです。
福祉用具専門相談員指定講習を受講する
福祉用具専門相談員指定講習を受講するにはまず、ホームページなどで都道府県の指定を受けた講習機関を探しましょう。
都道府県により応募条件に若干の違いがあるものの、一般的には受講資格の制限はないため、どなたでも受講可能です。受講したい講習機関の募集要項にしたがって申し込み、受講料を支払います。
福祉用具専門相談員指定講習は50時間のカリキュラムで構成されており、介護保険や福祉用具に関する知識を実践演習を交えて学びます。
講義はオンライン形式や対面形式などがありますが、数日間に及ぶため、あらかじめスケジュールに余裕をもって臨むことが大切です。
修了評価を受ける

すべての講習を終えると最終日に修了評価を行います。評価は筆記試験が主な内容で、一定の基準に合格すれば修了証が交付されます。
ただし、全カリキュラムの受講が修了の条件になるため、日頃から体調管理や勤務先でのシフト調整に配慮しましょう。
私たちハッシュタグ転職介護は、求職者を人生のキャリアパートナーとして捉え、転職への希望や悩みにとことん寄り添う姿勢を大切にしています。
また、就職後も定期的に連絡を取り、現場での悩みや将来のキャリアについての相談にも対応しています。転職後も安心感を持って働ける環境作りをサポートし、着実にキャリアを積み重ねられるようお手伝いします。
「就職が決まっても相談できる環境が欲しい」
「転職後も着実にキャリアを積み重ねたい」
など、希望がありましたら、ぜひ一度ハッシュタグ転職介護の無料相談をご利用ください。私たちの専門アドバイザーが、あなたのキャリア形成を全力でバックアップいたします。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
指定講習の主な学習内容
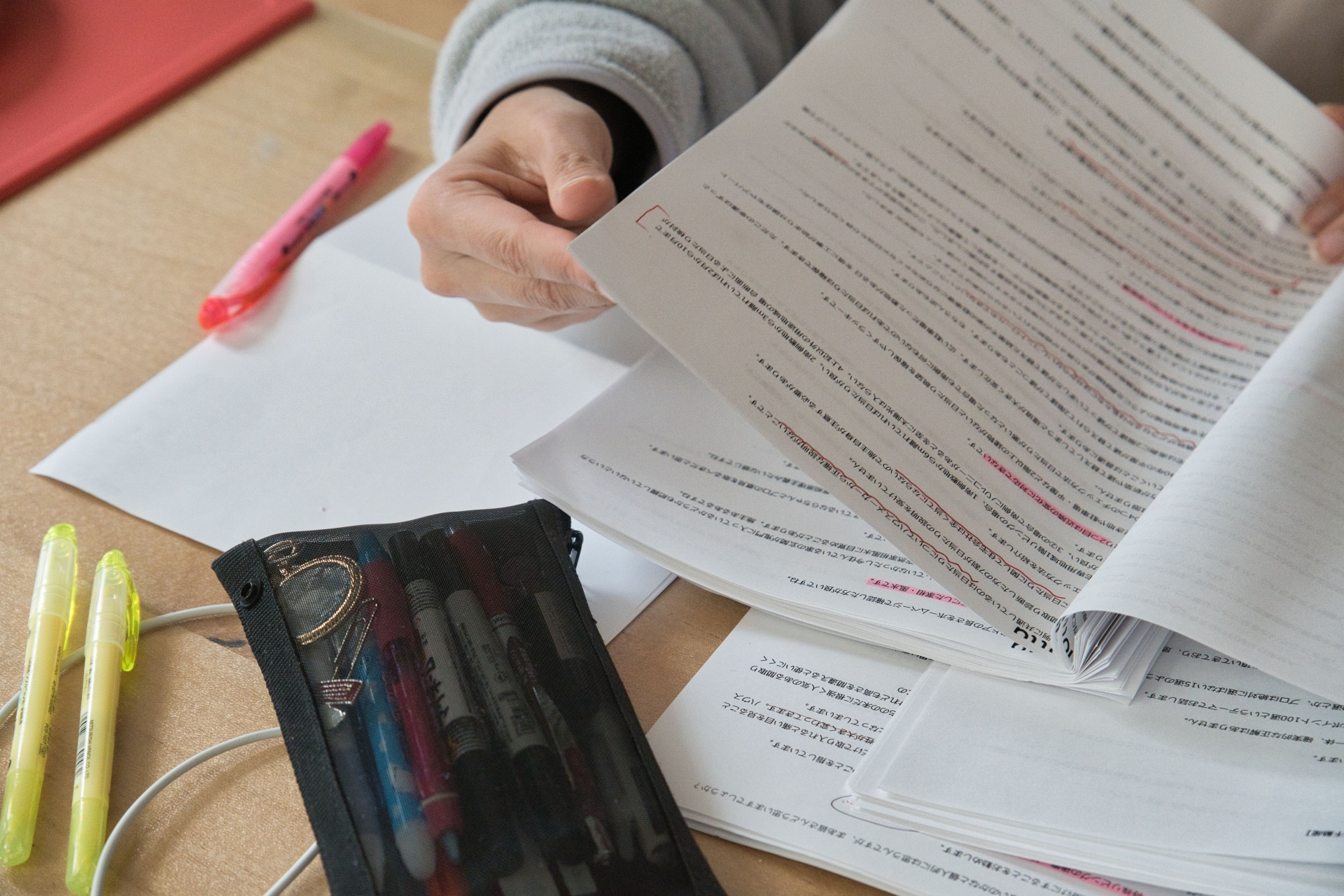
指定講習では福祉用具専門相談員としての専門的な知識や技術などさまざまなカリキュラムを学びます。
しかし、具体的な学習内容がわからず学習についていけるのか不安に思う方もいるのではないでしょうか。
指定講習で行われている主な学習内容は以下のとおりです。
- 福祉用具専門相談員の役割
- 介護保険制度に関する基礎知識
- 高齢者の介護や医療に関する知識
- 個別の福祉用具に関する知識や技術
- 福祉用具のサービスの仕組み
- 福祉用具の利用支援に関する知識と総合演習
上記の講習内容を通して福祉用具に関する専門知識と実践的な対応力が身に付き、現場でも即戦力として活躍が期待されるでしょう。
ここからは指定講習で行われている主な学習内容をみていきましょう。
福祉用具専門相談員の役割
講習では単に福祉用具の扱い方を学ぶだけではありません。福祉用具専門相談員としての役割を知り、現場での関わり方を学んでいきます。
福祉用具の活用により、利用者が安全にかつ快適な生活が送れるよう業務に取り組みます。これにより利用者の自立を支え、生活の質の向上を目指せるでしょう。
また介護度の変更に伴い利用している用具の再検討も行い、利用者が適切に用具を使える状態にすることも大切な役割です。
介護保険制度に関する基礎知識

介護用具の提供では介護保険制度のルールに基づいて行われるため、介護保険制度の理解は利用者に適切な用具のアドバイスを提供するうえで不可欠です。
講習では要介護認定の流れや保険給付の仕組み、用具の導入方法など幅広く学んでいきます。
具体的には電動ベッドはレンタルの対象ですが、ポータブルトイレや風呂の椅子などは購入対象に分類されます。
介護保険制度に基づき、福祉用具のレンタルや購入対象となる品目を利用者の介護度と照らし合わせながら選定します。
高齢者の介護や医療に関する知識
福祉用具は高齢者の利用が多く、高齢者の身体や医療に関する知識を得ることも大切です。
具体的には身体機能の低下や認知症、生活習慣病などの病気への理解が求められます。高齢者の身に起きやすい身体の変化を理解することで、一人ひとりに適した用具の選定が可能となります。
また麻痺や関節の拘縮などに対応したリハビリの基本を知ることで、医療や介護スタッフとの連携が取りやすくなり、車いすなどの用具選定がしやすくなるでしょう。
個別の福祉用具に関する知識や技術

講習では介護ベッドや車いす、歩行器など介護の現場で必要となる器具の取り扱い方を数多く学びます。
どのくらいの介護度の方が使用に適しているか、注意すべき点は何かなど一つずつ深く知ることで使用者の体格や身体的な状況に合ったものを選定できるでしょう。
また実技では福祉用具の組み立てや調整、安全面の確認作業を実際に行います。これにより現場で即戦力として活躍できる技術を多く学べるでしょう。
福祉用具のサービスの仕組み
レンタル品の交換時期や故障時の早急な対応など、福祉用具のサービスの仕組みを理解することも大切な学習です。
また福祉用具の導入の際に利用者や家族へレンタルの仕組みや注意事項などをわかりやすく伝える必要があります。
サービスの仕組みを通して福祉用具を円滑に導入し、介護しやすい環境づくりに大きく貢献できるでしょう。
福祉用具の利用支援に関する知識と総合演習

講習の後半では実際の利用者事例を参考にしながら、福祉用具専門相談員として用具の選定や利用支援に関する総合的な演習に取り組みます。
具体的には用具の選定や利用計画書の作製、導入・アフターフォローに至るまで一連の流れを実際に体験しながら学びます。
業務の全体像を把握することで、実際の現場を想定した実践的な内容を学ぶことができるでしょう。
私たちハッシュタグ転職介護は医療や福祉業界に特化した人材紹介を得意とする会社です。
求職者と雇用先の双方に丁寧なヒアリングを行い、できる限り雇用のミスマッチを起こさない転職支援を実現しています。
また福祉用具専門相談員などの専門職を目指したい方には、具体的な取得方法や専門スキルを活用できる職場紹介も積極的に行っています。
プロ視点の的確なアドバイスにより、働きながら理想とするキャリアを目指せるでしょう。
「福祉用具専門相談員になるための方法を知りたい」「働きながら専門職の資格を取得したい」などお考えの方は、介護業界に精通したアドバイザーが在籍するハッシュタグ転職介護へぜひご連絡ください。
無料相談であなたに合ったキャリアの築き方をご提案いたします。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
福祉用具専門相談員資格の取得難易度と必要な費用

福祉用具専門相談員の資格に興味があるけれど、難易度が高いのではないか、費用が高額になるのではないかと不安に感じていませんか。
たしかに、福祉用具専門相談員になるためには医療や介護の知識や実践スキルなど、学ぶべきことはたくさんあります。
しかし、介護の現場経験のある方にとっては理解できるものも多いため、決して取得困難な資格であるとはいえないでしょう。
さらに国家試験のような難しい試験があるわけではなく、講習受講後の修了評価(筆記試験のようなもの)に合格すれば資格が取得できます。
講習をしっかり聞き理解できれば、十分に資格取得が目指せるといってよいでしょう。
講習の費用に関しては地域や講習機関によってさまざまです。おおよそ20,000円から50,000円の範囲内で受講できる講習機関が多く見られます。
また、講習機関によっては厚生労働省の定める特定一般教育訓練制度の対象となるケースもあるため、条件を満たせば雇用保険より受講費用の一部給付が認められます。
受講したい機関のホームページなどで費用や特定一般教育訓練制度の対象機関であるかの確認をするとよいでしょう。
ハッシュタグ転職介護は無料相談であなたの転職に関する悩みを丁寧にヒアリングしています。また現在働きながら転職を考えている方でも、希望や状況に合ったキャリアの提案を実施しています。
「今の職場での労働環境に不満がある」「転職のための具体的な準備内容を知りたい」など、疑問に思うことがありましたらぜひ一度ハッシュタグ転職介護の無料相談であなたの想いをお聞かせください。
私たちと一緒に転職への新たな一歩を踏み出しましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
福祉用具専門相談員を取得して求められる人材を目指そう

福祉用具専門相談員の仕事内容や資格取得の方法、指定講習の学習内容などを解説しました。
高齢化が進むなか、福祉用具の需要が高まるにつれて専門相談員の必要性も増加傾向です。
福祉用具専門相談員の資格取得により施設や在宅、販売事業所など多様な現場で活躍が期待されるでしょう。
福祉用具専門相談員に興味のある方はぜひ資格を取得し、現場から求められる人材を目指してみてはいかがでしょうか。
ハッシュタグ転職介護では福祉用具専門相談員になるための具体的なキャリアプランをわかりやすくご紹介しています。
介護業界に精通した専門アドバイザーが現場で活躍するためのノウハウを丁寧に提供し、理想に合った働き方を全力でサポートします。
「一人で転職活動をするのが心配」「自分に合った職場を一緒に探してほしい」など、どのような相談でも構いませんので、ぜひ一度ハッシュタグ転職介護の無料相談をご利用ください。
あなたの就職へのお悩みを、私たちと一緒に解決していきましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼






