介護福祉士国家試験とは

介護福祉士国家試験は、介護分野における唯一の国家資格を取得するための試験です。
介護福祉士とは、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者と定義されています。
この資格は、高齢化が進む日本において、介護サービスの質の向上と専門性の確保を目的として設けられた重要な資格です。介護福祉士の取得により、介護現場でリーダーシップを発揮し、より高度な介護技術と知識を活用したケアを提供できます。
受験資格
介護福祉士国家試験の受験資格は、複数のルートが設けられており、現在の職歴や学習歴に応じて選択できます。3年以上(従業期間3年以上(1,095日以上)、従事日数540日以上)介護等の業務に従事した方で、実務者研修を修了した方が最も一般的な実務経験ルートです。
このルートでは継続的な実務経験が重視されており、介護現場での豊富な実践経験を通じて必要なスキルを身につけていることが前提となります。3年以上(従業期間3年以上(1,095日以上)、従事日数540日以上)介護等の業務に従事した方で、介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修(第1号研修または第2号研修)を修了した方も実務経験ルートの受験資格となっています。
また、介護福祉士養成施設(2年以上)を2017年4月以降に卒業(修了)した方や介護福祉士養成施設(1年以上)を2017年4月以降に卒業(修了)した方が養成施設ルートの対象です。
このルートは体系的な理論学習と実習を組み合わせた教育を受けることができるため、基礎からしっかりと学びたい方に適しています。
2009年度以降に、福祉系高校に入学して、必要な科目を履修して卒業した方が福祉系高校ルートの対象となります。
高校在学中から介護を専門的に学んでいるため、若い世代で介護福祉士を目指す方の主要なルートとなっているのです。
あなたに適切なルートで介護福祉士を目指すためには、転職先も自分にぴったり合った職場を見つけることが大切です。ハッシュタグ転職介護は、医療・福祉業界特化の専門アドバイザーが、一人の担当者として一貫してサポートいたします。
給与・労働環境・人間関係など、あなたが重視するポイントをしっかりとヒアリングし、精度の高いマッチング率を誇る職場をご提案します。あなたの理想に合った転職先を一緒に探しましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
試験内容や科目

介護福祉士国家試験は年1回試験(第1次試験(筆記試験)、第2次試験(実技試験))※一定の要件を満たすと実技試験は免除され、「筆記試験は例年1月下旬、実技試験は例年3月上旬に実施」とされていましたが、現在は筆記試験のみとなっています。
出題形式は5肢択一のマークシート式で、全125問が出題されます。合格基準は「総得点の6割に難易度補正した点数以上、かつ、試験科目群すべてにおいて得点することとなっているのです。試験科目は以下のように分かれています。
- 人間と社会(人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーション、社会の理解)
- 介護(介護の基本、コミュニケーション技術、生活支援技術、介護過程)
- こころとからだのしくみ(発達と老化の理解、認知症の理解、障害の理解、こころとからだのしくみ)
- 医療的ケア(医療的ケア)
- 総合問題
これらの科目は介護福祉士として必要な幅広い知識領域をカバーしており、理論的な基礎から実践的な技術まで総合的な理解が求められます。
人間と社会、こころとからだのしくみ、医療的ケア、介護、総合問題の各領域から幅広く出題されます。
合格率
第36回試験結果(2023年度実施) 受験者数 74,595人、合格者数 61,747人(合格率82.8%)という高い水準で推移しています。第37回試験の結果についても受験者数75,387人 合格者数58,992人 合格率78.3%であり、国家資格としては多くの方が合格できる試験であることを示しています。
また、同試験において、経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者の合格者は498名(37.9%)でした。という結果も公表されており、外国人介護人材の確保にも重要な役割を果たしています。
高い合格率の背景には、受験資格として一定の実務経験や研修修了が求められているため、基礎的な知識と技術を有する方が受験していることがあります。つまり、受験者の多くがすでに介護現場での実践経験を積んでおり、ある程度の基盤があった状態で試験に臨んでいるのです。
さらに、介護福祉士養成施設や実務者研修などの教育課程を通じて、体系的な学習を行った方々が受験していることも高い合格率の要因となっています。
ただし、合格率が高いからといって油断は禁物です。全科目での得点が必要である条件があるため、得意分野だけでなく苦手分野もバランスよく学習することが重要です。
特に問題数が少ない科目でも、しっかりと得点できるよう準備することが必要です。
介護福祉士の実技試験は廃止される?

介護福祉士国家試験の実技試験は廃止されました。
従来は年1回試験(第1次試験(筆記試験)、第2次試験(実技試験))であり、一定の要件を満たすと実技試験は免除されていましたが、現在は筆記試験のみで介護福祉士資格を取得できるようになっています。
実技試験廃止の背景には、実技試験には複数の免除条件が設けられており、実務経験ルートや養成施設卒業者、福祉系高校卒業者の多くが免除対象となっていたことがあります。
その結果、実際に実技試験を受験する方が大幅に減少し、試験実施の実質的な意義が薄れていたのです。
また、実技試験の免除条件が複雑で、受験者にとってわかりにくい制度となっていたことも廃止の背景にあります。免除期間の管理や、受験回数による制限など、受験者が理解しなければならない条件が多岐にわたっていました。
実技試験の廃止により、これらの複雑な条件を気にすることなく、シンプルに筆記試験対策に専念できるようになりました。この変更により、受験者は実技試験の準備に時間を割く必要がなくなり、その分を筆記試験の学習に充てることができます。
特に働きながら資格取得を目指す方にとって、限られた学習時間を効率的に活用できるようになったことは大きなメリットでしょう。
実技試験廃止により学習時間が効率化できるように、転職活動もスピーディーに進めてみませんか?ハッシュタグ転職介護は、医療・福祉業界に特化した一気通貫型のサポーで迅速なマッチングを実現します。
専門知識を持つアドバイザーが、限られた時間のなかであなたに適切な職場探しをお手伝いし、働きながらでも転職活動を進められます。
さらに、私たちは求職者一人ひとりにとことん寄り添っている人材紹介会社です。あなたの希望や不安に真摯に対応しながら、理想の職場を見つけるサポートをいたします。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
実技試験の免除条件

実技試験はすでに廃止されていますが、過去の免除条件を理解することで、現在の試験制度がいかに受験者にとって有利になったかを把握できます。また、現在の受験資格の背景にある考え方も理解できるでしょう。
介護過程や介護過程IIIの履修修了
実務経験ルートで受験する方の場合、実務者研修の修了により実技試験が免除されていました。実務者研修では介護過程の理論と実践を体系的に学習するため、受講者はすでに十分な実技能力を身につけているとみなされていたのです。
実務者研修のカリキュラムには実技演習が含まれており、介護技術の基本から応用まで幅広く学習することができます。また、介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修(第1号研修または第2号研修)を修了した方も実技試験免除の対象でした。
これらの研修には実際の介護技術や医療的ケアの実技演習が含まれているため、別途実技試験を課す必要がないと判断されていました。特に喀痰吸引等研修は、医療的ケアなどの高度な技術を扱うため、この研修を修了していることで実技能力の担保ができていると考えられていたのです。
福祉系高校で介護過程IIIなどの所定科目を履修し卒業した場合も、実技試験は免除されていました。高校での系統的な学習のなかで、十分な実技演習を行っているため、追加の実技試験は不要とされていました。
福祉系高校卒業

2009年度以降に、福祉系高校に入学して、必要な科目を履修して卒業した方は、在学中に介護に関する専門的な教育を受けているため、実技試験が免除されていました。
福祉系高校では、理論学習と並行して実習や実技演習が充実しており、卒業時には一定レベルの介護技術を身につけていることが前提でした。
2008年度以前に、福祉系高校に入学して、必要な科目を履修して卒業した方も同様に、卒業見込みの段階でも免除対象でした。ただし、万が一卒業できなかった場合は、資格取得そのものができなくなる条件がありました。
福祉系高校卒業者の免除には期間制限があり、介護技術講習修了後一定期間である条件が設けられていました。この期間を過ぎると実技試験の受験が必要となるため、卒業後早期に受験することが推奨されていたのです。
養成施設での経験
介護福祉士養成施設(2年以上)を2017年4月以降に卒業(修了)した方や介護福祉士養成施設(1年以上)を2017年4月以降に卒業(修了)した方は、修了した課程に関わらず実技試験が免除されていました。
養成施設では、介護に関する理論と実技の両方を体系的かつ段階的に学習するカリキュラムが組まれています。
実習も含めた総合的な教育により、卒業時には介護福祉士として必要な実技能力を十分に身につけていると判断されていました。そのため、別途実技試験を課す必要がないとされていたのです。
養成施設卒業者の場合、免除期間は介護技術講習修了後、続く一定回数の受験までである条件がありました。この回を超えた受験では実技試験が必要となるため、複数回受験する場合の負担が大きな問題となっていました。
実務での経験

実務経験ルートの場合、単に介護業務に従事しただけでは実技試験免除の対象とはなりませんでした。3年以上(従業期間3年以上(1,095日以上)、従事日数540日以上)介護等の業務に従事した方で、実務者研修を修了した方である条件があり、実務者研修等の指定研修修了が必須条件でした。
これは、現場での実践経験と体系的な研修の両方があって初めて、十分な実技能力があると認められる考え方に基づいています。
従業期間3年以上(1,095日以上)、従事日数540日以上である具体的な基準が設けられていました。これにより、継続的かつ十分な実務経験を積んでいることが確認されていました。
現場での多様な経験を通じて、さまざまな利用者の状態や状況に応じた介護技術を身につけていることが前提となっていたのです。
この実務経験と研修を組み合わせた免除条件の考え方は、現在の受験資格にも引き継がれており、理論と実践の両方をバランス良く学習することの重要性を示しています。
介護福祉士には単なる技術的なスキルだけでなく、利用者の尊厳を重視した質の高いケアを提供する能力が求められるため、実務経験と理論学習の両立が不可欠とされているのです。
介護福祉士国家試験の当日の流れ

実技試験が廃止されたことで、試験当日のスケジュールはとてもシンプルになりました。筆記試験のみの実施となるため、1日ですべての試験が完了し、受験者の負担も大幅に軽減されています。
午前の部
試験当日は、開始前には試験会場に到着することを心がけましょう。受付では受験票と身分証明書の確認が行われ、指定された座席に着席します。
この時点で携帯電話の電源を切り、試験に不要な持ち物は指定された場所に保管しましょう。試験開始前には監督者から注意事項の説明があり、マークシートの記入方法も確認されます。
午前の筆記試験では、人間の尊厳と2問、人間関係のコミュニケーション4問、社会の理解 12問、こころとからだのしくみ 12問、発達と老化の理解 18問、認知症の理解 10問、障害の理解 10問、医療的ケア5問の問題が出題されます。
これらの分野は介護の基盤となる知識が問われるため、基本的な理論をしっかりと理解しておく必要があります。
試験中は集中して取り組み、見直し時間を確保できるよう時間配分に注意しましょう。
特に問題数が少ない科目でも、全科目での得点が必要なため、慎重に解答することが重要です。焦らず丁寧に解答していくことが合格への鍵となります。
試験当日に万全の準備で臨めるように、転職活動でも専門家のサポートを受けてみませんか?ハッシュタグ転職介護では、医療・福祉業界に特化したアドバイザーが、選考対策から入社後のフォローまで継続的にサポートしています。
面接の通過率向上につながる徹底的なサポートを提供し、あなたの転職を成功に導きます。
まずはお気軽にご相談ください。新しい職場での不安も解消し、安心感を持って仕事に取り組める環境を整えるお手伝いをいたします。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
午後の部
午前の部が終了すると、昼休憩があります。この時間は昼食を取るだけでなく、午後の試験に向けた準備にも活用できます。
ただし、試験会場によっては昼食の購入が困難な場合があるため、事前に持参するのがおすすめです。また、午後の試験に備えて適度に休息を取り、集中力を回復させることも大切です。
午後の筆記試験では、介護の基本 10問、コミュニケーション技術6問、生活支援技術 26問、介護過程8問、総合問題 12問の問題が出題されます。
介護領域は実務経験がある方にとって馴染み深い分野であり、日々の業務経験を活かして解答できる問題が多く含まれているのです。
総合問題は複数の領域にまたがる事例問題が中心となり、総合的な判断力と実践的な思考力が問われます。
利用者の状況を読み取り、適切な介護方法や対応を選択する能力が試されるため、現場での経験と理論的な知識を結びつけて考えることが重要です。
午後の試験でも落ち着いて問題に取り組むようにしましょう。
介護福祉士国家試験の対策方法

実技試験が廃止されたことで、学習時間をすべて筆記試験対策に集中できるようになりました。
効率的な学習方法を身につけることで、働きながらでも十分に合格を目指すことができます。
学習時間の確保
介護福祉士国家試験の合格に向けて、継続的な学習時間の確保が重要です。
働きながら学習する場合は、毎日継続することが何より重要であり、短時間でも構わないので学習習慣を身につけることから始めましょう。
効果的な時間確保の方法として、通勤時間を活用した学習があります。これにより移動時間を利用して学習を進めることができるのです。
また、職場での休憩時間を活用することで、積み重ねれば大きな学習時間となります。
休日にはまとまった時間を確保し、集中学習を行うことで、平日の学習内容を整理し定着させることができます。
学習計画を立てる際は、試験日から逆算して全体のスケジュールを把握し、科目ごとの学習期間を設定することが大切です。週単位での学習目標を設定し、定期的に進捗を確認して計画を調整していくことで、無理のない学習を継続できます。
集中できる時間帯を作ることも、効率的な学習には欠かせません。
過去問を利用

過去問学習は介護福祉士国家試験対策の重要な学習方法です。過去問を解くことで出題傾向を把握し、頻出分野や問題形式を理解することができます。
また、実際の試験時間と同じ条件で解くことで、時間配分の練習にもなり、本番での時間管理能力を向上させることができます。さらに、自分の弱点を発見し、重点的に学習すべき分野を特定することも可能です。
効果的な過去問活用法として、まず過去問を通して解いて現在の実力を把握することから始めましょう。
その後、科目別に問題を解いて各分野の理解度を確認し、苦手分野を特定します。次の段階では、時間を測って本番形式での練習を行い、最終的には間違えた問題を繰り返し学習して知識の定着を図るのです。
過去問は社会福祉振興・試験センターの公式サイトで試験問題として入手することができます。
- 第37回(2024年度)介護福祉士国家試験 試験問題
- 第36回(2023年度)介護福祉士国家試験 筆記試験問題
- 第35回(2022年度)介護福祉士国家試験 筆記試験問題
以上が公開されており、実際の試験を想定した学習を進めることが可能です。過去問を活用する際は、単に問題を解くだけでなく、解説をしっかりと読み込み、なぜその答えが正解なのかという根拠を理解することが重要です。
これにより、類似問題への応用力も身につけることができ、本番での得点力向上につながります。
過去問で出題傾向を把握するように、転職活動でも業界の専門知識が重要です。ハッシュタグ転職介護は、医療・福祉業界に特化した人材紹介会社として、業界ごとの課題や求職者のニーズを熟知し、あなたに適切な職場を見つけるお手伝いをします。
私たちは求職者一人ひとりの希望にとことん寄り添い、あなたが抱える悩みや不安をしっかりと聞きながら、理想の職場環境を一緒に探す人材紹介会社です。
大手の人材紹介会社では拾いきれないような細かな希望にもお応えし、ミスマッチのない転職を実現するために、業界特有の情報を駆使して精度の高いマッチングを行います。
また、転職活動だけでなく、入社後のフォローにも注力し、あなたが新しい職場にスムーズに馴染み、安心感を持って働き続けられるようサポートします。
理想の職場を見つけたいと考えている方は、まずは無料相談で、あなたの希望をお聞かせください。あなたにとってのベストなキャリアを実現するため、全力でサポートいたします。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
模擬試験の活用
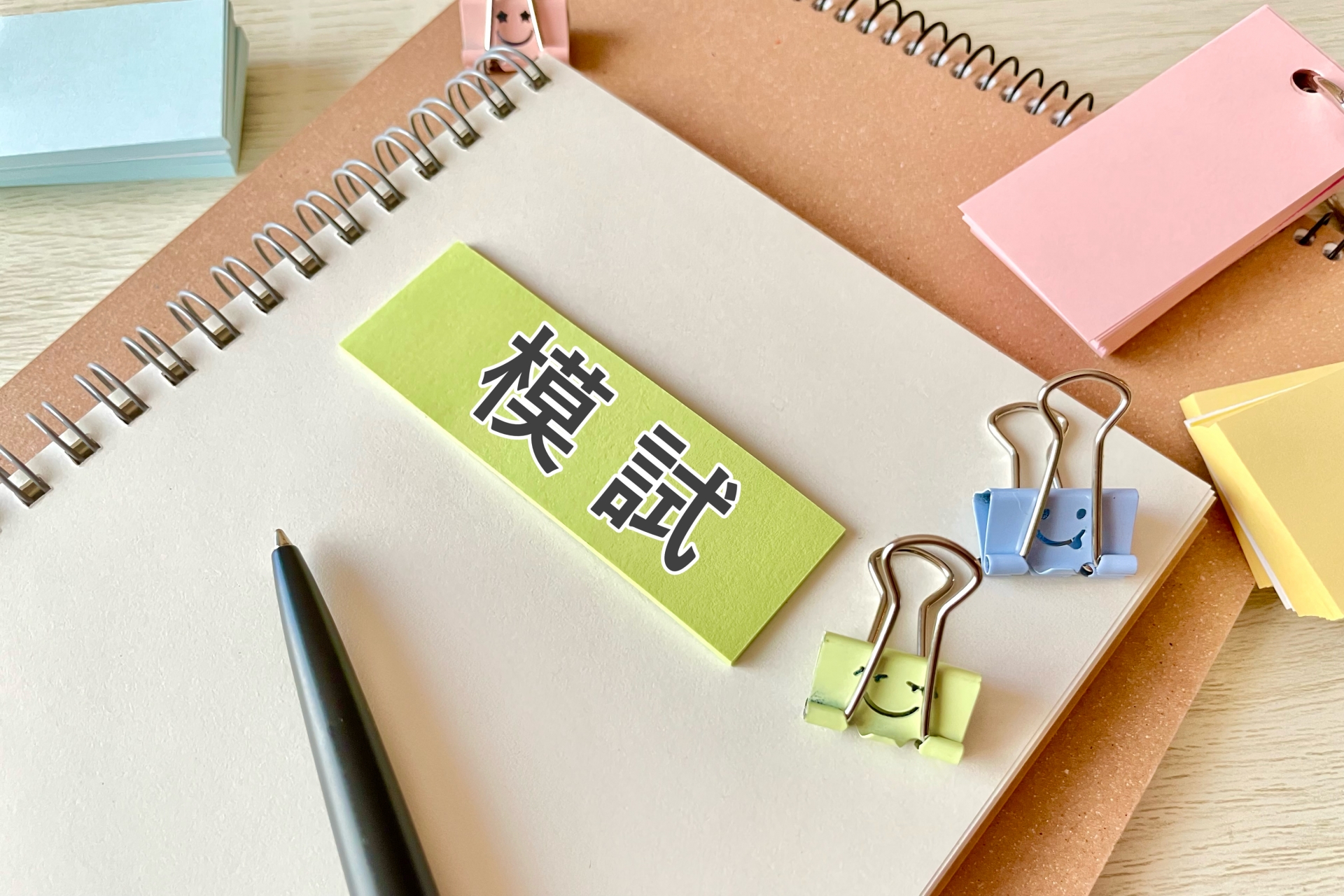
模擬試験を受験することで、本番の緊張感に慣れることができ、実際の試験での緊張を軽減することができます。
また、自分の実力を客観的に把握することが可能です。模擬試験では時間配分の練習も重要な目的であり、本番での効率的な解答につながります。
模擬試験には複数の形式があります。それぞれに特徴があり、自分の学習状況や都合に合わせて選択することができるのです。
模擬試験の結果は必ず分析し、正答率の低い分野を重点的に復習することが大切です。時間配分に問題がある場合は見直しを行い、ケアレスミスの傾向があれば対策を立てる必要があります。
模擬試験の結果を踏まえて学習計画を調整し、弱点を克服していくことが合格への近道となります。
業務での復習
日々の介護業務は、試験学習にとってとても貴重な実践の場となります。
業務で遭遇するさまざまな事例を試験の視点で分析することで、理論と実践を結びつけた深い理解が得られます。利用者との関わりのなかで、人間関係やコミュニケーション技術も学ぶことができ、医療的ケアの実践を通じて関連知識を定着させることも可能です。
業務中の学習では、常に根拠を意識した介護実践を心がけることが重要です。なぜその方法を選ぶのか、なぜその対応が適切なのかを考えながら業務を行うことで、試験で問われる判断力を養うことができます。
他職種との連携場面では専門用語を確認し、利用者の状態変化と疾患や症状の関連性の理解を深めることも学習につながります。
職場の同僚と一緒に学習することも効果的な方法です。勉強会を開催して疑問点を相互に解決したり、学習の進捗を共有して励まし合ったりすることで、モチベーションを維持しながら学習を継続できます。
現場での経験を共有し合うことで、より深い理解と記憶の定着を図ることができるでしょう。
介護福祉士国家試験の実技試験免除期間

実技試験はすでに廃止されていますが、過去の免除期間を理解することで、現在の制度がいかに受験者にとって有利になったかを把握できます。また、制度変更により受験の機会がどのように拡大されたかも理解できるでしょう。
福祉系高校なら講習修了後2年
過去の制度では、福祉系高校卒業者は介護技術講習修了後一定期間に限り実技試験が免除されていました。この期間制限は、卒業後早期に受験することを前提としており、期間を過ぎると実技試験の受験が必要でした。
特に卒業後に他の進路を選択したり、すぐに受験しなかった方にとっては、後に受験する際の負担となっていました。
この期間は多くの方にとって短く、卒業後の進路や就職活動、さらには介護現場での経験を積むことを考えると、必ずしも十分な期間とはいえませんでした。
そのため、卒業と同時に受験準備を進める必要があり、他の選択肢を検討する余裕が少ないという問題もありました。
実技試験廃止により、福祉系高校卒業者はこのような期間制限に縛られることなく、自分のタイミングで受験することができるようになりました。
卒業後に現場経験を積んでから受験したり、ほかの学習や経験を通じて準備を整えてから挑戦したりすることが可能となり、受験の機会が大幅に拡大されています。
養成施設や実務経験なら3回目までの受験
実務経験ルートや養成施設卒業者の場合、介護技術講習修了後、続く一定回数の受験まで実技試験が免除されていました。
この制度は一定の猶予期間を設けているものの、この回数を超えた受験では実技試験が必要となるため、複数回受験する場合の負担がとても大きな問題でした。
この制限は、一見すると十分な機会があるように思えますが、実際には受験者にとって大きなプレッシャーとなっていました。
特に働きながら受験する方の場合、仕事と学習の両立が困難で十分な準備ができずに不合格となることもあり、回数制限があることで焦りを感じながら受験せざるを得ない状況がありました。
また、長期間にわたって受験を続ける方にとって、実技試験の準備は大きな負担でした。筆記試験の学習に加えて実技試験の対策も必要となり、限られた学習時間のなかで両方の準備をすることは現実的に困難な場合が多くあったのです。
さらに、実技試験は筆記試験は例年1月下旬、実技試験は例年3月上旬に実施とされており、別日程で実施されることもあり、複数回の試験会場への足を運ぶ必要もありました。
実技試験廃止により、これらの回数制限や期間制限がすべて撤廃され、受験者は自分のペースで学習を進めて受験できるようになりました。再受験の際も筆記試験のみとなったため、継続的な学習により合格を目指すことが可能となり、長期的な学習計画を立てやすくなっています。
実技試験廃止で再受験の負担が軽減されたように、転職活動でも不安を取り除きませんか?ハッシュタグ転職介護は、求職者を人生のキャリアパートナーとして徹底サポートいたします。
医療・福祉業界に特化した専門知識を持ち、業界特有の課題を理解しているからこそ、あなたの希望にぴったり合った職場を見つけることができます。
転職活動に不安を感じている方、ぜひ一度、ハッシュタグ転職介護の無料相談を利用して、あなたの理想の職場を見つけるお手伝いをさせてください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
実技試験なしで集中して試験に臨むなら

実技試験の廃止により、受験者は筆記試験対策に専念できるようになりました。この変更を最大限に活用することで、より効率的でしっかりとした合格への道筋を描くことができます。
実技試験対策に必要だった時間をすべて筆記試験の学習に充てることができるようになったため、全125問すべての分野でより深い理解を得ることが可能です。
特に苦手分野の克服に十分な時間を確保でき、試験科目群すべてにおいて得点することである合格条件をクリアしやすくなっています。
また、総合問題12問のような複合的な思考力を問う問題への対策時間も十分に確保できるため、より高い得点を目指すことができます。
学習計画の立案も大幅に簡素化されました。筆記試験のみの対策となるため、過去問分析や模擬試験の結果をもとにした効率的な学習スケジュールを組むことができます。
実技試験の日程を考慮する必要がなくなったため、自分の生活リズムに合わせた無理のない学習計画を立てることが可能です。精神的な負担も大幅に軽減されています。
実技試験への不安がなくなることで、筆記試験の学習に集中でき、一度にすべての試験が終了するため長期間の緊張状態を維持する必要もありません。再受験の場合も実技試験を心配する必要がないため、純粋に筆記試験の学習に取り組むことができます。
具体的な学習戦略としては、まず基礎知識のしっかりとした定着を考えることが重要です。
全125問で幅広い知識が問われるため、暗記だけでなく理解に基づいた学習を心がける必要があります。日々の業務経験を理論と結びつけて理解することで記憶に定着しやすくなり、根拠を常に意識した学習が効果的です。
医療的ケア5問のように問題数が少ない科目も軽視せず、試験科目群すべてにおいて得点することである条件を常に意識して学習を進めることが大切です。模擬試験の重要性も高まっており、本番と同じ時間配分での練習を重ねることで得点力をしっかりと身につけましょう。
試験と同様に、その後の転職活動も大切です。ハッシュタグ転職介護では、求職者が重視するポイントを深くヒアリングし、あなたにぴったりな職場環境を提案しています。
求職者一人ひとりに向き合い、密にコミュニケーションを取り、人生のキャリアパートナーとしてサポートしています。
些細なことでもぜひ、ご相談ください。あなたに合った職場環境を一緒に探しましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼






