ケアマネ試験とは

ケアマネージャーを目指す方がまず通過しなければならないのが、ケアマネ試験です。この試験は介護保険制度の要となるケアマネージャーとしての基礎知識と専門性を測る重要な関門となっています。ここでは試験の概要や目的について詳しく解説していきます。
介護支援専門員実務研修受講試験の概要
ケアマネ試験の正式名称は介護支援専門員実務研修受講試験です。この試験は、介護保険制度における要となるケアマネージャーになるための第一段階として位置づけられており、毎年多くの介護従事者が挑戦しています。
試験は年1回、全国で同日に実施され、例年10月の第2日曜日に開催されることが多くなっています。試験時間は120分で、マークシート方式による選択問題が出題される形式です。出題範囲は介護支援分野と保健医療福祉サービス分野の2つに大きく分かれており、合計60問が出題されます。
合格基準は各分野で正答率70%程度とされていますが、問題の難易度によって調整される場合があります。合格後は実務研修の受講が必要となり、この研修を修了して初めて介護支援専門員として登録できる仕組みです。
実務研修は約87時間のカリキュラムで構成されており、ケアマネジメントの実践的な知識と技術を学びます。
試験の目的と役割

ケアマネ試験の目的は、介護支援専門員として必要な基礎知識と専門性の確認です。ケアマネージャーは、要介護者やその家族のニーズを把握し、適切なケアプランを作成する重要な役割を担っています。
利用者一人ひとりの状況に応じて、医療・介護・福祉サービスを組み合わせた適切なケアプランを作成し、サービス提供事業者との調整も行います。
そのため、試験では介護保険制度の理解、ケアマネジメントの知識、保健医療福祉サービスに関する専門知識が幅広く問われるのです。社会の高齢化が進むなかで、質の高いケアマネージャーの育成は急務となっており、この試験がその基準を担保する役割を果たしています。
試験を通じて確認される知識には、介護保険法の詳細・要介護認定の仕組み・各種サービスの特徴と適用条件・ケアプランの作成方法・関係機関との連携方法などが含まれます。
これらの知識は、実際の業務において利用者やその家族に対して適切なサポートを提供するために不可欠なものばかりです。
ケアマネ試験の受験資格

ケアマネ試験を受験するためには、特定の資格と実務経験が必要です。この受験資格は介護保険法に基づいて定められており、介護や医療の専門職としての一定の経験を積んだ方のみが受験できる仕組みになっています。
ここでは受験資格の詳細について解説します。
必要な実務経験年数
ケアマネ試験を受験するためには、対象となる業務での実務経験が5年以上かつ900日以上必要です。この実務経験は、試験実施年度の3月31日までに満たしている必要があります。
つまり、例年10月に実施される試験であれば、その年の3月31日時点で実務経験要件を満たしていることが条件となります。
実務経験の計算において重要なのは、連続した期間である必要はないという点です。複数の職場での経験を合算することができ、また異なる資格での経験も通算可能となっています。
ただし、同一期間内での重複計算はできないため注意が必要です。例えば、看護師と介護福祉士の両方の資格を持っている場合でも、同じ期間の勤務を両方の資格での実務経験として重複してカウントすることはNGです。
実務経験の対象となる業務は、保健・医療・福祉に関する相談援助業務や介護などの業務、介護などに関する講師や相談員などの業務が含まれます。パートタイムや短時間勤務でも、実際に従事した日数が900日以上あれば実務経験として認められます。
対象となる資格職種

受験資格の対象となる資格職種は、法定資格に基づいて定められています。これらの資格は、保健・医療・福祉の各分野における専門職として位置づけられており、ケアマネジメントに必要な基礎的な知識と技術を有していると認められるものです。
主な対象資格には以下のようなものがあります。医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・言語聴覚士・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・栄養士(管理栄養士含む)・精神保健福祉士などが含まれます。
これらの資格を持ち、該当する業務に従事した期間が実務経験として認められるのです。資格によって対象となる業務の範囲が若干異なる場合があるため、自分の保有資格でどのような業務が実務経験として認められるかを事前に確認することが大切です。
また、生活相談員・支援相談員・相談支援専門員など、特定の相談援助業務に従事している場合も一定の条件を満たせば受験資格の対象となります。
受験資格を満たすかの確認方法
受験資格を満たしているかどうかの確認は、まず保有資格と実務経験年数の整理から始めましょう。実務経験の計算は複雑な場合があるため、勤務先の人事担当者や各都道府県の試験実施機関に相談することをおすすめします。
特に複数の資格を持っている場合や、転職経験がある場合は、どの期間がどの資格での実務経験にあたるかを明確にすることが重要です。実務経験証明書の作成時に必要となる情報でもあるため、事前に整理しておくとスムーズに手続きを進められます。
確認の際は、勤務していた事業所の種類・従事していた職種・勤務期間・勤務日数を正確に把握しておく必要があります。特に介護保険法の改正により、実務経験の対象となる業務や施設の範囲が変更されている場合があるため、新しい情報を確認することが大切です。
不明な点がある場合は、各都道府県の試験実施機関や関係団体に問い合わせることで、個別の状況に応じたアドバイスを受けることができます。
ハッシュタグ介護転職は、介護業界で働くあなたのための転職支援サービスです。今の職場でもっとスキルアップしたい、給料を上げたいと思っていませんか。
経験豊富な専任アドバイザーが、あなたの希望にぴったりの職場を一緒に探します。ケアマネジャーへのステップアップを目指している方には、資格取得のサポート情報も用意しており、どのような相談にも親身に対応可能です。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
ケアマネ試験の申込方法

ケアマネ試験の申し込みは、都道府県ごとに実施されており、手続き方法も地域によって多少異なります。しかし、基本的な流れはどの地域でも共通しているため、ここでは一般的な申込方法について詳しく解説します。
早めの準備と正確な手続きが合格への第一歩です。
申込書の入手方法
ケアマネ試験の申込書は、各都道府県の指定試験実施機関から入手できます。多くの場合、都道府県庁または市区町村の介護保険担当窓口・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所・介護保険施設・医療機関などで配布されています。配布場所は地域によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
また、各都道府県のホームページからダウンロードできる場合も多く、PDF形式で提供されているケースが一般的です。申込書とあわせて受験要項も必ず入手し、詳細な手続き方法や注意事項を確認しておきましょう。
受験要項には、申込期間・必要書類・受験手数料・試験日程・会場など重要な情報が記載されているため、しっかりと確認することが必要です。
一部の地域では、説明会の開催や郵送での配布も行われています。説明会では申込手続きの詳細説明に加え、試験の傾向や対策についての情報も提供される場合があるため、積極的に参加することをおすすめします。
申込書の配布期間は限られているため、配布開始日を事前に確認し、早めの入手が肝心です。
申し込みの流れ
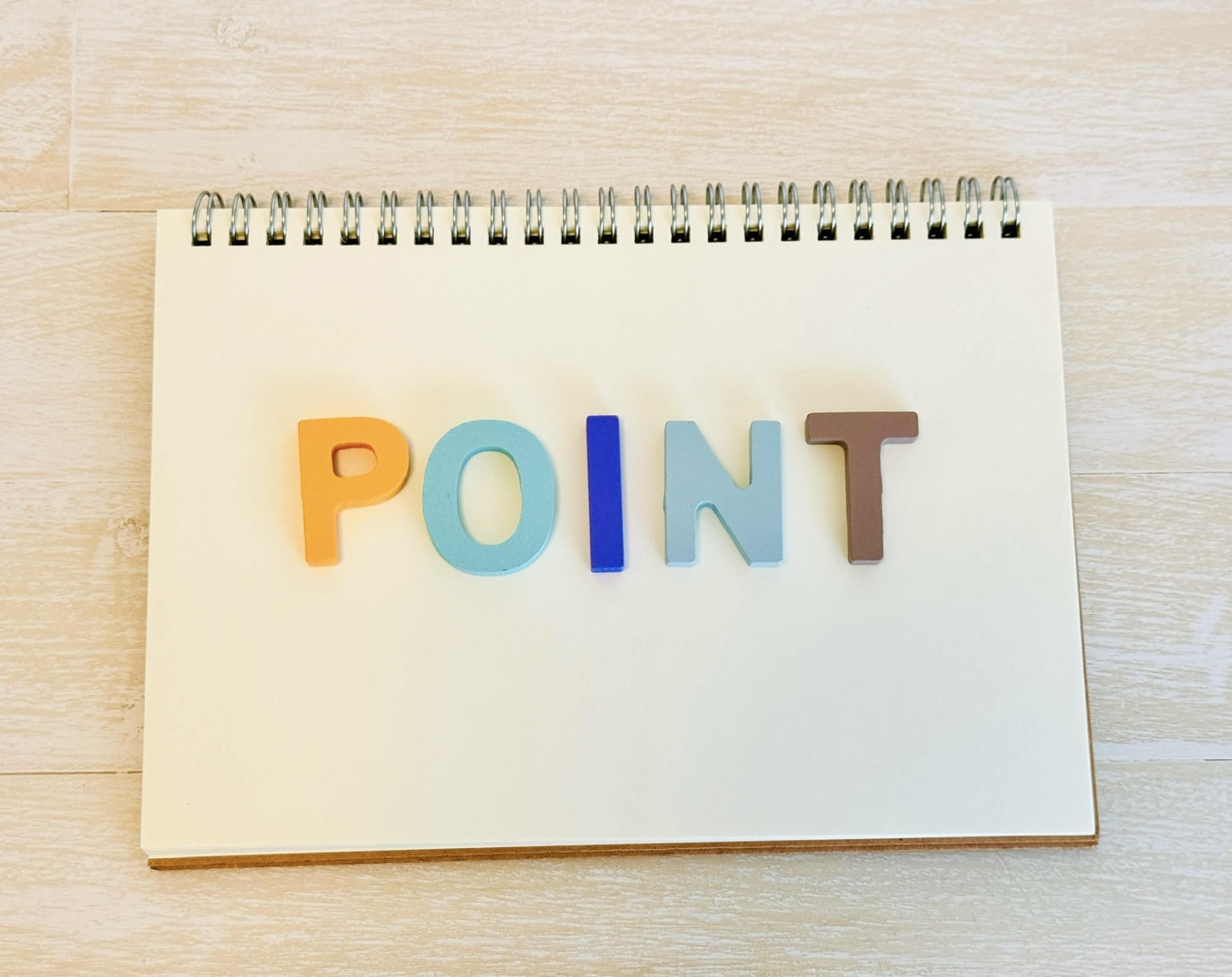
申し込み手続きの基本的な流れは以下のとおりです。
まず、申込書と受験要項を入手し、受験要項を熟読して手続きの詳細を把握します。次に、申込書に必要事項を黒のボールペンで丁寧に記入してください。
必要書類の準備では、実務経験証明書や資格証明書など、第三者が作成する書類については早めに依頼することが重要です。特に実務経験証明書は、勤務先の都合により作成に時間を要する場合があります。
受験手数料の納付については、指定された方法での対応が必要です。現金書留・銀行振込・コンビニ払いなど、地域によって対応している支払い方法が異なるため、確認することが重要です。領収書や振込明細書は必ず保管し、申込書と一緒に提出しましょう。
書類一式がそろったら、指定された方法で提出します。郵送の場合は簡易書留や特定記録郵便など、配達記録の残る方法での送付が一般的です。窓口持参の場合は、受付時間内に直接提出しましょう。
提出後は受付確認の連絡があるまで、控えや領収書などを大切に保管しましょう。
オンライン申込が可能な地域
ケアマネ試験のオンライン申込が可能な地域はないのが現状です。申し込みを行うためには窓口へ書類を持参して直接提出する、または簡易書留などによる郵送での申し込みが一般的です。
さまざまな申請や手続きがオンライン化している昨今、将来的にはケアマネ試験のオンライン申込が実現する可能性はあります。しかし、現時点では窓口持参か郵送に限られています。
ハッシュタグ介護転職では、あなたのこんな職場で働きたいという思いをしっかりヒアリングし、理想の職場を見つけるお手伝いをします。
給与・勤務地・人間関係など、あなたが重視するポイントにあわせた求人情報を紹介するサービスです。将来的にケアマネジャーになりたい方には、そのためのキャリアプランも一緒に考えます。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
ケアマネ試験に必要な書類
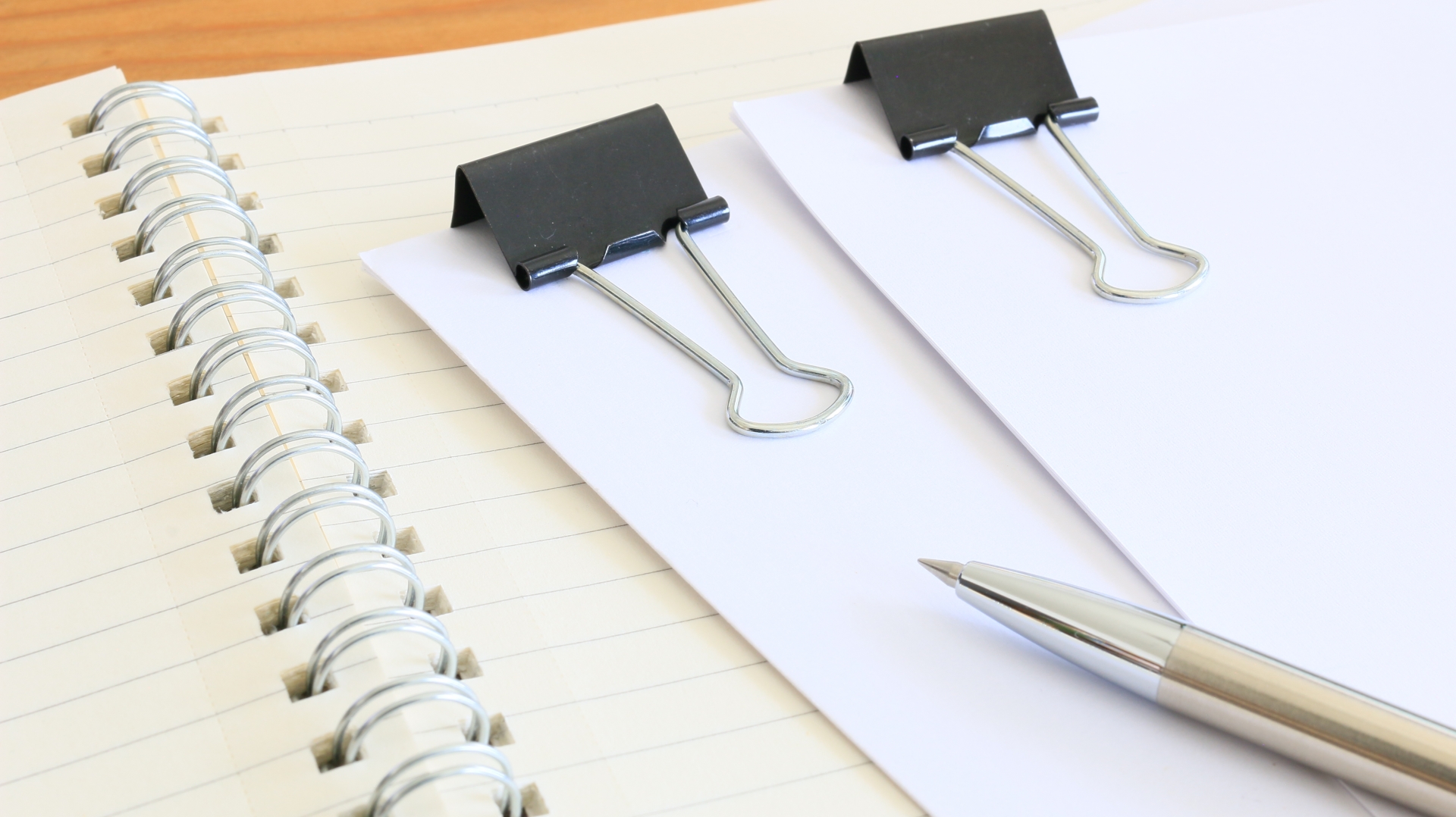
ケアマネ試験の申し込みには複数の書類が必要となり、それぞれに重要な役割があります。書類の準備には時間がかかる場合があるため、早めに着手することが大切です。ここでは各書類の詳細と注意点について解説します。
申込書
申込書は試験申し込みの基本となる書類で、個人情報や受験地の希望、実務経験の詳細などを記入します。記入にあたっては、黒のボールペンを使用し、修正液や修正テープの使用は避けるのが一般的です。
間違いがあった場合は、二重線で訂正し、訂正印を押すか、新しい申込書に記入し直すことをおすすめします。
氏名や生年月日、住所などの基本情報に加え、保有資格の詳細や実務経験の内容を正確に記載する必要があります。
特に実務経験の記載は、後述する実務経験証明書との整合性を保つことが重要です。勤務先名・勤務期間・職種・業務内容などは、実務経験証明書と一字一句同じになるよう注意深く記入しましょう。
受験地の希望については、原則として住所地または勤務地での受験となります。地域によっては複数の試験会場が設置される場合もあるため、通いやすい会場を選択するのがよいでしょう。
写真の貼付も必要で、申し込み前6ヶ月以内に撮影された正面上半身の写真(縦4cm×横3cm)を使用します。不明な点があれば、提出前に実施機関に確認することをおすすめします。
実務経験証明書または実務経験見込証明書

実務経験証明書は、受験資格要件である実務経験を証明する重要な書類です。
勤務先の事業所に作成を依頼し、事業所の代表者または人事担当者による証明が必要となります。この書類の作成には時間を要する場合があるため、申し込みを決めたら早めに依頼することが大切です。
証明書には、勤務期間・職種・業務内容・勤務日数・勤務形態(常勤・非常勤の別)などが詳細に記載されます。実務経験の計算は複雑で、実際に従事した業務が受験資格の対象となるかどうかの判断も必要です。
事業所の担当者と十分に相談しながら、正確な内容で作成してもらいましょう。
複数の事業所での勤務経験がある場合は、それぞれの事業所から証明書を取得する必要があります。退職した事業所については、連絡を取るのが困難な場合もあるため、できるだけ早めに依頼することが重要です。
試験実施年度の3月31日までに実務経験要件を満たす予定の場合は、実務経験見込証明書での申し込みが可能です。この場合、合格後に実務経験を満たしたことをあらためて証明する書類の提出が必要となります。
国家資格の免許証または登録証の写し
受験資格の基となる国家資格の証明として、免許証または登録証のコピーを提出します。
資格によって証明書の名称や発行機関が異なるため、該当する資格の正式な証明書を確認することが重要です。例えば、看護師の場合は看護師免許証、社会福祉士の場合は社会福祉士登録証というように資格ごとに異なる名称の証明書があります。
コピーは鮮明で判読できるものを用意し、A4サイズで提出するのが一般的です。コピー機の設定によっては文字が不鮮明になる場合があるため、提出前に内容がはっきりと読めることを確認しましょう。両面に記載がある場合は、両面をコピーして提出します。
複数の資格を保有している場合でも、受験に使用する資格の証明書のみの提出で十分です。ただし、実務経験の通算を行う場合は、関連するすべての資格の証明書が必要となる場合があります。
免許証の有効期限がある資格については、申し込み時点で有効であることを確認することが重要です。更新手続きが必要な資格の場合、期限切れの免許証では受験資格を証明できず、不合格となる可能性があります。
ケアマネ試験の申込期間と注意点

ケアマネ試験の申し込みには厳格な期限があり、一日でも遅れると受験できません。また、書類の準備や記入には予想以上に時間がかかる場合があるため、計画的な準備が必要です。
ここでは申込期間と重要な注意点について詳しく解説します。
申込受付期間(例年の目安)
ケアマネ試験の申込受付期間は、例年6月上旬から7月上旬頃に設定されています。具体的には、6月の第1週から7月の第1週頃までの約4週間程度が一般的です。
ただし、具体的な期間は都道府県によって若干異なる場合があるため、必ず該当地域の実施機関で正確な日程を確認してください。
申込受付の開始日は平日に設定されることが多く、終了日も平日の午後5時頃までとなっているのが通常です。土日祝日は受付を行わない地域がほとんどなので、締め切り日が金曜日以外の場合は特に注意が必要です。
受付期間は約1ヶ月程度と限られており、期間を過ぎると一切受け付けてもらえません。
特に、書類の準備に時間を要する場合があるため、早めの準備開始を心がけましょう。実務経験証明書の作成依頼は、勤務先の都合もあるため申込期間の開始前から準備を始めることがおすすめです。
申込期間の詳細な日程は、例年4月頃に各都道府県のホームページで発表されます。受験を予定している方は、定期的にホームページをチェックし、常に新しい情報を入手するようにしましょう。
提出締切の厳守

申込書類の提出締切は厳格で、1日でも遅れると受験資格を失うのが一般的です。これは法的な手続きであるため、例外は一切認められません。
郵送の場合は当日消印有効の場合がありますが、配達遅延のリスクを考慮し、締切日の数日前には投函することをおすすめします。
郵便事故や配達遅延による不達のリスクを避けるため、簡易書留や特定記録郵便などの配達記録が残る方法で送付することが重要です。また、ポストへの投函ではなく、郵便局の窓口で手続きを行い、しっかりと消印を押してもらうことをおすすめします。
窓口提出の場合も、受付時間内での提出が必要です。多くの場合、平日の午前9時から午後5時までとなっていますが、昼休み時間は受付を行わない場合もあります。交通渋滞や電車の遅延なども想定し、時間に余裕を持って向かいましょう。
特に締切日当日は、多くの申込者が集中する可能性があるため注意が必要です。窓口が混雑し、予想以上に時間がかかる場合もあるため、できる限り早めの提出を心がけましょう。
書類不備があった場合の対応
書類に不備があった場合の対応は、都道府県によって異なりますが、基本的には受理されないケースが多くなっています。軽微な不備については、実施機関から連絡があり修正の機会が与えられる場合もありますが、重大な不備や締切後の対応は困難です。
よくある不備としては、記入漏れ・押印忘れ・証明書の期限切れ・実務経験の計算間違い・写真の貼付忘れ・受験手数料の納付漏れなどがあります。これらを防ぐため、提出前のチェックリストを作成し、複数人での確認を行うことをおすすめします。
特に実務経験の計算は複雑で、勤務形態や職種によって計算方法が異なる場合があるため注意が必要です。不安がある場合は、提出前に実施機関に相談し、計算方法が正しいかどうかを確認してもらうことも可能です。
書類の訂正が必要な場合は、修正液や修正テープの使用は避け、二重線での訂正と訂正印の押印または新しい用紙への記入し直しを行いましょう。訂正箇所が複数ある場合は、見た目の印象も考慮し、新しい申込書に記入し直すことをおすすめします。
ハッシュタグ介護転職は、あなたのパートナーとして、転職の成功をサポートするサービスです。履歴書の書き方から面接対策まで、スムーズに転職活動ができるよう丁寧にアドバイスします。
ケアマネへのステップアップに興味がある方には、専門的な情報を提供し、あなたのキャリアを応援します。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
申込後から試験当日までの流れ
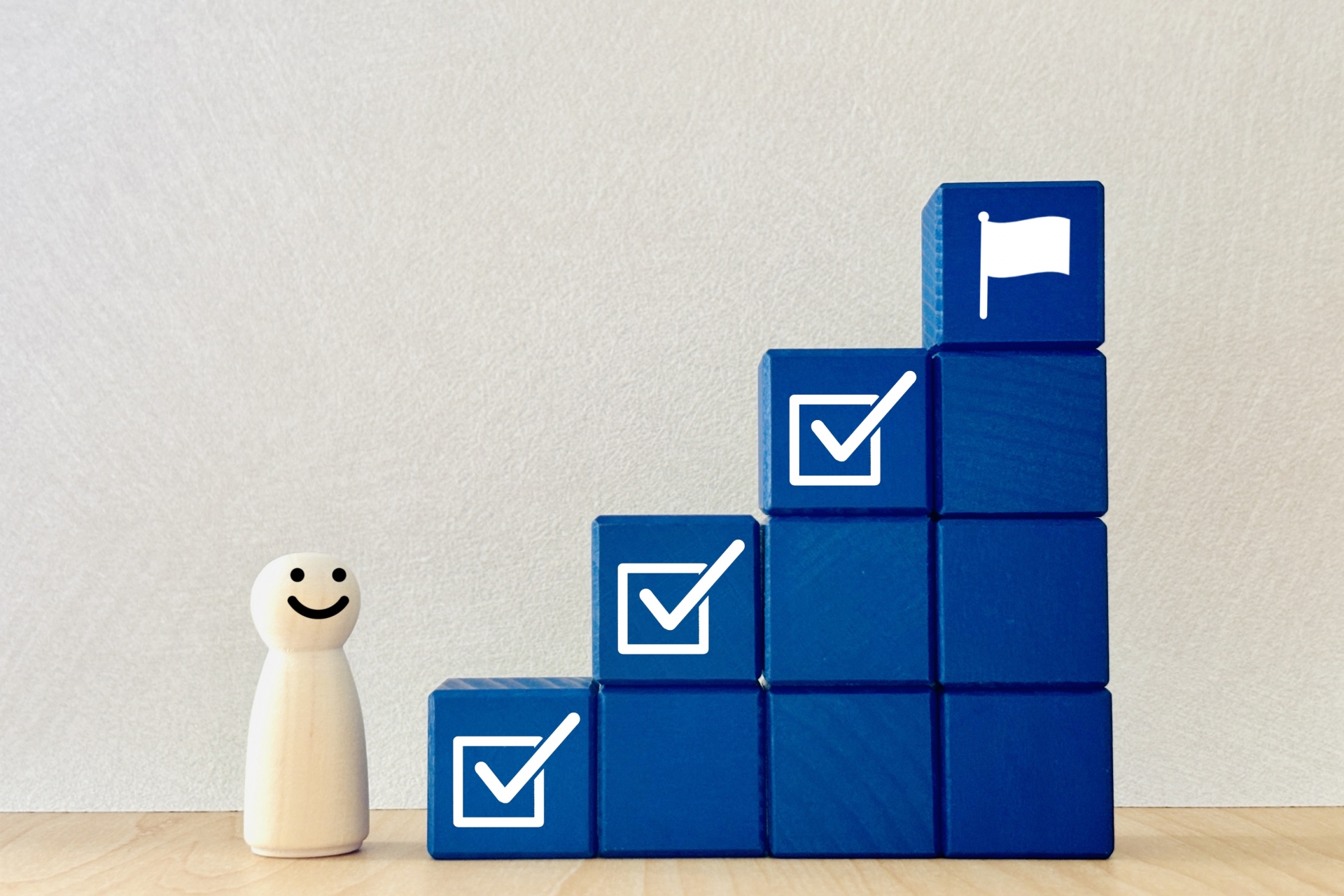
申込手続きが完了した後は、受験票の到着を待ちながら試験当日に向けた準備を進める期間です。この期間の過ごし方も合格への重要な要素となるため、計画的に準備を進めることが大切です。
受験票の発送・確認方法
申込手続きが完了し、書類に不備がないことが確認されると、試験実施の約1ヶ月前に受験票が発送されます。
具体的には、例年9月上旬頃に発送されることが多く、受験票には受験番号・氏名・試験会場・試験開始時間・持参物・注意事項などの重要な情報が記載されています。
受験票が届いたら、記載内容に間違いがないか必ず確認することが必要です。氏名の漢字・生年月日・受験地・受験番号などに誤りがあった場合は、速やかに実施機関に連絡しましょう。訂正には時間がかかる場合があるため、受験票到着後すぐに確認することが重要です。
試験会場については、申込時に希望した地域内で指定されますが、具体的な会場は受験票で初めて知ることになります。会場までのアクセス方法や所要時間を事前に確認し、可能であれば下見を行っておくことがおすすめです。
受験票は試験当日の入場に必要不可欠な書類のため、紛失しないよう大切に保管してください。万が一紛失した場合は、試験実施機関に連絡し、再発行の手続きを行う必要があります。
試験当日の持ち物
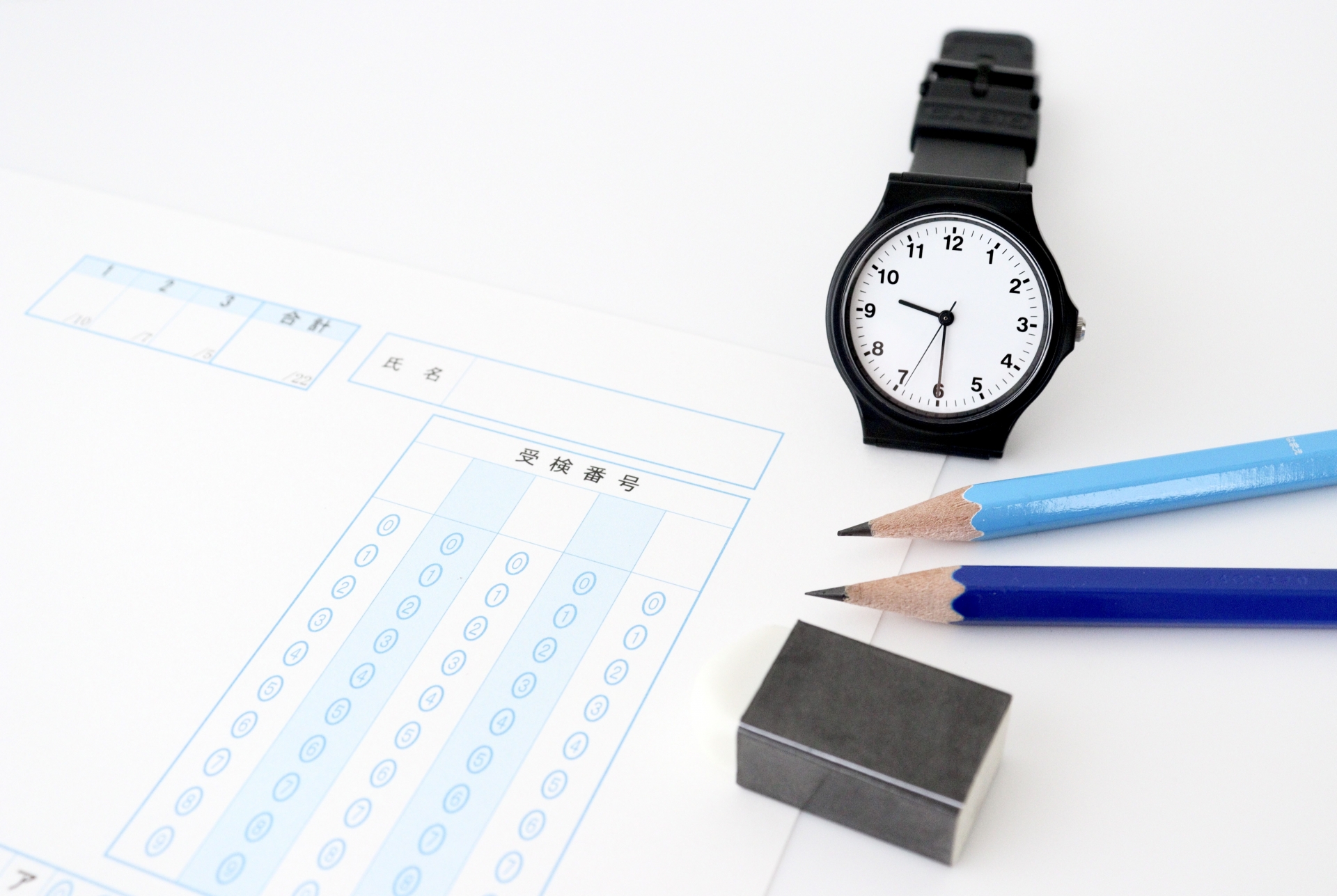
試験当日は受験票と本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証など)の持参が必須です。
本人確認書類は、顔写真付きのものが原則となりますが、健康保険証などの場合は追加の証明書類が必要となる場合があります。事前に受験要項で確認しておくことが重要です。
筆記用具については、書きやすく消しやすいHBまたはBの鉛筆(シャープペンシル可)と消しゴムを用意しましょう。マークシートの読み取りに支障をきたす可能性があるため、濃すぎる鉛筆やボールペンの使用は避けてください。
また、腕時計(計算機能付きや通信機能付きは不可)の持参も重要です。試験会場によっては時計が設置されていない場合があるため、時間管理のために必ず持参しましょう。上着なども会場の温度調整用として持参することをおすすめします。
携帯電話は電源を切るか機内モードに設定し、指定された場所に保管することが必要です。アラーム機能も含めてすべての機能を停止してください。不正防止のため、持ち込み禁止物品については受験要項で詳しく確認し、該当するものは持参しないよう注意しましょう。
試験会場での注意点
試験会場では、指定された座席に着席し、試験監督者の指示に従いましょう。
座席は受験番号順に配置されていることが多く、受験票に記載された座席番号を確認して着席します。試験開始前には受験票と本人確認書類の照合が行われるため、机の上に準備しておくとスムーズです。
試験中は私語や不正行為は厳禁で、発覚した場合は即座に失格となります。ほかの受験者の迷惑となる行為も慎みましょう。体調不良やトイレなどで退席が必要な場合は、必ず試験監督者に申し出る事が必要です。無断での退席は不正行為とみなされる場合があります。
マークシートへの記入は指定された方法で行い、記入漏れや誤記入がないよう注意深く確認することが大切です。問題番号とマークシートの番号が対応しているか、マークがしっかりと塗りつぶされているかなど、定期的に確認しながら進めましょう。
試験終了時刻まで退席は原則として認められていません。早めに問題を解き終わった場合でも、見直しの時間として有効活用し、終了まで集中力を維持することが重要です。
ハッシュタグ介護転職は、経験者のキャリアアップに特化した転職支援サービスです。あなたの経験や資格を正当に評価してくれる職場を、全国の求人情報から見つけ出します。
もちろん、将来的にケアマネジャーとして活躍したい方のための情報も豊富です。新しい職場で、あなたの可能性を広げてみませんか?
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
ケアマネージャー試験の不安を相談しよう

ケアマネ試験への不安や疑問は、一人で抱え込まず積極的に相談することが重要です。受験に関する情報収集や精神的なサポートをえることで、よりよい準備と心構えで試験に臨むことができます。
各都道府県の試験実施機関では、受験に関する問い合わせに対応しており、手続きや受験資格について詳しく教えてもらえます。
特に複雑な実務経験の計算や書類の準備については、専門的なアドバイスを受けることができるため、不明な点があれば遠慮なく相談するのがよいでしょう。
また、職場の先輩ケアマネージャーや同僚からは、実際の受験体験に基づいた具体的なアドバイスをえることができます。試験対策の方法・勉強時間の確保の仕方・当日の心構えなど、実体験に基づく情報はとても貴重です。
同じ職場で働く仲間からのサポートは、精神的な支えにもなるでしょう。
介護関連の研修会や勉強会も貴重な情報源となります。これらの場では、同じ目標を持つ仲間と出会うことができ、情報交換や励まし合いを通じて、モチベーションの維持にも役立ちます。
また、講師として参加する現役のケアマネージャーから直接話を聞くことも可能です。
受験までの期間中に感じる不安や プレッシャーは、多くの受験者が経験するものです。一人で悩まず、家族や友人、職場の同僚などに気持ちを打ち明けることで精神的な負担を軽減できます。
適度な息抜きやリラックスの方法についても、周囲の方からアドバイスをもらうのがよいでしょう。
適切な準備と心構えがあれば、ケアマネ試験は決して乗り越えられない壁ではありません。この記事を参考に、しっかりとした申込手続きを行い、合格に向けて着実に歩を進めていきましょう。
受験資格の確認から書類の準備や申込手続き、そして試験当日まで、一つひとつのステップを丁寧にクリアしていくことが成功への鍵です。
ケアマネージャーとしての第一歩を踏み出すため、十分な準備と前向きな気持ちで試験に臨んでください。皆さんの努力が実り、介護支援専門員として活躍される日が来ることを心より応援しています。
ハッシュタグ介護転職は、介護業界の転職にまつわるあらゆる悩みを解決します。どのような求人があるか知りたい、自分に合う職場がわからないといったご相談も大歓迎です。
プロの視点から、あなたの強みを活かせる職場を提案します。ケアマネへのステップアップを目指す方には、資格取得のための具体的なステップや、新しい試験情報もお伝えします。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼






