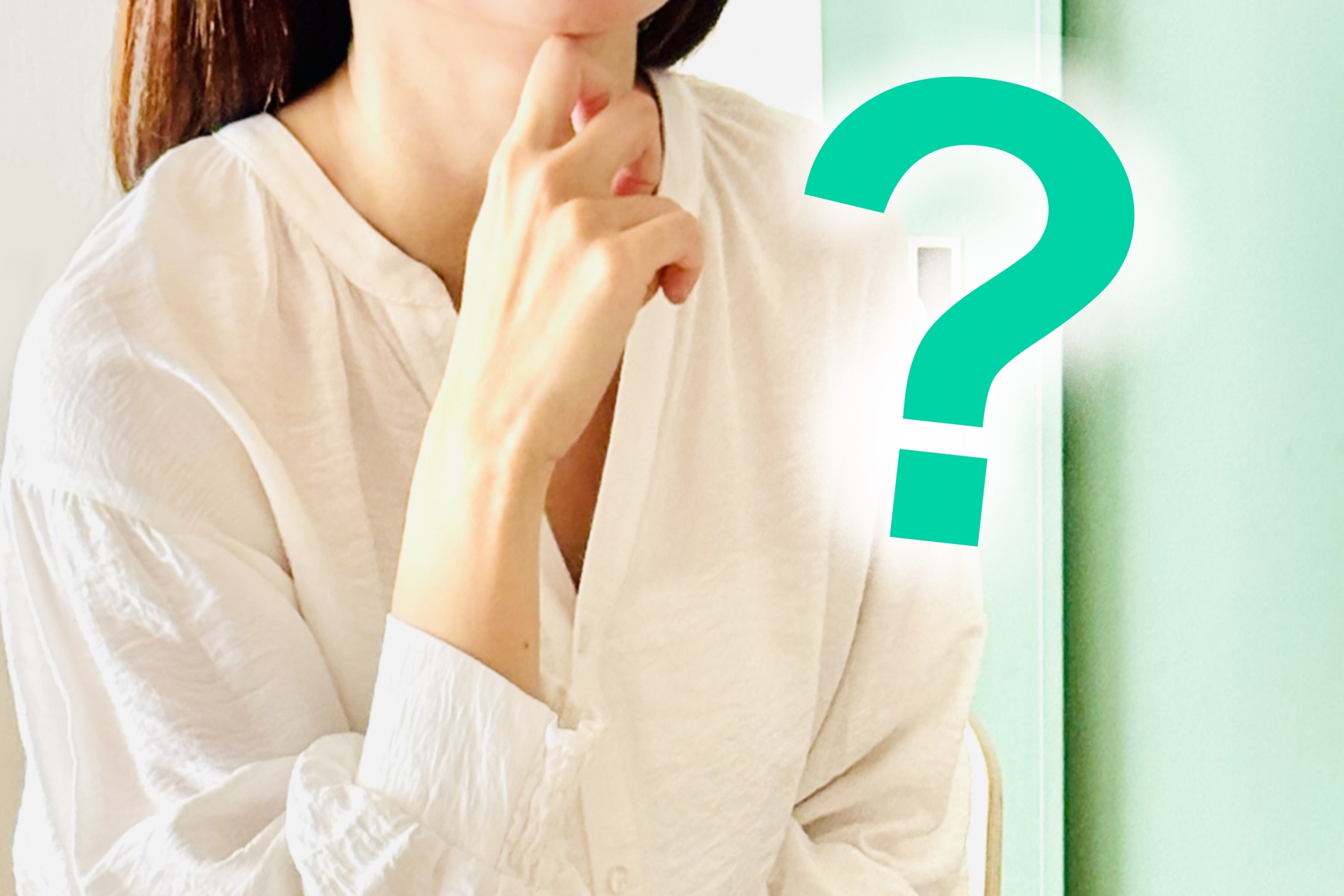介護職がメンタルをやられる原因とは?

介護職に従事する方の多くが、精神的な疲労やストレスを感じています。その背景には、共通するいくつかの要因が存在します。
「なぜこんなにも疲れるのだろう」「自分だけがつらいのではないか」と、不安や孤独を感じている方も少なくないでしょう。メンタルが落ち込む主な原因はなんなのでしょうか。
職場の人間関係によるストレス
介護の仕事では、スタッフ同士のチームワークが欠かせません。しかし、多くの人と関わりながら働くからこそ、人間関係にストレスを感じることも少なくありません。
24時間体制の施設ではシフト勤務が基本のため、常に同じメンバーと働けるわけではなく、コミュニケーションの取りづらさを感じる場面もあります。また、世代や経験の違いから、ケアの方針や価値観にズレが生じ、摩擦が起きてしまうこともあります。
業務の忙しさから、些細な誤解が大きなトラブルにつながったり、情報共有が不十分なまま「自分だけが負担を抱えている」と感じてしまうケースもあるでしょう。
特に、新人スタッフは「質問しづらい雰囲気」に戸惑ったり、指導の厳しさに不安を抱くことがあります。さらに、管理職は現場スタッフと上層部の板挟みになり、悩みを抱えやすい立場にあるといえます。
人手不足による過重な業務量

介護業界全体が抱える大きな問題として、慢性的な人手不足があります。
これにより一人あたりの業務負担が増え、過重労働につながっています。
多くの施設は人員配置基準ギリギリの状態で運営されているため、急な欠勤があると、残りのスタッフでカバーせざるを得ない状況です。
ケアのほかにも記録や報告書などの事務作業も増加傾向にあり、時間内に業務を終わらせようとすると、休憩時間を削ることになりやすいです。
このような状況が続くといつも時間に追われたり、仕事が終わらないというプレッシャーを感じたり、疲労が蓄積された状態で翌日の勤務に臨むことになります。
利用者・家族対応での精神的負担
介護職は利用者様の生活を直接支える職種であり、深い人間関係が生まれます。
そこには喜びもありますが、同時に大きな負担も伴います。認知症の方の予測できない言動や、時には暴言・暴力に対応することもあります。
終末期ケアなど、命と向き合う場面での精神的負担も小さくありません。
利用者様の体調悪化や死別を経験することによる喪失感を抱えることもあるでしょう。
家族からの高い期待や要望に応えきれないジレンマも存在します。特に、もっとよいケアをしたいという思いが強い方ほど、理想と現実のギャップに苦しみやすくなります。
給与面での不満と評価への不安
介護職は責任の重さに比べて、給与水準が低いと感じている方もいるでしょう。
業務の重責や専門性の高さに見合った報酬が得られていないと感じたり、キャリアパスが不明確で将来の見通しが立てにくかったりすることも不安の一つです。
また、介護の仕事は成果が目に見えにくく、努力が適切に評価されないこともあります。
これだけ頑張っているのにという思いが募ると、モチベーションの低下につながりやすくなります。
メンタルがやられやすい介護職の特徴

介護職のなかでも、特にメンタル不調に陥りやすい傾向のある方がいます。
自分自身の性格や傾向を知ることで、早めの対策を取ることが可能です。
責任感が強すぎる方
責任感が強すぎる方は、自分がやらなければと必要以上に仕事を抱え込んでしまいがちです。
利用者様の些細な変化も見逃すまいと常に神経を張り詰め、ミスを恐れるあまり、完璧を求めすぎてしまいます。
ほかのスタッフに仕事を任せられず、休暇中も仕事のことが気になって心から休むことができません。
このタイプの方は、自分の限界を超えて頑張りすぎる傾向があります。
完璧を目指すのではなく、ベストを尽くすという考え方に切り替え、チームで働く意識を持つことが大切です。
ネガティブ思考に陥りやすい方

ネガティブ思考の方は、利用者様やご家族からの何気ない一言を深く受け止めてしまったり、上司からのアドバイスを叱責と捉えてしまったりします。
自分はダメな介護職員だと自己否定的になりやすく、小さなミスを何度も思い返して自分を責め続けることもあるでしょう。
対策としては、成功体験や感謝されたことをノートに書き留めるなど、ポジティブな側面に目を向ける習慣をつけることが効果的です。
周囲の評価を気にしすぎる方
周囲の評価を気にしすぎる方は、周りからどう思われているかを常に気にしています。
自分の意見よりも他者の意見を優先しがちで、無理をしてでも期待に応えようとします。
このタイプの方は、人間関係を大切にする反面、自分自身のニーズや限界を無視してしまいがちです。
すべての人に好かれる必要はないということを受け入れ、自分の意見をきちんと伝える練習をすることが大切です。
メンタル不調に陥りやすい介護施設の特徴

メンタルヘルスの問題は個人の資質だけでなく、職場環境に大きく左右されます。
職員のメンタル不調を引き起こしやすい施設の特徴を紹介します。
休みが取りづらい
休みが取りづらい施設では、シフト希望がほとんど反映されなかったり、急な休みを申請すると肩身が狭い思いをさせられたりすることがあります。
有給休暇の取得率が低く、休暇を取る際に申し訳ないと感じさせる文化が存在することも珍しくありません。
このような環境では、休息を十分に取れないまま働き続けることになり、疲労が蓄積されます。
その結果、判断力の低下やミスの増加などにつながり、メンタルヘルスにも悪影響を及ぼします。
残業や業務量が多すぎる
残業や業務量が多すぎる施設では、残業が当たり前という風潮があり、定時で帰りづらい雰囲気が形成されていることがあります。
業務の効率化や改善提案が受け入れられにくい環境も、ストレスの要因となります。
このような環境では、家庭生活や趣味、十分な睡眠時間などが犠牲になりがちです。
その結果、リフレッシュする機会が減り、ストレスが解消されないまま蓄積されていきます。
職場内でパワハラやいじめがある
パワハラやいじめがある職場では、上司や先輩からの厳しい叱責や人格否定的な発言が日常的に行われることがあります。
特定のスタッフが孤立させられたり、無視されたりする現象も見られます。
このような職場では、ミスを報告しづらい雰囲気があり、隠ぺい体質になっていることが問題です。
パワハラやいじめなどが続く職場環境では、自尊心の低下や不安感の増大など、メンタルヘルスへの悪影響が避けられません。
「最近、心が疲れている」「職場に行くのがつらい」と感じる方は、そのまま我慢せず、ぜひ一度ハッシュタグ転職介護にご相談ください。
ハッシュタグ転職介護では、介護・福祉業界に精通した専門アドバイザーが、メンタル面にも配慮された安心して働ける職場を厳選してご紹介しています。
あなたの気持ちに寄り添いながら、より良い働き方を一緒に考えていきます。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
介護職が陥りやすいメンタルの症状と兆候

介護職の方がメンタル不調に陥ると、どのような症状や兆候が現れるのでしょうか。
特に多く見られる症状について解説します。
燃え尽き症候群
燃え尽き症候群(バーンアウト)は、長期間のストレスや過度な期待に応えようとする努力の末に、心身のエネルギーが枯渇してしまう状態です。
特に意欲的で真面目な方ほど陥りやすいといわれています。
燃え尽き症候群になると、仕事への情熱や関心が急激に低下し、何をやっても意味がないという無力感を感じるようになります。
利用者様に対して感情的な反応が鈍くなる(脱人格化)といった変化も現れ、以前は楽しめていた仕事が苦痛に感じられるようになります。
抑うつ・適応障害

抑うつ・適応障害の状態では、気分の落ち込みが続き、何をしても楽しめません。
集中力や決断力が低下し、些細なことでも悩んでしまうようになります。
自己評価が低下し、将来に対して悲観的になり、食欲の変化や睡眠障害といった身体的な変化も現れることがあります。
何をしても楽しくない、自分はダメな人間だと思ってしまうなどの考えが続く場合は、専門家への相談を検討することがおすすめです。
身体的症状(不眠、頭痛、倦怠感など)
メンタル不調による身体的症状としては、寝つきが悪い、または夜中に何度も目覚める不眠症状がよく見られます。
原因不明の頭痛や肩こり、腰痛などの痛みが続くこともあります。
常に疲れを感じる倦怠感や体のだるさも特徴的です。
さらに、食欲不振や消化器症状、動悸や息切れ、めまい、発汗などの自律神経症状も、ストレスによって引き起こされることがあります。
病院で検査しても異常がない、休んでも疲れが取れないという場合は、ストレスが身体症状として現れている可能性があります。
こうした身体的な不調が続いている場合、「自分の頑張りが足りない」と無理をしてしまいがちですが、それは心と体からのSOSかもしれません。
ハッシュタグ転職介護では、心身の健康を第一に考え、メンタル面に配慮された働きやすい職場をご紹介しています。
介護業界に精通した専門アドバイザーがあなたの状況を丁寧にヒアリングし、不調の原因となる環境からの転職を全力でサポートします。
「今の働き方を変えたい」「心も体も健やかに働き続けたい」と感じている方は、ぜひ一度ハッシュタグ転職介護の無料相談をご活用ください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
介護職のメンタルケアに役立つ具体的な方法

介護の仕事は心身ともに負担がかかりやすく、気づかないうちにストレスが蓄積されることがあります。
次の項目では、メンタル不調を感じたときや、日頃からできる予防のためのケア方法をご紹介します。
職場での相談窓口を活用する
信頼できる上司や先輩に、業務上の悩みを相談することで、新たな視点や解決策が見つかることがあります。
施設内に相談窓口やメンタルヘルス担当者がいる場合は積極的に活用しましょう。
外部の介護職専門の相談窓口やホットラインも利用できます。
弱音を吐くのは恥ずかしいと思わず、早めに相談することが問題解決の第一歩です。
専門家からのアドバイスを受けることで、新たな視点や解決策が見つかることもあります。
適度な休息と趣味でリフレッシュする
勤務と勤務の間に十分な休息を取り、睡眠の質を高める工夫をすることが重要です。
自分が本当に楽しめる趣味や活動の時間を定期的に確保することで、ストレス解消になります。
特に、仕事のことは家に持ち帰らないという意識的な切り替えが重要です。勤務時間外は介護のことを考えず、自分の時間を大切にする習慣をつけましょう。
定期的な運動や健康管理を行う

ウォーキングやジョギングなど、無理のない範囲で体を動かすことでストレスホルモンの分泌が抑えられ、幸福感をもたらすホルモンが分泌されます。
バランスの良い食事を心がけ、十分な水分補給も大切です。
定期的な健康診断を受け、自分の身体の状態を把握することで、早期に問題を発見することができます。
十分な睡眠時間を確保し、質の良い睡眠のための環境づくりを行うことも重要です。
職場環境改善を上司に提案する
業務効率化のためのアイデアや改善案を具体的に提案することで、業務負担の軽減につながります。
チーム内のコミュニケーション強化のための定期的なミーティングを提案すると、情報共有が円滑になります。
問題点だけでなく解決策も一緒に提案する、施設や利用者様にとってのメリットも伝えるというポイントを意識すると、採用される可能性が高まります。
職場環境の改善を目指して行動を起こすことは素晴らしい一歩です。しかし、それでも「なかなか改善が見られない」「努力しても状況が変わらない」と感じる場合は、環境そのものを見直すことも必要かもしれません。
ハッシュタグ転職介護では、介護業界に精通した専門アドバイザーが、働きやすさや人間関係に配慮された職場をご紹介しています。
職場環境に悩みを抱えている方は、まずはハッシュタグ転職介護の無料相談をご利用ください。あなたが安心感を持って長く働ける環境を一緒に探していきましょう。
メンタルの負担が少ない介護職場を見つけるためのポイント

現在の職場環境に限界を感じたら、自分に合った新しい職場を探すことも選択肢の一つです。
メンタルの負担が少ない職場を見つけるためのポイントを紹介します。
職場見学や口コミで職場環境をチェック
可能であれば、職場見学や1日体験を申し込み、実際の雰囲気を感じることをおすすめします。
職員同士のコミュニケーションの様子や、利用者様への接し方を観察すると、職場の本質が見えてきます。
現場のスタッフに直接質問することも効果的です。
スタッフの表情が明るいか、利用者様とスタッフの関係性が良好か、質問に対して誠実に答えてくれるかなどは職場環境を判断する上で重要なポイントです。
施設の離職率や評判を調べる

面接時に職員の平均勤続年数や離職率について質問してみると、施設の実情がわかることがあります。
長く働いているスタッフの割合を確認することも、職場の安定性を判断する材料になります。
高い離職率や常に求人を出しているという状況は、職場環境に何らかの問題があるサインかもしれません。
一方、長く働いているスタッフがいる職場は、働きやすさの証といえるでしょう。
自分の働き方に合った施設形態を選ぶ
特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、施設の種類によって業務内容や特性が異なります。
日勤のみの職場か、夜勤を含むシフト制かなど、勤務形態も重要な選択ポイントです。
自分が大切にしたい介護の姿勢と、施設が掲げる理念や方針が一致しているかどうかは、安心して長く働くうえで非常に重要なポイントです。
そのためにも、事前に施設の理念や方針をきちんと確認しておくことが大切です。「自分に合った職場で、やりがいを持って働きたい」と考えている方は、ハッシュタグ転職介護へぜひご相談ください。
経験豊富なキャリアアドバイザーが、離職率が低く働きやすい施設をご希望に沿って丁寧にご紹介いたします。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
メンタルを守って長く働ける介護職を見つけよう

これまで紹介してきたように、介護職のメンタルヘルス問題にはさまざまな要因があります。
しかし、適切な対策と環境選びによって、心の健康を保ちながら長く働き続けることは十分に可能です。
自分一人で悩みを抱え込まず、専門家のサポートを受けることも大切です。
ハッシュタグ転職介護の無料相談では、介護業界に詳しいキャリアアドバイザーが、あなたの状況やご希望に寄り添いながら、適切な職場探しをサポートします。
多数の介護施設との取引実績があるハッシュタグ転職介護では、一般には公開されていない「非公開求人」も含め、幅広い選択肢のなかからご紹介が可能です。
施設の内部情報や職場の雰囲気など、求人票だけではわからない詳細な情報もお伝えします。
介護の仕事は、人の生活と尊厳を支える重要な役割を担っています。だからこそ、支援する側であるあなた自身の心と体の健康も大切にしていただきたいと考えています。
適切な職場環境とセルフケアを大切にしながら、介護のやりがいを長く感じられるキャリアを一緒に築いていきましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼