介護業界未経験の方でも、とことん寄り添った求職者支援で安心して転職活動を行いませんか?
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
地域包括支援センターとは?

地域包括支援センターは、介護に関する総合相談窓口です。病気やケガで急に介護が必要になった・最近物忘れが気になる・一人暮らしで今後が心配など、地域の高齢者やその家族の相談対応を行います。
また地域包括支援センターはすべての市町村に設置されており、専門職(社会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師)が配置されています。
この専門職が中心となり連携をとりながら、地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように支援する総合相談窓口でもあります。
介護だけではなく、福祉・医療・健康などさまざまな側面から支援を行うのが特徴です。
介護保険法第115条の46第1項では”地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び 福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設”となっています。
介護が必要になってからだけではなく、地域の実情に合わせて高齢者の暮らしを支援するのも地域包括支援センターの大きな役割になります。
地域包括支援センターの歴史や設置などについては、次の通りになります。
介護保険法で定められた施設で、2005年から制定されました。
責任主体は市町村。設置主体は、市町村または市町村から委託を受けた法人です。
地域包括支援センターは、第一号被保険者数がおおむね3000〜6000人の区域に設置されます。
全国に5,451か所の地域包括支援センターが設置されています。(令和6年4月末現在)
地域包括支援センターは全国共通の法律で定められた正式名称です。「包括」「包括センター」など略称して呼ぶ場合があります。
地域包括支援センターの名称は地域住民になじみのある名称を使用してもかまわないため、自治体によっては独自の名称(高齢者センターなど)を用いることがあります。
このように地域包括支援センターは、主に地域の高齢者の暮らしを支援する仕事を担っています。
地域包括支援センター以外にも、介護の仕事は本当に多岐にわたります。
一言で介護といっても、施設介護や訪問介護、デイサービスなど選択肢が多く、どの道を選べばよいのか迷ってしまう方も少なくありません。
そんなときは、ハッシュタグ転職介護にご相談ください。
福祉業界に特化した専門知識とネットワークを持つキャリアアドバイザーが在籍しており、求人票だけではわからない職場の雰囲気や働き方まで含めて、あなたに合った選択肢を丁寧にご提案します。
まずは無料相談から、不安や疑問を一緒に整理してみませんか?
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
地域包括支援センターを利用できる方

主に65歳以上の高齢者及び支援する方が対象になります。
本人だけではなく、家族や地域住民も利用できます。また、介護保険制度を利用していない(未申請の方)も利用できます。
地域包括支援センターは、住み慣れた地域・自宅で安心して暮らしていけるように支援する施設です。元気なうちから介護予防に取り組みたい方や、定年退職後に地域に貢献できるような活動を行いたい方なども利用対象となります。
注意点は、利用対象地域の地域包括支援センターなのか確認することです。自治体のホームページなどで、どこの地域包括支援センターに相談すればいいか事前に確認をしましょう。
また、違う市町村で暮らす親や親族の介護相談は、本人が住んでいる地域の地域包括支援センターへ問い合わせる必要があります。利用対象者が住んでいる地域を支援している地域包括支援センターを活用することで、スムーズに支援を開始していくことができます。
地域包括支援センターの主な事業内容

地域包括支援センターでは、次の事業を行っています。
- 総合相談支援業務
- 第一号介護予防支援事業
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
- 権利擁護事業
- 地域ケア会議の実施
それぞれの事業内容について解説します。
総合相談支援事業
地域の高齢者や介護を行っている家族に対して、初期の段階から継続的・専門的に相談支援を行います。
地域のさまざまなサービス等につなげ、高齢者や家族介護者が抱えている悩みなどに対して専門的立場から支援を行っていきます。
また、地域包括支援センターでも介護保険申請が可能です。外出が困難など状況に応じて職員が自宅を訪問し相談支援や介護保険申請の代行などの支援を行います。
総合相談では、近隣の住民から「最近Aさんの言動がおかしい」「外でBさんがよく転んでいるから心配だ」といった相談にも対応しています。
地域の民生委員などからも相談を受け付けており、高齢者が地域で孤立せず必要な支援が受けられるようにしていくのも大きな業務となります。
第一号介護予防支援事業
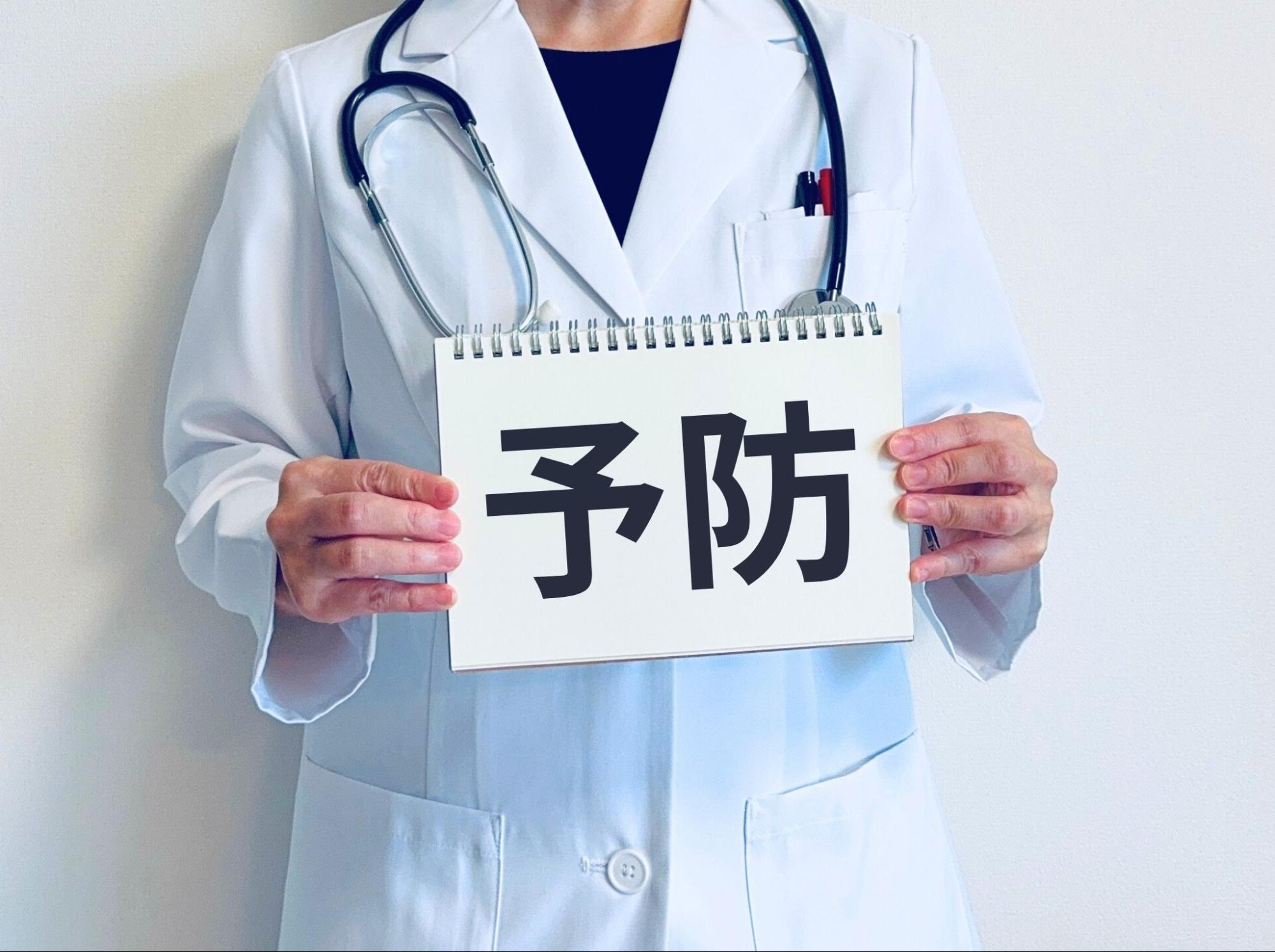
介護予防ケアマネジメントともいう第一号介護予防支援事業とは、要支援1・2の認定を受けた方などが介護予防・日常生活支援を目的とした活動を支援していきます。
本人や家族と相談を繰り返し、選択した介護保険サービスやボランティアらによる支援が受けられるように調整等を行います。
地域で開催されている体操教室やサロンの案内など本人や家族に情報提供を行ったり、介護保険制度を始めとする制度の説明なども必要に応じて対応をします。
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
地域包括支援センターでは、活躍中のケアマネジャーへの支援も行っています。
ケアマネジャーは介護保険制度の専門家であり介護の司令塔のような立場の職種です。しかし、支援が難しいケースなどケアマネジャーの抱えている悩みごとなどの相談窓口でもあります。
また介護予防サービスの検証などを行い、高齢者の自立支援や介護予防に努めていく事業です。
権利擁護事業
例え寝たきりになっても認知症になっても、本人の尊厳ある生活を奪うことはできません。
権利擁護事業では、尊厳ある生活が送れるように支援していきます。具体的には成年後見制度の活用促進や高齢者虐待への対応を行います。
地域の高齢者がその人らしく生活できるよう支援していくために、行政や弁護士・行政書士などの専門職と連携して事業を行っています。
指定介護予防支援
指定介護予防支援とは、要支援1・2の認定を受け介護予防サービス等の適切な利用等ができるようにすることです。
地域包括支援センターだけではなく、居宅支援事業者に一部委託をしたり、市から直接介護予防支援の指定をうけた居宅支援事業者が介護予防を目的に支援を行っていきます。
地域ケア会議の実施

地域ケア会議とは、医療・介護の専門職や自治体職員・民生委員などで構成され高齢者個人の課題解決に向けた手法です。
高齢者個人への支援の充実と同時に、地域の課題を明確にします。高齢者を取り巻く環境は、地域によって違いがあります。
例えば買い物に行けないという高齢者個人の悩みをよく検討してみると、身体の状態がよくない・近所にスーパーなどがない・公共交通機関が充実していない・代わりに買い物に行ってくれる人がいない・経済的に余裕がないなどがあげられます。
介護保険制度では解決できない課題も含まれています。このような課題を明確にし、地域づくりや資源開発の検討を行っていきます。
また市町村への働きかけも行い、介護保険事業計画へ反映させていくなど政策形成につなげる重要な役割を持っています。
地域ケア会議を積み重ね、高齢者個人や家族・介護関係者だけではなく地域レベルで検討・実施することで地域住民が安心して暮らしていけるようにつなげていく大きな意味を持つ会議だといえるでしょう。
住み慣れた地域でその人らしく暮らしていけるよう支援を行うことも、介護の大きな仕事になります。
ハッシュタグ転職介護では、「一気通貫型」の仕組みを採用しています。キャリア相談から企業紹介、選考対策、入社後のフォローまで一人の担当者が対応しスピード感ある転職活動が可能になります。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
地域包括支援センターではどのような職種の方が働いている?

地域包括支援センターでは、原則として社会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師の3職種の職員の配置が決まっています。
また、予防プランナーという職種の方も働いています。地域包括支援センターによっては、配置していない場合や名称の違いなどがあります。
社会福祉士
社会福祉士とは、生活に困難を抱える人々やその家族に対して、相談・助言・指導・関係機関との連携や調整を行い、生活の自立や社会参加を支援する専門職です。高齢者、障害者、児童、生活困窮者など、幅広い対象者に対応できる国家資格として位置づけられています。
資格は社会福祉士国家試験に合格した者に与えられ、取得のためには指定の養成課程を修了することが必要です。そのため、福祉全般に関する知識や相談援助技術を体系的に学んだ専門職であるといえます。
具体的な業務としては、生活保護や介護保険、障害福祉制度などの社会保障制度を活用した支援、福祉サービス利用の調整、就労支援や地域資源の活用、さらには医療・教育・行政との連携などが挙げられます。単に相談に応じるだけでなく、対象者が安心して暮らせる環境を整えるために多方面から支援を行う役割を担っています。
社会福祉士は福祉全般の相談援助における唯一の国家資格であり、地域包括支援センターや病院、福祉施設、行政機関など幅広い現場で必要とされる存在です。
主任ケアマネジャー

主任ケアマネジャーとは、ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格を持ち、一定期間の実務経験を積んだうえで、所定の研修を修了することで取得できる資格です。受験資格としては、通常5年以上かつ900件以上のケアプラン作成など、実務に基づいた経験が求められます。そのため、現場での豊富な実務知識と実践力を備えた人材といえます。
主任ケアマネジャーと一般のケアマネジャーとの大きな違いは、自らケアマネジメントを行うだけでなく、事業所内や地域における他のケアマネジャーに対して指導・助言を行う役割を担う点です。後輩ケアマネジャーの相談役や育成指導者として、チーム全体のケアマネジメントの質を高めることが期待されています。
さらに、地域包括支援センターなどでは、多職種との連携を推進し、複雑なケースへの対応や地域包括ケアシステムの中核を担う存在としても活躍します。そのため、主任ケアマネジャーはケアマネジャーの上位資格として位置づけられ、介護現場におけるリーダー的役割を果たす重要な資格といえます。
予防プランナー
予防プランナー(または介護予防プランナー)という資格はありません。厳密にいえば、地域包括支援センターに予防プランナーという職種を配置しなくても良いです。
ただし、人員の確保など難しい場合に社会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師資格以外でも第一号介護予防支援事業を行う職員の役職名になります。
予防プランナーとして働くには、ケアマネジャー・看護師・社会福祉士など条件を満たせていれば可能です。
保健師

保健師とは、医療・福祉・介護の分野で活動し、高齢者だけでなく乳幼児から成人まで、地域に暮らすすべての住民を対象に保健サービスを提供する国家資格です。病気の予防や健康づくり、生活習慣改善の支援、育児・介護に関する相談対応など、幅広い領域に携わり、人々が安心して暮らせる環境を整える役割を担っています。
具体的には、乳幼児健診や予防接種の実施、妊産婦や新生児への訪問指導、学校での健康教育、高齢者の生活習慣病予防や介護予防の推進など、多様な場面で活動しています。行政機関に所属することが多く、地域の健康課題を把握し、住民に対して必要なサービスを提供する役割を持っています。
また、地域包括支援センターにおいては、医療的な視点から高齢者やその家族を支援することが特徴です。介護支援専門員や社会福祉士など他職種と連携しながら、健康管理や疾病予防に関するアドバイスを行い、介護予防ケアマネジメントにも深く関わります。保健師は、地域で暮らす人々の健康寿命を延ばし、生活の質を向上させるために欠かせない存在です。
地域包括支援センターでの職種別の仕事内容

地域包括支援センターでは、資格に応じて主な仕事内容を担当し多職種と連携を行っています。
すべての職種に共通していえることは、地域の高齢者が健康で安心して暮らせるように支援を行っていくことです。
社会福祉士の仕事内容
社会福祉士は、主に総合相談と権利擁護に関して担当しています。福祉の専門職である社会福祉士は、高齢者やその家族からの相談に応じ、必要な各機関と調整を行います。
主任ケアマネジャーの仕事内容
主任ケアマネジャーは、主に地域のケアマネジャーの支援や地域ケア会議開催などを担当しています。地域の高齢者を支えるケアマネジャーの支援を行うのが大きな特徴といえるでしょう。
予防プランナーの仕事内容
第一号介護予防支援事業を行います。主に、要支援1・2認定の高齢者に対して介護予防ケアプランを作成します。この介護予防ケアプランに基づき、必要な支援を行っていきます。
保健師や看護師の仕事内容

保健師や看護師は、主に医療の視点から高齢者の支援を担当しています。介護予防のために講座を開催したり、医療機関や保健所など関係機関と連携・調整を行います。
介護の仕事をするには「資格を取得してからじゃないと難しいのかな…?」と感じる方も多いのではないでしょうか。実は、資格がなくても介護の仕事は始められます。
ハッシュタグ転職介護では、未経験や無資格の方にも安心感を持ってスタートできる職場をご紹介しています。さらに、キャリア形成を見据えたサポート体制を整えているため、働きながら資格取得を目指したい方や将来的にスキルアップを考えている方もご利用ください。
給与や労働環境だけでなく、「自分らしい働き方」まで含めてとことん寄り添ってくれるのが、ハッシュタグ転職介護の強みです。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
地域包括支援センターで働くやりがいや大変な点

地域包括支援センターでの業務は、他の介護の仕事とは異なる業務を行うことが多いです。そのため、他の介護の仕事とは少し違ったやりがいや大変な点があります。
他の職種との連携だけではなく、地域住民や自治体との調整も必要不可欠な業務も多くコミュニケーション能力が必須です。
また、地域包括支援センターは苦情窓口でもあります。
さまざまな相談・苦情に対応するため介護の分野だけではなく、他の関係法律や自治体による支援制度など幅広い知識も必要になってきます。
地域の歴史や特性も知っておく必要があるでしょう。
やりがい
地域包括支援センターで働くやりがいは、たくさんあります。職種によって、多少の違いはあるかもしれません。
共通して言えるのは、地域に住む高齢者が自分らしく暮らし続けていけるように支援ができた時に「ありがとう」と感謝される瞬間だと思います。
地域包括支援センターに相談してよかったと安心してもらえるように、それぞれの職種が連携して適切な支援を行っていくプロセスもやりがいの一つといえるでしょう。
介護予防を目的とした体操教室や地域住民が集えるサロンの開催なども、やりがいの一つです。
元気なうちから地域住民と関わることで、早期に地域の課題や支援が必要な方の発見につながります。
元気になってきた・楽しみが増えたといった声を聞いた時も、地域包括支援センターで働いて良かったと思う瞬間でしょう。
大変な点
地域包括支援センターでは、地域で起こる高齢者のトラブルに対応することも多いです。ゴミ問題や認知症を抱える方への周囲の対応など、課題は複雑なことがあります。
高齢者個人だけではなく、家族や近隣住民・病院・自治体・民間企業などさまざまな関係者と連携が必要です。理解と協力を得ることが、大変な点でもあります。
地域包括支援センターで仕事をしたいなら

「介護業界未経験だと難しそう…」「資格を持ってないし…」と不安に感じた方もいらっしゃるかと思います。
地域包括支援センターで働くためには、資格取得と実務経験が必要になってきます。
実務経験がないと取得できない資格もあるため、まずは資格なしでも働ける介護の仕事を行うのがおすすめです。養成学校に通うのも方法の一つです。ですが、資格によっては遠回りになってしまうこともあります。
また、地域包括支援センターと併設されている介護施設などで働くのもおすすめです。より具体的に仕事内容を見ることができます。
仕事と勉強の両立は、簡単ではありません。職場によっては、資格取得のためのサポートが充実しているところもあります。
地域包括支援センターで仕事をしたい!と思ってくださるあなたを、現場では求めています。
より具体的に「自分に合った介護の職場はどんなところなのか」を明確にするには、専門アドバイザーに相談するのがおすすめです。
求人票だけでは見えにくい、職場の雰囲気や研修制度、資格取得のためのサポート体制なども気になるポイントではないでしょうか。
ハッシュタグ転職介護では、こうした不安や疑問を解消できるよう、入社後のフォロー体制を強化しています。単なる転職サポートではなく「人生のキャリアパートナー」として伴走し、あなたの想いや希望を丁寧にすり合わせることで、長く安心して働ける職場探しを実現しています。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼






