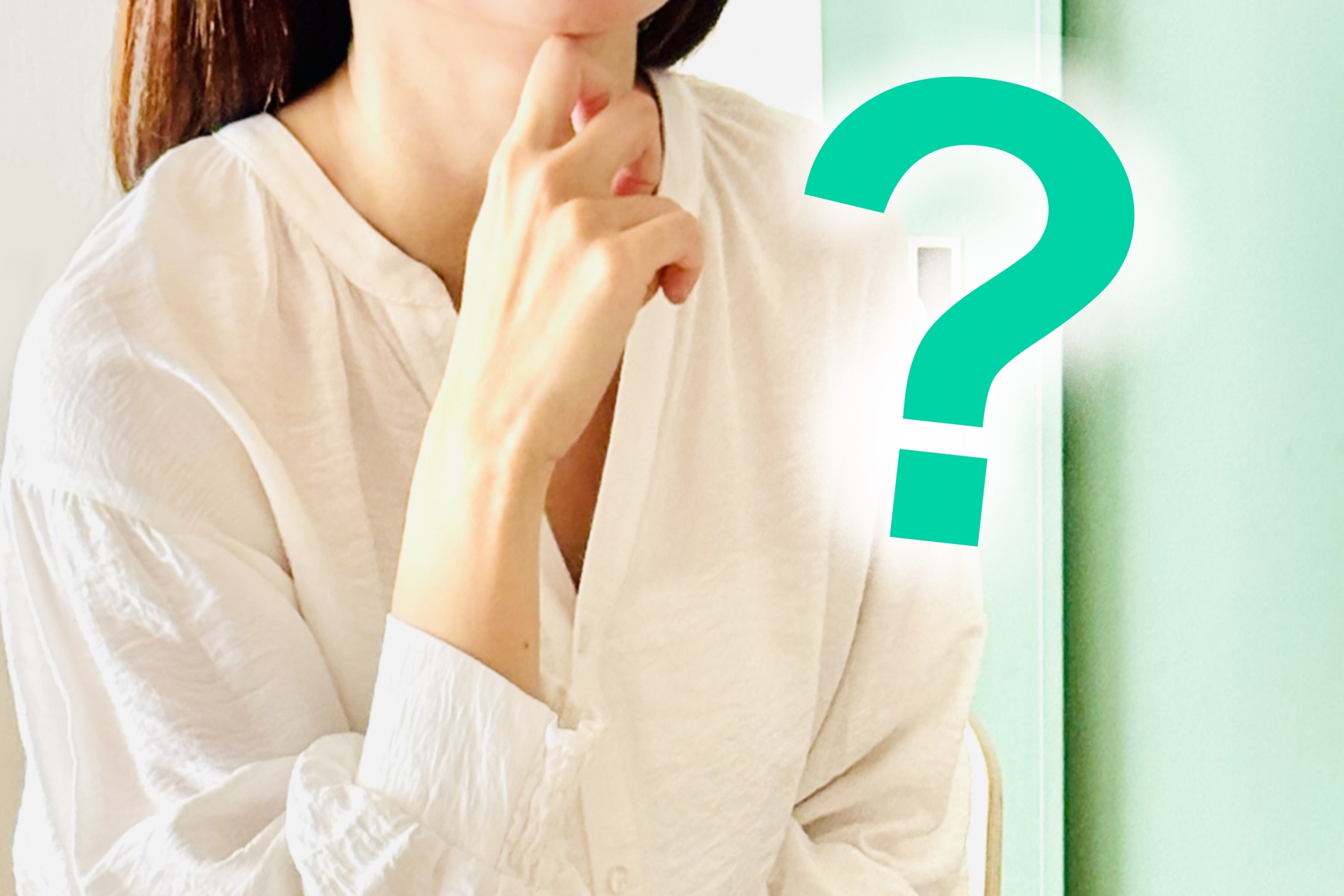じゃばらとは

排泄介助で実際に実施していても、じゃばらという言葉の意味が曖昧な方は少なくないでしょう。
じゃばらには手法や目的があり、それを理解したうえ取り組む必要があります。目的が明確になれば、適切な対応でよりよい介護が可能です。
ここでは、じゃばらの定義や目的、実施方法などの知識を基本から解説します。
介護のじゃばらのやり方
じゃばらは、平らな尿取りパットをアコーディオンのようにじゃばら状に折りたたんで使用します。
具体的には、折りたたんだ尿取りパットを男性の陰部に巻きつけるように当てたり、特定の部位に集中して配置したりする用途です。
紙おむつと合わせて使用し、テープ止めタイプの立体ギャザーの内側に入れることが大切です。
じゃばらの効果

じゃばらはおむつに隙間ができやすい方の隙間漏れを防ぐ役割があります。
夜間に尿が漏れて取り替えることになると、利用者にも介護者にも手間がかかり、利用者は睡眠を妨害されるリスクがあります。
もし尿パットを重ねて使おうとしても、裏面に防水フィルムがあるため尿は十分に吸収されません。パットの厚みが増すことが隙間の増加や褥瘡の原因になります。
やわらかい両面吸水シートを折ると隙間にぴったり入れることができ、男性器を包むように入れることで尿の勢いを抑える効果もあります。
主に使われる場面
じゃばらが主に使われるのは排泄介助のときです。おむつのなかで股間部や陰部、痩せた部分の隙間を塞ぐように入れ、伝い漏れや隙間漏れを防ぎます。
伝い漏れしやすい方には、じゃばらに折った両面吸収シートを使用して、漏れそうな部分の隙間を補うことができます。
じゃばらのデメリット

じゃばらは排泄介助において、便利な方法ではありますが、同時にデメリットもあります。現場で働いていると、ネガティブな側面はあまり意識しないこともあるでしょう。
しかし、じゃばらには皮膚トラブルや感染症のリスクなど、利用者にとって不利益な要素もあります。ここでは、じゃばらのデメリットを具体的に紹介します。
皮膚トラブルの原因
じゃばらのデメリットの一つが皮膚トラブルです。
隙間なくじゃばらを入れてしまうとおむつ内部の通気性が失われ、尿や汗による湿気を外に逃せなくなって、おむつ内の温度や湿度が上昇します。
湿度が高くなると皮膚はふやけて傷つきやすくなり、わずかな摩擦でも傷や炎症を起こしやすくなります。
傷つきやすくなった状態で圧がかかり、血流が悪化して皮膚組織が壊死するリスクが高まり、それが褥瘡をつくる一つの原因です。
感染症のリスク

じゃばらが原因で生じるリスクの一つに、感染症があります。じゃばらによってつくられるおむつのなかの湿潤環境は、感染症が発生するには十分な条件が揃っています。
尿路感染症や皮膚感染症の原因菌は温かく湿った場所で繁殖しやすいため、免疫力が低下している高齢者にとって大きなリスクになります。
尿路感染症は発熱や脱水を引き起こし、重大な体調不良を招きます。清潔さと乾燥の維持、おむつの材質や使用方法に注意する必要があります。
利用者に有益な方法としてじゃばらを使っていたとしても、結果的に感染症のリスクを高めてしまうため、じゃばらの使い方や使用理由を見直す必要があります。
利用者の不快感
じゃばらの使用は、硬くなったパットが身体にあたってしまい、不快感を招きやすい状況になります。これは日常生活を送るうえで重大な問題です。
介護士は利用者の尊厳を守る義務があります。意見や不満を表現しにくい利用者にとって、じゃばらに不快感があっても言えないことは、苦痛や痛みにつながるでしょう。
それは利用者の生活の質を下げ、尊厳を損なう行為です。介護者の都合でじゃばらを使用するのではなく、利用者の目線で快適さを保つ工夫が求められます。
じゃばらは身体拘束になる?

じゃばらにはデメリットがあり、身体拘束のリスクも含まれます。しかし具体的に何が身体拘束にあたるのか、明確な基準や判断がわからない方もいるでしょう。
ここでは身体拘束の定義を紹介し、じゃばらの使用方法や基準、注意点を提示します。
身体拘束の定義
身体拘束とは、個人の行動の自由を制限することです。
個人の行動を他者が制限することは自由と尊厳を無視した行為であり、生命や身体を保護する場合を除き、法律でも禁止されています。
具体的には、立ち上がれる方をベッドや椅子に縛りつけること、脱衣やおむつ外しを防ぐためにつなぎ服を着せることなどが挙げられます。
ほかに直接的に身体を拘束しなくても、睡眠薬や精神薬を過剰に服用させたり一つの場所に留めておくような声かけをしたりすることも、拘束の一種です。
施設や事業所の職員は、利用者一人ひとりに向き合い、身体拘束防止に向けて定期的に見直して改善を行う努力が必要です。
じゃばらが身体拘束とみなされるケース

じゃばらはおむつのなかに入れるものであり、利用者の自由を奪う身体拘束とは異なると考える方もいるかもしれません。
しかし、じゃばらが身体拘束と見なされるケースもあります。まず、身体拘束には利用者のADL低下や皮膚トラブル、精神的苦痛という悪影響が考えられます。
じゃばらの使用による悪影響には、おむつの隙間を埋めてしまうこと、湿気と熱気で弱くなった皮膚が傷つきやすくなることが挙げられます。それは利用者の自由を奪う行為と同様です。
自由を奪うだけでなく、皮膚トラブルや感染症のリスクもADL低下の原因となります。
また、じゃばらの使用で不快感や痛みを伴うことも、身体拘束で受ける精神的苦痛と同じく悪影響を及ぼします。
施設や事業所の職員は身体拘束の防止に向けて、定期的な検討が義務づけられていますが、じゃばらの使用に関しても随時見直しが必要があるでしょう。
じゃばらが身体拘束に該当するかもしれない -そう聞いても、実際にどう対応すればよいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、ハッシュタグ転職介護にご相談ください。私たちは医療・福祉業界に特化した専門知識とネットワークを活かし、現場での悩みに寄り添いながら適切なアドバイスを行っています。
「身体拘束を避けるケアの工夫」や「働きやすい職場の見極め方」など、介護現場で役立つ情報を具体的にお伝えすることが可能です。さらに入社後も継続的にフォローを行うため、安心感を持ってしてスキルアップに取り組めます。
正しい介護を実践したい方や、キャリアを着実に築いていきたい方は、ぜひ一度ハッシュタグ転職介護にご連絡ください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
パットごとの役割

尿取りパットはおむつのなかに入れる吸収パットです。パットにはさまざまな種類があり、利用者の状態や用途によって使い分けることができます。
この章では、パットの基本的な種類とその特徴、利用者の状態に応じた使い分けのポイントを整理して解説します。
パットの種類
パットにはいくつか種類があります。主なものは以下のとおりです。
- 生理用ナプキン形状
- テープ止めタイプ
- 面積が広いタイプ
- 尿や便が多くても対応できるタイプ
- 形状や機能に特徴があるタイプ
生理用ナプキンの形状をしたものは、吸収力が高い場合は170cc程度の尿を吸収できる機能をもちます。テープで止めるタイプは尿道口から肛門までカバーすることができます。
面積が広いタイプには立体ギャザーが付いているもの、ひょうたん型のものなどがあります。尿や便が多くても対応できるものは、溝やへこみなど漏れを防ぐ工夫が施されます。
形状や機能に特徴があるパットはベルトタイプや穴あきタイプなど、特殊な形状をしているため、利用者それぞれの状態に合わせて使い分けることができます。
パットの特徴

尿取りパットは、おむつのなかに入れることで、排泄があってもおむつを汚さずに済みます。パットのみを交換すればよいため、おむつ代の節約になります。
おむつごと交換する時間が短縮されるため業務が効率化され、利用者の肌を清潔に保つことが可能です。
尿取りパットと合わせて補助パットも使用すると、吸収力をあげて隙間の漏れ対策にもなるため、じゃばらを使う必要がなくなります。
使い分けのポイント
尿取りパットは、利用者のADLや生活スタイル、精神面に注意して使用しなければなりません。
自分でトイレに行ける方や誘導すればトイレに座れる方は、トイレ時間までの排尿量を考慮してパットの大きさを選びます。
就寝時から起床時までの排尿量を想定することで、夜間のおむつ交換を避けることも可能です。
ベッドで横になって過ごす時間が長い方や寝たきりの方には、通気性のよいパットを選びます。おむつのムレを防ぎ、褥瘡や感染症など皮膚トラブルの予防に効果的です。
また、利用者にとって排泄の臭いがストレスになる場合があるため、抗菌や消臭効果のあるパットを使用すると精神的な負担を軽減できます。
臭いの予防は介護士にとってもストレスの軽減につながり、介護の質の向上につながります。
介護士はパットの用途や特徴を正しく理解し、利用者の負担をできるだけ減らせるよう努めることが大切です。
私たちハッシュタグ転職介護は、求職者を人生のキャリアパートナーとして、求職から就職後のフォローまで一貫してサポートしています。
一般的な人材紹介では入社後の支援が手薄になりがちですが、私たちは悩みや迷いにも継続的に寄り添い、安心感を持って業務に取り組める環境づくりを支えています。
排泄ケアをはじめ、利用者の生活を支える知識や技術をしっかりと身につけたい方は、ぜひハッシュタグ転職介護にご相談ください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
正しい巻き方

実際に排泄介助を行っていると、実践のなかで迷いながらパットを当てている方も少なくないでしょう。パットの使用方法には、性別による違いや注意点があります。
ここでは、パットの実践的かつ具体的な巻き方を、どのように行えばよいか男女別に解説します。
男性への正しい巻き方
男性用パットには巻き留めテープがあるもの、袋状のもののほかに、立体ギャザーが陰部付近の内部にあって巻かずに使用できるものもあります。
男性への一般的な正しい巻き方の手順は、以下のとおりです。
- 片側を防水シート側に折り返す
- 中央付近から斜め上に折る
- 反対側も斜め上に折る
最初に片側を折り返すのは、皮膚に当たる不快感を避けるためです。この巻き方はパットの厚みが少なく、違和感を抑えることができます。
隙間漏れがある場合は、折り込んで底を作ると先端からの漏れを軽減できます。
男性用のパットは尿が広がってしまうのを防げる点がメリットです。しかしパットを重ねてしまう厚みが増し、行動を制限する危険性があります。
また男性用の巻き方は、十分に吸収面を活用できずに頻繁に交換する必要があるため、長時間使用できないことがデメリットです。
大きなパットを使用する際は、男性器を下向きにし、パットの面積の広い部分を被せるように装着することが重要です。
女性への正しい巻き方

女性用のパットの当て方は、できるだけ尿が広がらないようにお尻の方までカバーしなくてはいけません。具体的な当て方は以下のとおりです。
- お尻の下にパットを3分の1程度敷く
- 山型あてをする
おむつを巻くときに尿取りパットを3分の1程度お尻の下に入れると、尿道口がパットの中央部に当たるため効率よく尿を吸収できます。
大型パットを使用する際は、面積が広い方をお尻側に入れると効果的です。
また、パットを山型あてにすることで、尿の吸収を促進し内部でしっかり吸収します。
山型あては排尿量が多くても脇の立体ギャザーで止められるため、隙間漏れを効率的に防げる方法です。
パットの上部をつかんで引っ張る作業で簡単につくれるため、業務にも支障なく実施できます。
その他の巻き方
尿取りパットは男性用の巻き方、尿の吸収に有効な山型あてのほかに、谷型あてという方法もあります。
パットのあて方は山型あてが基本ですが、下痢状の水様便が尿と混ざってしまうと、吸収が間に合わず表面に広がることがあります。
そのようなときは、広い面積のパットを使い、肌との間に隙間をつくる谷型あてが適しています。谷型あては、肌とパットとの隙間に尿や便を溜めて、ゆっくり吸収させる方法です。
夜間に排尿量が多い方、やわらかすぎる便が出てしまう方には谷型あてが適しています。使用するときは、谷型あてができる面積が広いパットを選びましょう。
パットの巻き方にはさまざまな方法がありますが、利用者は一人ひとり体質や機能が異なります。正しく個別対応できるか、不安に感じる方も少なくありません。
私たちハッシュタグ転職介護は、求職者の疑問や悩みに合わせて、とことん寄り添うフォロー体制を整えています。
特に医療・福祉業界に特化した専門知識とネットワークを活かし、実際の現場に即したアドバイスを提供できる点が強みです。求職者にとって「頼れるパートナー」であることを大切にしています。
介護スキルを学びたい方や、現場で意欲的に活躍したい方は、ぜひ一度ハッシュタグ転職介護にご相談ください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
利用者の尊厳と快適さを守るために

介護現場では、業務に追われていると技術面に偏りがちになり、ケアの根底にある人権や尊厳への配慮が抜け落ちている可能性があります。
じゃばらはデメリットも身体拘束のリスクもあるため、利用者の同意や気持ちへの配慮が欠かせません。利用者の意思を尊重することが必要です。
ここでは、じゃばらを使用する際の説明や対話の大切さを解説します。
本人への説明
利用者の快適な生活を守るためには、本人へ説明をする手間を惜しんではいけません。
まずは本人の意思確認をする必要があります。意思と心身の状態をアセスメントし、ADLや精神面の分析を丁寧に実施します。
おむつ自体を不満に思っている利用者も少なくないでしょう。尿取りパットやじゃばらを使用すると不快感はさらに深まるかもしれません。
利用者の状態を分析したうえで、現状を正直に伝え、おむつやじゃばらを利用する理由を説明することが大切です。
介護者の都合ではなく、適切な分析と利用者の目線で排泄ケアを行う必要があります。
こまめなコミュニケーションが重要
利用者の尊厳と快適さのために、こまめなコミュニケーションをとることも重要です。
おむつやじゃばらの使用は決して快適な状態ではありません。不満や不快感は、介護士への不信につながる可能性があります。
十分にコミュニケーションをとっていないと不信感が募り、信頼関係を崩すことになります。
さらなる不快感を生み出し、利用者の精神的負担を増やすだけでなく、介護の質を下げてしまうでしょう。
普段からコミュニケーションをとっていれば、お互いの理解が深まり、利用者は安心感をもって介護を受け入れることができます。
コミュニケーションは利用者の尊厳を守るだけでなく、介護士への信頼や業務効率化にもつながる大切な要素です。
「もっと利用者さんに寄り添いたい」「でも、業務に追われて余裕がない…」
そんな悩みを抱えながら働いている方も、多いのではないでしょうか。
ハッシュタグ転職介護は、あなたの“よりよい介護をしたい”という気持ちを大切にします。
私たちは入職後も相談できるアフターフォロー体制を整えており、就職後も定期的にヒアリングを実施。
職場での人間関係や働き方、キャリアに関するご相談にも丁寧に寄り添い、あなたが安心感を持って働けるようサポートします。
また、事業所側にも求職者が働きやすい環境づくりのアドバイスを行い、職場の環境改善にも積極的に取り組んでいます。
「利用者にも自分にも、優しい介護がしたい」
そんなあなたは、ぜひ一度、ハッシュタグ転職介護にご相談ください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
介護士として利用者に快適な生活を届けよう

介護現場では、排泄ケアをする際におむつのなかに尿とりパットを入れるケースが少なくありません。
吸収力を上げるためにパットをじゃばらに折って入れる場合がありますが、それは身体拘束にあたる可能性があります。
介護士として利用者に快適な生活を届けるためには、利用者の立場で考えられる柔軟性と知識が必要です。
よりよいケアを実施するためには、正しい知識を実践できる職場環境や研修制度が整った施設の選択が重要です。
現状よりも介護士として成長したいと思う場合は、転職という選択肢もあります。
あなたに合った職場選びを、就職後までサポートします。
私たちハッシュタグ転職介護は、介護職の方が大切にしている条件や希望を丁寧にヒアリングし、一人ひとりに合ったぴったりな職場をご提案しています。
さらに、入職後も定期的なヒアリングを実施し、職場での悩みやキャリアに関する相談に対応するアフターフォロー体制も整っています。
また、医療・介護業界に精通した専門エージェントが在籍しており、制度や職場選びのポイントについても的確なアドバイスが可能です。
「もっと利用者の役に立ちたい」「学びながら成長できる環境に転職したい」
そんなあなたの思いを、私たちは全力で支援します。
あなたに本当に合った職場、私たちと一緒に見つけましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼