介護職の夜勤は眠い?

夜勤は、私たちの体内時計に大きな影響を与えます。人の体は、約24時間周期で睡眠や覚醒のリズムを刻んでいます。
体内時計は、夜になると睡眠ホルモンのメラトニンが分泌されることで眠くなり、朝の光を浴びると分泌が止まって目が覚める仕組みです。
しかし、夜勤ではこのリズムが崩れやすく、特に夜勤と日勤を交互に行うシフトでは体内リズムが安定しません。勤務後に朝日を浴びることで体が朝だと誤認し、疲れていても寝つきが悪くなり、慢性的な疲労につながります。
また、日中の睡眠は騒音や光の影響で質が低下しやすいため、睡眠が十分に取れず夜勤中に眠気を感じやすくなります。
介護職の夜勤の仕事内容

介護職の夜勤は、ただ施設内を見回るだけではありません。入居者の健やかな暮らしと健康を守るため、夜勤ならではの重要な業務が数多くあります。
日中とは違い、静かな時間のなかで体調変化の対応や生活のサポートを行うことが求められます。夜勤の仕事内容は、以下の6つです。
1つ目は、夜間巡回です。数時間ごとに入居者の部屋を訪れ、呼吸や体調に変化がないかを確認します。必要に応じて、寝たきりの方の体位変換も行います。
夜間巡回では、入居者を起こさないようドアの開閉や足音に気を配ることが大切です。部屋の照明はつけず、ライトで足元や必要な部分だけを照らしながら進める必要があるため、日勤とは異なる細やかな配慮が求められます。
2つ目は、排泄介助です。夜間、頻尿で目を覚まし、介助が必要になる方も少なくありません。あらかじめ決めた時間に起こしてトイレに誘導したり、移動が難しい場合はオムツ交換を行ったりします。
深夜でもトイレに行きたい方がいれば、その都度対応します。排泄の回数やタイミングは人によって異なるため、状況に応じた柔軟な対応が大切です。
3つ目は、就寝準備から入眠までをサポートする就寝介助です。自分で着替えるのが難しい方には、夜間着への着替えを手伝います。
さらに、歯磨き・入れ歯の洗浄・ベッドへの誘導・洗顔なども行い、快適に眠れる環境を整えます。就寝介助では、本人ができない部分だけを補うように心がけましょう。
4つ目は、ナースコールの対応です。入居者のベッドにはナースコールボタンがあり、「トイレに行きたい」「飲み物を取ってほしい」などの日常的な要望が多く寄せられます。
その際には、スタッフが素早く部屋へ行き、ほかの方を起こさないよう静かに対応します。しかし、ナースコールは要望だけではありません。なかには「体調が悪い」という連絡もあります。
体調不良は緊急性を伴う場合があるため、すぐに入居者の様子を確認し、医療関係者に連絡します。緊急時の対応手順は事業所でマニュアル化されているため、落ち着いて行動できるよう、日頃からマニュアルを確認しておくことが重要です。
5つ目は、食事のサポートと服薬確認です。夜勤では、夕食と翌朝食のサポートをします。配膳後は入居者がきちんと食べているか、量や食べ進み具合の確認が必要です。
食事を終えた方から順番に食器を下げ、早く部屋に戻りたい方がいる場合は部屋までの移動介助を行います。
また、服薬確認も欠かせない重要な業務です。薬は飲み忘れや飲み間違いがないよう、手渡しや声かけでしっかり確認します。
入居者の健康状態を維持するためにも、食事と服薬の両方を丁寧にサポートすることが求められます。
6つ目は、起床介助です。入居者が起き上がる際にベッドから転倒しないようサポートし、必要に応じて普段着への着替えを手伝います。その後は朝食の準備を行い、スムーズに食事を始められるようにします。
食後は、口内を清潔に保つために口腔ケアが必要です。また、男性の入居者には髭剃りを手伝う場合があります。1日のスタートを快適に迎えられるよう、起床時から身支度までの流れを支援します。
「自分に合った職場を選びたい」「体に負担をかけずに夜勤をしたい」と考える方は多いものです。
ハッシュタグ転職介護では、介護業界に精通したアドバイザーが希望に沿った職場をご紹介します。
相談から入社後のフォローまで一気通貫で対応し、スピード感のあるマッチングを実現しています。担当者が変わらないため情報の行き違いも少なく、安心感を持って転職活動を進められます。
まずは無料相談で、あなたの要望や悩みをお聞かせください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
介護職の夜勤で眠くなりやすいタイミング

「夜勤中に眠くなるタイミングはいつ?」や「なぜ眠くなるの?」と、疑問に感じる方もいるでしょう。
夜勤は体内リズムが乱れやすいため、どうしても眠気を感じやすいものです。しかし、あらかじめ眠気がピークになりやすい時間帯を知っておけば、事前に準備や対策をとることができます。
ここでは、夜勤で眠くなりやすい3つのタイミングを詳しく解説します。
デスクワーク中
夜勤で特に眠気を感じやすいのは、デスクワークをしているときです。日中は入居者が起きているため、体を動かす場面が多くあります。
一方、夜勤は入居者が眠っている時間が長く、介護記録の記入やレクリエーションの企画書の作成など座って行う業務が中心です。
体を動かす機会が少ないうえ、同じ姿勢で長時間作業を続けることで眠気が強まりやすくなります。
食事を摂った後
食後も眠気を感じやすくなります。その理由の一つは、血糖値の変化です。食事をすると血糖値が上昇しますが、特に炭水化物を多く含む食事では、この上昇が急激になります。
そして一時的にエネルギーが供給された後、血糖値は下降します。この急な上昇と下降が、体をリラックス状態にし、眠気を引き起こす原因です。
もう一つの理由は、消化活動による血流の変化です。食事を摂ると、消化器官が食べ物を分解して栄養を吸収するために、多くのエネルギーを必要とします。
そのため、血液が胃や腸に集中し、ほかの部位への血液供給が一時的に減ります。眠気を感じやすくなるのは脳への血流や酸素、栄養の供給が減少し、思考が鈍くなってしまうのが要因です。
作業が少ないとき

作業が少ないときや、ナースコールが落ち着いているときは、眠気を感じやすくなるため注意が必要です。
長時間座ったままだと集中力が低下し、脳への刺激が減ることで、副交感神経が優位になって眠気を感じやすくなります。
「自分に合った職場がわからない」「未経験でも働けるのか不安」などの悩みを抱えていませんか。
ハッシュタグ転職介護では、介護・福祉業界に特化したアドバイザーが、履歴書の添削や面接対策、求人の紹介まで丁寧にサポートします。
スピード感のある一気通貫型の仕組みで、効率よく転職活動を進められるのも強みです。
さらに入社後のフォローも行っているため、長期的なキャリア形成まで支援できます。
まずは無料相談で、あなたの想いをお聞かせください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
夜勤で眠くなったときに眠気を覚ます方法

「夜勤中の眠気は我慢するしかないのかな……」と感じていませんか?実は、ちょっとした工夫で眠気を和らげ、集中力を取り戻せます。
ストレッチや軽い運動で血流を促したり、短時間の仮眠で脳をリフレッシュしたりと、眠気を覚ます方法はさまざまです。
ここでは、夜勤中に眠くなったときにすぐ試せる実践的な眠気対策を紹介します。
軽いストレッチなど体を動かす
夜勤で眠気を感じたときは、軽いストレッチや体を動かすのがおすすめです。体を動かすことで交感神経が刺激され、脳が活動モードに切り替わります。また、体温や血圧が上昇するため、眠気が覚めやすくなります。
手首や足首を回す、背中を伸ばすなど簡単な動きだけでも、眠気の軽減に効果的です。さらに、ストレッチ以外にもタオルをたたんだり掃除をしたりすると、じっとしている時間を減らすことができ眠気を抑えられます。
ほかの職員と会話をする
ほかの職員と会話をすることも、有効な眠気対策です。会話によって脳が活性化され、刺激を受けることで眠気が覚めやすくなります。
また、話すことで口元や表情筋が動き、血流も促進されます。夜勤中に眠気を感じたら、積極的に会話をするようにしましょう。
ミント系のガムやタブレットを食べる

眠気を感じたら、ミント系のガムやタブレットを口にするのも効果的です。ガムを噛むことで脳の血流が促進され、脳が活性化されるため眠気が和らぎます。
特にミント系は口のなかがスッキリし、気分もリフレッシュできます。ガムやタブレットは持ち運びしやすく、ポケットに入れておけば必要なときにすぐ使える便利な眠気対策です。
カフェインを摂取する
眠くなり始めたときは、カフェインを摂取するのもおすすめです。カフェインには中枢神経を刺激して眠気を覚ます作用があり、さらに疲労回復の効果も期待できます。
コーヒーや緑茶、エナジードリンク、紅茶、チョコレートなど、身近な食品に含まれています。ただし、過剰に摂取すると覚醒作用が強く出たり、血管拡張による体調不良を招いたりする恐れがあるため適量を心がけましょう。
顔を洗う
顔を洗うことも、手軽にできる眠気対策のひとつです。手や顔には知覚神経が密集しているため、水で顔を洗うとその刺激が脳に伝わり、眠気を覚ましやすくなります。
特に冷たい水は感覚神経を刺激して脳を活性化させるので、気分をリフレッシュするのに効果的です。特別な準備も必要なく、その場で取り入れられるため、夜勤中に強い眠気を感じたときの即効性のある方法として有効です。
目薬をさす

目薬をさすと眠気が覚めやすくなります。眠くなるとまぶたが重くなり視界がぼやけやすくなりますが、目薬を使うと脳が刺激されて気分がスッキリします。特に、クールタイプの目薬をさすと爽快感が広がるのでおすすめです。
さらに、目薬は眠気覚ましだけでなく、目の乾燥や疲れ目の改善にも役立つ効果があります。パソコンや記録作業などで目を酷使する夜勤では、眼精疲労や充血の予防にもつながります。
外の空気に当たる
夜勤中に眠気を感じたときは、外の空気を取り入れるのがおすすめです。窓を開けて深呼吸したり、少し外に出て新鮮な空気を吸ったりすることで、脳に酸素がしっかり送り込まれて気分を切り替えやすくなります。
同じ温度で保たれた室内に長時間いると、快適さから体がリラックスしすぎて眠気に襲われることがあります。そんなときに外の冷たい風や心地よい空気に触れると、普段とは違う刺激で目が覚めやすくなり、眠気対策として効果的です。
部屋を明るくする

眠気を覚ますためには、部屋を明るくしましょう。暗い部屋だとメラトニンが分泌されやすくなるため、眠気を感じやすくなります。
そのため、夜勤中は部屋を明るくしてメラトニンの分泌を抑えることが大切です。強めの照明や作業スペースを明るくすることで眠気が軽減され、集中して業務に取り組みやすくなります。
仮眠をとる
夜勤中にどうしても眠気を抑えられないときは、仮眠をとるのも有効です。20分程度の仮眠でも疲労回復や眠気覚ましの効果が期待でき、頭がスッキリします。
ただし、長く眠りすぎると逆にだるさが残り、リフレッシュ効果が薄れてしまう場合があります。そのため、仮眠は短時間で切り上げることが大切です。
特に10〜20分程度の仮眠をこまめに取り入れると、眠気を抑えながら疲労感の軽減にもつながります。
「夜勤の経験がないから不安」と感じている方は、ぜひハッシュタグ転職介護の無料相談をご利用ください。
介護・福祉業界に特化したアドバイザーが、あなたの希望や不安を丁寧にヒアリングし、働きやすい職場をご紹介します。
スピード感のある一気通貫型のサポートに加え、入社後も定期的にフォローを行っているため、転職後の悩みやキャリア相談にも対応できます。
まずはお気軽にご相談いただき、あなたに合った職場を一緒に見つけていきましょう。
夜勤前に眠れない場合の対処法

「夜勤をすると昼間にちゃんと寝られるか心配」や「寝不足で仕事に支障が出ないかな……」と、不安に感じる方も多いでしょう。
夜勤中に眠気を防ぐためには、量よりも質を意識して睡眠をとることが大切です。しっかり休める環境を整えることで、翌日の業務にも集中しやすくなります。
ここでは、夜勤前にぐっすり眠るための具体的な方法を3つ紹介します。
遮光カーテンを活用する
夜勤前にしっかり眠るためには、遮光カーテンの使用がおすすめです。遮光カーテンは、外からの光をほとんど通さず、昼間でも部屋を暗くできます。
人は光を浴びると脳が覚醒して眠りにくくなりますが、遮光カーテンを使えばメラトニンの分泌が促され、自然な眠気を感じやすくなります。
遮光率は通常のカーテンと比べて90〜99%と高く、昼間の強い日差しを遮断するのに効果的です。静かで暗い環境を整えることで、ぐっすり眠れる時間を確保でき、夜勤に備えてしっかり休養をとれます。
就寝前にスマートフォンを見ない
就寝前は、スマートフォンの使用を控えましょう。スマートフォンの画面から発せられるブルーライトはメラトニンの分泌を妨げるため、体が昼だと錯覚してしまいます。
脳が覚醒すると目が冴え、なかなか眠りにつけなくなるので注意が必要です。また、ブルーライトを浴び続けると交感神経が活発になり、リラックス状態から遠ざかってしまいます。
ぐっすり眠るためには、少なくとも寝る2時間前からスマートフォンの使用をやめ、部屋を暗めにして過ごすのがおすすめです。
就寝前にカフェインを摂取しない

ぐっすり眠るためには、就寝前にカフェインを摂取しないことが大切です。通常、アデノシンという物質が働くことで眠気を引き起こしますが、カフェインはこの働きを抑制してしまうので眠りにくくなります。
さらに、カフェインには利尿作用があるため、睡眠中にトイレに行く回数が増えることもあります。目が覚めてしまうと再び眠りにつきにくかったり、眠りが浅くなったりする可能性があるので、カフェインの摂取は控えましょう。
ハッシュタグ転職介護では、夜勤未経験の方にも働きやすい職場をご紹介しています。介護・福祉業界に特化したアドバイザーが、悩みや希望を丁寧に伺い、適切な職場をご提案します。
履歴書の添削や面談対策などもサポートしており、スピード感のある一気通貫型の対応で効率的に転職を進められます。
さらに入社後もフォローを継続しているため、キャリアアップや職場での悩みについても気軽に相談できます。
まずは無料相談で、あなたの想いをお聞かせください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
介護職の夜勤の注意点
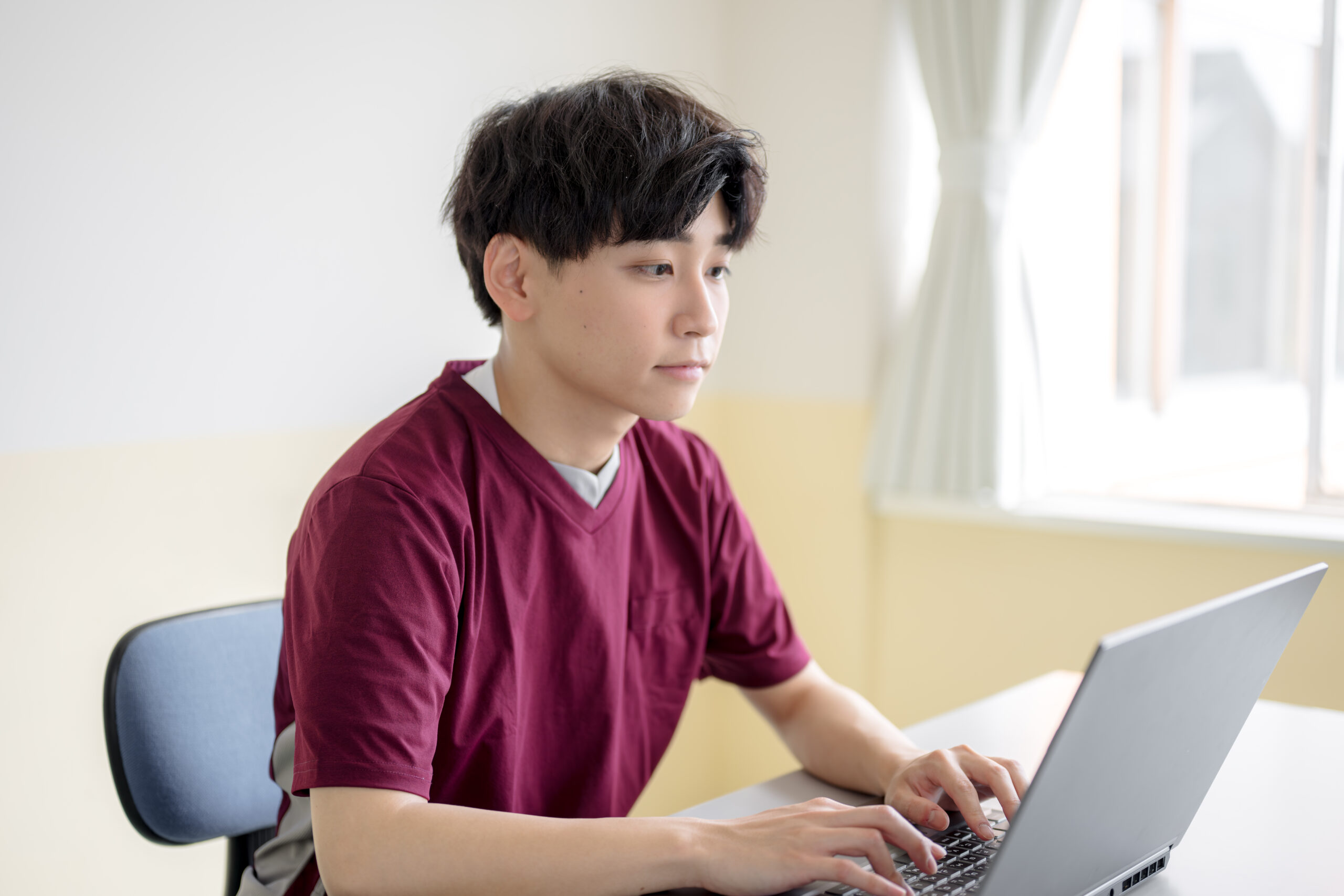
介護職の夜勤では、体調管理と緊急時対応の両方に注意が必要です。夜勤と日勤を交互にこなすシフトでは生活リズムが乱れやすいため、夜勤明けでも昼間は起きるよう意識したり、バランスのよい食事を心がけたりして体調を崩さない工夫が大切です。
さらに、夜勤中は入居者の急変や転倒など、緊急対応が求められる場面が発生する可能性があります。そのため、緊急時マニュアルを把握しておくとともに、心肺蘇生法やAEDの使用方法を身につけておきましょう。
夜勤は一人で担当することもあるため、落ち着いて判断し、行動できる心構えが重要です。
介護職の夜勤について相談しよう

「夜勤と日勤のシフトに体がついていけるか心配」や「体調管理できるかな……」と、不安に感じる方も少なくありません。
夜勤では、日常的な体調管理・眠気対策・質のよい睡眠の確保など、気をつけるべきことが多くあります。そのため、自分の体質や生活リズムに合った職場を選ぶことが、無理なく働き続けるための大切なポイントです。
ハッシュタグ転職介護では、自分のライフスタイルにあわせた夜勤条件や施設を見つけられます。相談から企業紹介、選考対策までを一人の担当者が担うため、スピーディーなマッチングが可能です。
介護・福祉業界に特化したアドバイザーが、あなたの不安や悩みに寄り添い、働きやすい環境をご提案します。
入社後のフォローも行っているため、長く続けられるキャリア形成をしっかりサポートします。
まずは無料相談で、あなたの希望をお聞かせください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼






