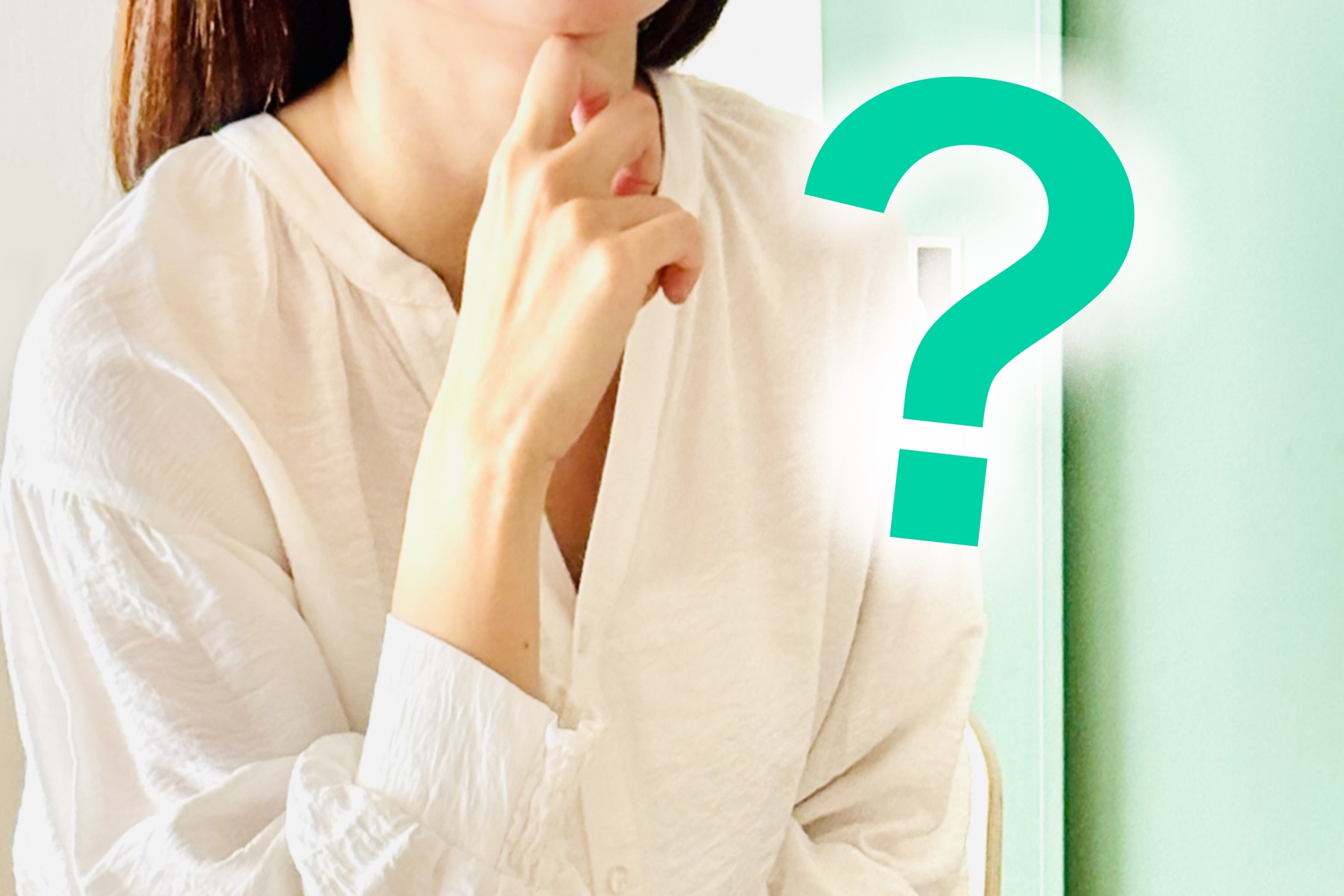スピーチロックとは

スピーチロックとは、言葉によって高齢者の行動を制限する行為です。
拘束により行動が制限されると、身体機能の低下、感染症への抵抗力の低下、精神的苦痛、さらには認知症の進行などが生じます。
さらに職員自身の士気の低下や、施設や事業所への不信感、拘束された方の心身機能低下による経済的負担が生じる可能性があります。
スピーチロックを含む身体的・精神的拘束は、国家レベルで問題視されている重要な課題です。
3つのロックについて

3つのロックとはフィジカルロック、ドラッグロック、スピーチロックのことです。
フィジカルロックとは身体拘束のことで、物理的に拘束して身体の動きを制限します。
転倒や転落の恐れがあると判断された場合に、拘束する選択をしてしまうことがあります。
身体を動けなくしてしまう以外に考えられるのは、ベッドの柵を高くしたり柵で囲ったりすることです。
胃瘻や経鼻栄養などで体に入っている管を抜いてしまう恐れがあるときに、両手にミトンをはめてしまうこともフィジカルロックにあたります。
ドラッグロックは不用意に動いてしまう方の行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させることです。
認知症の方で、夜通し起きていたり大声をあげたりしている場合、睡眠薬を服用させて強制的に寝かせてしまうことがあります。
また、薬が強すぎると、眠すぎてほとんど食事が摂れないという弊害が生じます。
ほかに起こりやすい事態が、一日まったく起きられずに夜間目が覚めてしまい、再び睡眠薬を飲むという悪循環に陥ることです。
どれも高齢者の尊厳や主体性を阻むもので、施設や病院それぞれが対策を考えることが重要です。
スピーチロックが相手に与える影響

スピーチロックが相手に与える影響はとても大きく、生活自体に支障が出ることもあります。
利用者が自信を失ったり、認知症が悪化したりする恐れがあり、身体的にも心理的にも大きなダメージを与えかねません。
ここでは、スピーチロックがどのような影響を与えるのか、具体的に説明します。
行動意欲の低下
スピーチロックは高齢者の活気を奪い、行動意欲を低下させます。それは、体力や生活機能の低下を引き起こす要因の一つです。
身体的な機能低下だけでなく、心肺機能や感染症への抵抗力の低下、食欲不振などの内的弊害もあります。
さらに、不安や怒り、あきらめなどの精神的苦痛も与えます。
この苦痛が意欲低下につながり、さらに生活機能の低下が進んでしまう悪循環に陥ることが少なくありません。
認知症症状の悪化

動きが制限されると、認知症症状が悪化する傾向があります。これは精神的苦痛や意欲低下も影響しています。
それらが重なると、結果として認知症による行動や心理症状が増悪する以外に生じるのが、一時的な意識障害であるせん妄です。
場所や人の判別ができなくなったり、幻覚や錯覚が見えたりする症状が現れる危険性があります。
それまで見られなかった場合でも、突然大声を出したり怒ったりする症状が現れる可能性も否定できません。
要介護度の悪化
スピーチロックによって利用者が行動を制限されたときに考えられるのが、関節拘縮や筋力低下、四肢の廃用症候群といった身体的機能の低下です。
それにより、うまく身体が動かせなくなって要介護度が悪化し、さらに介助が必要になる危険性があります。
また身体的機能の低下のほか、認知症症状の悪化でも要介護度は高くなるので、注意が必要です。
介護度が悪化すると介護サービスを多く受けられることはありますが、長期的な施設入所や介護用品の購入などで費用がかさむ可能性があります。
コミュニケーションの悪化

スピーチロックは精神的苦痛を与え、認知症の進行やせん妄の頻発を招く恐れがあります。
それは会話が成り立たない状況になる可能性があり、十分なコミュニケーションをとれないリスクがあります。
また拘束されて不安や怒りの感情を持っていると、職員への信頼が揺らぎ、会話や介助への拒否やトラブルのもとになることも否定できません。
言葉には力があり、特に否定的な言葉は心に大きなダメージを与えます。
スピーチロックが好ましくないと分かっていても、忙しい介護現場では思わず使ってしまわないか不安に感じる方もいるでしょう。
ハッシュタグ転職介護では、求職者のキャリア相談から入社後のフォローまで、一人の担当者が一貫してサポートする一気通貫型の仕組みを採用しています。
キャリアアドバイザーとリクルーティングアドバイザーを統合しているため、スピーディーで無駄のない対応が可能です。
「介護現場での適切な言い回しがわからない」「働き方に不安がある」そんな方もご安心ください。
経験豊富なアドバイザーが丁寧に寄り添い、あなたに合った職場選びをサポートします。
まずは無料相談で、あなたの悩みや希望をお聞かせください。あなたに適切な一歩を一緒に見つけましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
スピーチロックが発生する原因

スピーチロックは利用者に大きな影響を与えますが、その背景には原因があります。
やってはいけないと思いつつも、現場ではなぜスピーチロックが生じてしまうのか、疑問に思う方もいるでしょう。
ここでは、現場でスピーチロックが発生しやすい背景を解説します。
人手不足
介護現場の人手不足は、スピーチロックや身体拘束などで高齢者の行動を抑えてしまう理由の一つです。
現場で一定人数の職員が確保されていても、要介護者や認知症が重い方などに時間をかけている状況があります。
そのため、結果として考えられることは、動くと危ないと判断される方の動きを制限してしまうことです。
職員が一人あたり対応する業務が増えるため、時間や心に余裕がなくなって、結果的に乱暴な言い回しになってしまうことが考えられます。
ケアなどの対応の重なり
介護施設では一定数の利用者が入所しているため、複数の利用者が同時にケアを必要とする場合が少なくありません。
ケアが重なってしまうと、一人ひとりにかける時間が少なくなり、利用者の要望を叶えることが難しくなってしまいます。
急を要するニーズを優先せざるを得なくなり、結果として優先度が低いと判断された利用者の希望や行動を、抑制する状況が生じやすくなります。
利用者の危険行動

利用者の危険行動はスピーチロックを発生させる要因の一つです。
介護施設やその職員は利用者の安全性を守る立場であり、転倒や転落が起こるリスクがある場合は、予防する義務があります。
利用者が新しい行動を起こそうとした際に選択されやすいのは、行動を制限することです。
例えば、歩く力がない方が歩こうとした場合、咄嗟に言葉で強く否定してしまう危険性があります。
知識不足
スピーチロックが生じる理由の一つが知識不足です。拘束に関する知識が不十分だと無意識にスピーチロックをしてしまう可能性があります。
言い方は丁寧でも、利用者の行動を制限する内容を口にしてしまっているかもしれません。
組織全体で、安易な身体拘束やスピーチロックが常態化している可能性もあります。
現場で勉強会や研修などを行うほか、積極的に本を読んだり調べたりすることで、知識を深めることが大切です。
スピーチロックが発生する背景には、状況だけでなく職場環境やスタッフの精神状態も影響している可能性があります。
ハッシュタグ転職介護では、労働環境や人間関係など、求職者が重視するポイントを丁寧にヒアリングし、安心して働ける職場をご提案します。
また、密なコミュニケーション体制で不安や悩みをしっかりサポートし、転職後も定着しやすいフォローを実現しています。
落ち着いて長く働ける職場を見つけたい方は、ぜひハッシュタグ転職介護にご相談ください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
スピーチロックを防ぐためのポイント

スピーチロックが与える影響や原因について、職場環境や状況などによる要因が大きいと解説してきました。
しかしスピーチロックがやってはいけないこととわかっても、具体的に何に気をつければよいかわからない、という方もいるでしょう。
スピーチロックは知識や心がけ次第で防止することができます。
ここでは、スピーチロックをしないための簡単な工夫を紹介します。
利用者の立場になって考える
スピーチロックを防ぐには、利用者の立場になって考えることが重要です。
利用者が行動するのには理由があります。
利用者が自ら理由を説明できるとは限らないため、その行動の意図や気持ちを推測する必要があります。
それには職員協働で対策にあたることや、普段から利用者を理解しようと努力する姿勢も大切です。
言い換え表現を意識する
スピーチロックになりそうな言葉を、意識的に言い換えることで、行動を制限する言い方を避けられます。
例えば、待っていて欲しいときは「◯◯してくるので、◯分お待ちいただいてもよいですか?」と確認します。
また、動くことにリスクがある場合は「どこに行きたいんですか?」と理由を尋ねる言い回しが有効です。
乱暴な言い回しではなく、利用者の意思を確認したり理由を説明したりする言い方に換えましょう。
研修やミーティングで理解を深める

研修やミーティングなどで、身体拘束やスピーチロックについて理解を深めることも重要です。
施設によっては、全職員で知識を深めるために、定期的に研修や勉強会を行なっているところもあります。
安全性を守るためにやむを得ないと正当化せず、適切な対応を模索する姿勢が大切です。
理解を深めることによって、利用者の行動を抑制する以外の方法を考え、安易な拘束やスピーチロックを防ぐことができます。
否定形ではなく依頼型で伝える
利用者に対して話す際に、否定形ではなく依頼型で伝える工夫も大切です。
例えば、行動してしまうことについては「動いてはいけません」ではなく「それは危ないので、◯◯しませんか?」と提案します。
また、食事をなかなか食べない場合は「食べないとだめです」ではなく「温かいうちにどうぞ」や「水分補給されますか?」などと伝えます。
「ご迷惑をおかけしますが」や「恐れ入りますが」というクッション言葉を使うことも有効です。
否定形は、利用者の意思を否定したり職員の意図を押し付けたりする言い方です。
依頼や提案の言い回しにすると、やわらかい言い方になるだけでなく、利用者の尊厳や意思を守ることができます。
施設や病院では、研修やミーティングのほか、言い換え表現を職員に周知して対策しているところもあります。
それでも「現場で本当に対応できるだろうか」と、不安を感じる方は少なくありません。
ハッシュタグ転職介護には、医療・福祉業界に特化した専任アドバイザーが在籍しており、業界ならではの課題や求職者のニーズに応じた的確なアドバイスをご提供します。
転職活動だけでなく、「新しい職場でしっかり活躍したい」と考えている方も安心してご相談いただけます。
あなたが自信をもって働けるよう、私たちが全力でサポートします。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
スピーチロックの具体例

スピーチロックが発生してしまう原因や、防ぐためのポイントを解説しました。
しかし具体的にどのような発言をしてはいけないのか、無意識に言ってしまいそうで怖い、と疑問や不安を持っている方もいるでしょう。
ここでは具体的な発言を挙げて、なぜそれがスピーチロックにあたるのか、言い換え表現とともに説明します。
萎縮させてしまう発言
スピーチロックの代表的な例が萎縮させてしまう発言です。「立っちゃダメ」「動かないで」などという言い回しは利用者を萎縮させます。
「どうされましたか」や「まもなくご飯なので待っていましょう」など、行動の理由を尋ねたり理由を提示したりします。
丁寧語を使っていたとしても、強い言い方をすると、それだけで利用者は尊厳を否定されたような気持ちになってしまうでしょう。
忙しかったり疲れていたりすると、語気が強くなる恐れがあります。言い方も意識して気をつけましょう。
侮辱するような発言
利用者を侮辱するような発言も、スピーチロックの一つです。利用者をおとしめるような発言は避けなくてはいけません。
明らかに侮辱するような言葉は、あまり利用者本人の前では言わないかもしれませんが、職員間でも言ってはいけない言葉なので注意しましょう。
存在を否定する発言

スピーチロックの一つに存在を否定する発言があります。「頭が悪い」や「役立たず」などの強い言葉は利用者の尊厳を傷つけます。
ほかに「こんなこともできないの」や「何でこんなことするの」なども利用者を否定し、抑制する言い方です。
もし敬語を使っても否定的な内容であれば意味がありません。
できないことがあっても「お手伝いしましょうか?」や「ご自分のペースで大丈夫ですよ」とやわらかく声かけしましょう。
また、行動を責めるのではなく「何かありましたか?」や「何か必要なものはありますか?」と寄り添う言い回しをするのが適切です。
利用者の行動や発言には理由があるので、症状や考え方を尊重した対応を心がける必要があります。
職員間や現場ではさまざまな会話をする機会があります。
丁寧な言葉遣いができるか、適切にやり取りできるか、不安や悩みを抱えている方がいるかもしれません。
ハッシュタグ転職介護では、求職者一人ひとりの希望やニーズに寄り添い、丁寧なヒアリングとコミュニケーションを重ねながら、あなたにとって適切な職場を一緒に見つけていきます。
条件だけでなく、職場の雰囲気や人間関係まで考慮したマッチングで、長く安心して働ける環境をご提案します。
「自分に本当に合う職場を見つけたい」とお考えの方は、ぜひ一度ハッシュタグ転職介護にご相談ください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
介護現場でのスピーチロックに気をつけて気持ちのよい介護を行おう

スピーチロックとは、言葉で利用者の行動を抑制してしまうことです。
行動を抑えることは、身体的機能の低下だけでなく、精神的苦痛や認知症の症状が悪化する危険性が高い行為です。
国家レベルで重要視されていることであり、職員個人だけでなく、組織で対策していかなければならない重要な問題といえます。
スピーチロックをしないためには、言葉を丁寧な言い方に工夫することが重要です。
介護は利用者と心を通わせる仕事であり、思いやりを持った丁寧な言葉遣いは、利用者の尊厳を守ることにつながります。
それは未経験でも思いやりの姿勢があれば可能であり、職員にとっても気持ちよく仕事する環境をつくることができます。
しかし頭ではわかっていても、職員数が少なかったり仕事が忙しかったりすると、思わず乱暴な言い方をしてしまうことがあるかもしれません。
スピーチロックを無意識にしてしまうのではないか、と心配になる方もいるでしょう。
ハッシュタグ転職介護は求職者に対して企業紹介から入社後のフォローまで行い、入社後も定期的なヒアリングを実施して職場の悩みの相談を行っています。
医療や福祉が得意分野であるエージェントもいるため、希望も悩みも共有しやすいといえます。
自分に合う職場を見つけたい方、気持ちよく仕事をしたい方は、ぜひハッシュタグ転職介護にご相談ください。
あなたの希望に沿った転職をお手伝いさせていただきます。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼