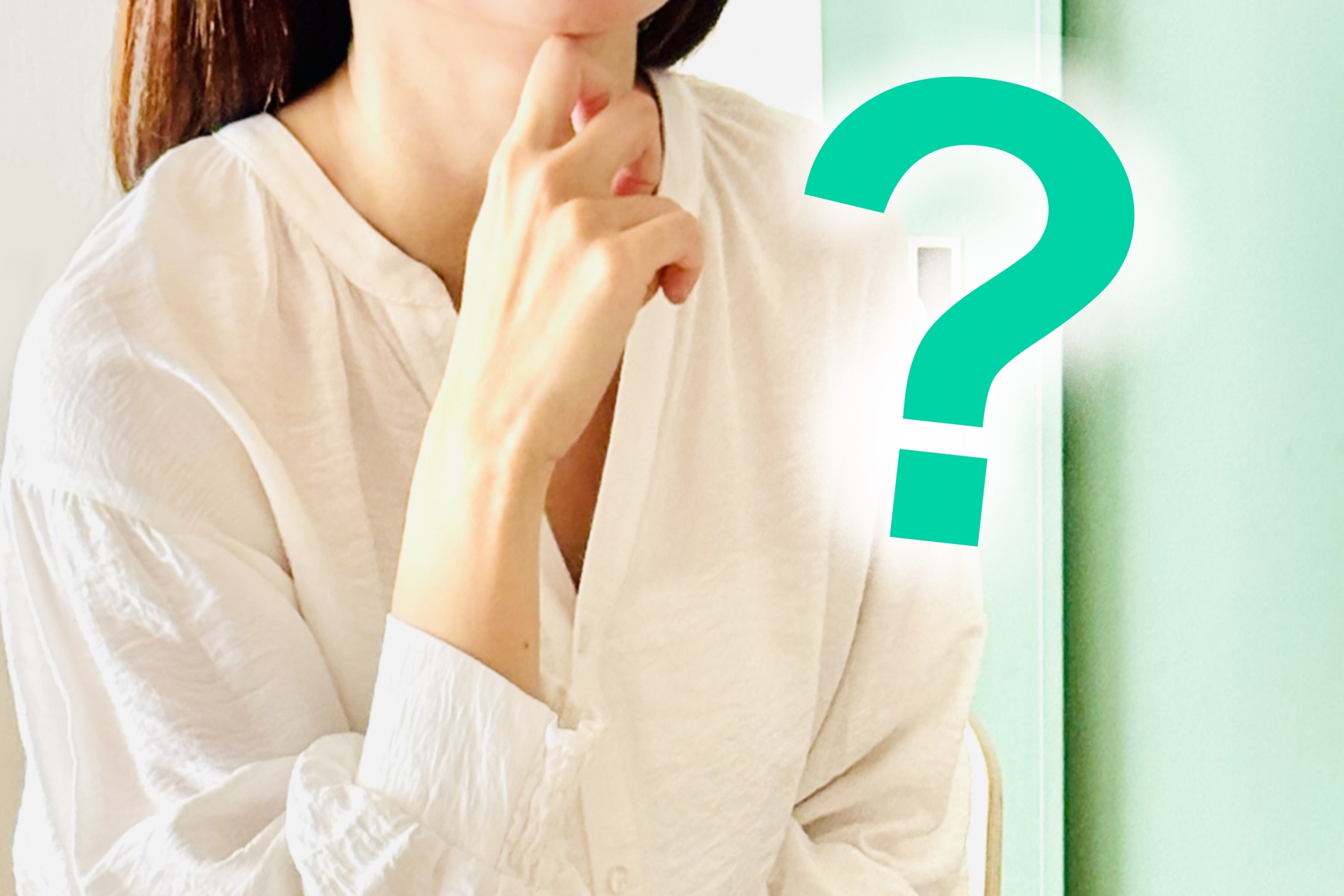介護職は産休と育休を取れる?

介護の職場は忙しいですが、産休と育休は法律で定められた権利です。介護職だからといって取れないことはありません。
産休と育休制度

産休と育休は、それぞれ根拠となる法律が異なります。産休(産前産後休暇)は労働基準法第65条に基づく制度で、出産予定日の6週間前(双子なら14週間前)から出産後8週間まで取得できます。
なお、産後8週間は本人の希望に関係なく働けません。
育休(育児休業)は育児・介護休業法に基づく制度で、原則として子どもが1歳になるまで取れます。両親とも育休を取る場合は1歳2ヶ月まで、保育園に入れない場合は2歳まで延長できます。
なお、男性の育休取得も可能で、2023年の厚生労働省の調査では男性の育児休業取得率は30.1%と年々増加傾向です。夫婦で協力して子育てする環境づくりが進んでいます。
産休と育休の取得条件
産休に条件はありません。正社員でもパートでも、働いている女性なら誰でも取得可能です。入社してすぐでも問題はなく、妊娠や出産を理由にした解雇は、男女共同参画社会基本法や労働基準法により禁止されています。
また、育休には条件を満たす必要があり、以下のとおりです。
- 同じ会社で1年以上働いている
- 子どもが1歳6ヶ月になるまでに契約が終わる予定がない
- 週2日以下の勤務ではない
これらの条件をクリアしていれば育休を取得できます。有期雇用の場合でも、条件を満たせば取得可能で、雇用形態による差別は認められていません。
また、介護職の慢性的な人手不足を理由にした取得の拒否も法律で禁止されています。
産休と育休の期間
産休は、取得期間は法律で定められており、体調や状況に応じて柔軟に調整できます。ただし、産後8週間は法的に就業が禁止されているため調整はできません。
育休は、子どもが1歳になるまでが基本ですが、保育園に入れなかった場合や配偶者が病気などで子育てができなくなった場合は延長できます。このような場合は2歳まで延長可能です。
派遣やアルバイトの場合
労働基準法では、雇用形態に関係なくパートやアルバイト、派遣社員でも産休・育休を取得できると決められています。
申請先は、派遣社員の場合は派遣会社、アルバイトやパートの場合は勤務先です。育休は、取得条件を満たす必要があります。
ハッシュタグ転職介護は、介護職に特化した人材紹介サービスとして、求職者と施設の双方に深く関わる一気通貫型のサポート体制を整えています。
特に、産休・育休の取得実績がある職場や、子育てと両立しやすい勤務条件を把握しており、育児と仕事の両立を目指す求職者と、理解ある職場との高精度なマッチングが可能です。
私たちは、ただ求人を紹介するだけではありません。今後のキャリアやライフスタイルも見据えたうえで、納得のいく選択を一緒に考えていきます。
「この先も安心して働ける職場を見つけたい」
そう感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
介護職が産休や育休を取得するまでの流れ

妊娠から産休や育休取得まで、適切な手続きを行うことでスムーズに休みに入れます。ここでは、取得までの具体的な流れを説明します。
妊娠がわかったらすぐに報告する
妊娠がわかったら、できるだけ早めに職場に報告しましょう。派遣で働いている方は派遣会社に、正社員の方は上司や人事担当者に報告します。早めに報告すると、体調に合わせて仕事内容を調整してもらえるでしょう。
介護の仕事は、重いものを持ち運ぶことも多く体力的にきついため、妊娠中の安全確保のためにも早めの報告が大切です。利用者の移乗介助や入浴介助など、身体的負担の大きい業務は、妊娠初期から配慮が必要になる場合もあります。
報告時には、出産予定日や産休・育休を取りたいこと、復帰したい意向を明確に伝えましょう。また、現在の体調や医師からの指示があればあわせての報告が大切です。これらを伝えることで、職場も業務調整や人員配置の準備ができ、不安なく働くことができます。
妊娠初期はつわりや体調の変化が起こりやすい時期です。夜勤の回数を減らしてもらう、重労働を避けるなどの体調に応じた業務調整を相談することで、母子ともに安心感を持って働き続けられます。
産休の申請を行う

出産予定日が確定したら、産休の申請を行います。出産予定日の6週間前までに行うのが一般的です。これは法定期限ではありませんが、職場の準備期間として推奨されています。
必要になる書類には、産前産後休業申請書や医師の診断書(出産予定日記載)などがあります。母体の状態によっては、医師からの業務制限指示書をもらいましょう。書類は事前に人事担当者に確認しておくとスムーズです。
育休の申請を行う

育休は休業予定日の1ヶ月前までに申請が必要です。育児休業申出書と子どもの出生を証明する書類(母子手帳)が必要になります。
出産直後で、仕事復帰せずに育休を続ける場合は、産休の時点で育休の申請も同時に行うことをおすすめします。また、配偶者と交代で育休を取る場合や育休を分割して取得する場合は、それぞれ別途申請が必要になるため計画的に手続きを進めましょう。
業務の引き継ぎを行う
業務の引き継ぎは計画的に進めて、以下の情報を整理しておくとよいでしょう。
- 担当の利用者情報とケア内容
- 業務マニュアルの作成
- 緊急時の対応手順
- 関係機関の連絡先一覧
介護職では利用者の安全と継続的なケアが重要なため、細かい注意点まで伝達が必要です。産休や育休から復帰後も働きやすい職場環境が整っているかは、事前に確認しておきましょう。
ハッシュタグ転職介護では、子育てと両立しながら長く働ける介護職場のご紹介に力を入れています。
産休・育休の取得実績はもちろん、復職後のサポート体制や柔軟なシフト対応など、働く環境の“リアルな情報”も丁寧にお伝えします。
「今の職場に戻れるか不安」「家庭との両立ができるか心配」と感じている方も、まずはお気軽にご相談ください。
子育て中のあなたが、無理なく安心感を持って働ける場所を一緒に見つけていきましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
介護職が産休や育休を取得するメリット

産休と育休の取得で、介護職として働く方には多くのメリットがあります。ここでは、具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。
復帰後も同じ職場で働ける
仕事を辞めずに復帰後も同じ職場で働けることは利点です。法律上、職場復帰の権利が保障されています。
介護の仕事は経験が重要で、利用者との信頼関係や職場での人間関係、業務の流れなどの長年培ってきたものがあります。今まで積み重ねてきた知識や経験をそのまま活かせるのは大きなメリットです。
新しい職場では一から関係を築く必要がありますが、同じ職場に復帰できれば、以前からの利用者や同僚との関係を維持できます。また、職場の業務手順や設備にも慣れているため、復帰後もスムーズに業務に取り組めるでしょう。
一定の収入を維持できる
産休と育休中は給付金で、普段の給料の一部がもらえます。出産手当金なら約3分の2、育児休業給付金は最初の6ヶ月は67%、その後は50%の支給です。
また、産休と育休中は健康保険料や厚生年金保険料の支払いが免除されるため、実際の手取り収入への影響は軽減されます。さらに、これらの給付金は非課税のため、所得税や翌年の住民税の計算にも影響しません。
育児には多くの費用がかかりますが、給付金があることで家計への負担を軽減でき、不安なく子育てに専念できるでしょう。特に介護職は夜勤手当などで収入を得ている方も少なくないため、手取りへの影響は抑えられます。
給付金の受給中も厚生年金の被保険者期間は継続されるため、産休・育休を取得することによる将来の年金額への影響もありません。また、会社によっては独自の育児支援金や復職一時金を支給する制度もあるため、事前に確認しておきましょう。
体調管理がしやすい

妊娠中から産後の回復まで、しっかり休めるのは何より大切です。介護の仕事は、身体的負担から、十分な休養期間の確保が必要です。
産休や育休の取得で、無理をせず健康第一で過ごせるのは安心感を持てます。出産は体力を大きく消耗するため、産後8週間の休業は母体の回復に不可欠な期間です。
また、新生児期は授乳や夜泣きで睡眠不足になりやすい時期でもあるので、休めるときにしっかりと身体を休め体調を整えておきましょう。
出産と育児に専念できる
子どもとの大切な時間を取れるのも育休の魅力の一つです。1歳になるまでの貴重な期間は、子どもの成長を間近で見守れるかけがえのない時間になります。
この時期は子どもの発達にとって重要で、親子の絆をしっかり育むことができます。授乳やスキンシップ、初めての笑顔や寝返りなど、成長の瞬間を見逃すことなく過ごせるのは育休の大きなメリットです。
また、保育園探しや復職の準備なども、慌てずに進められます。保育園の見学や申し込み、復職に向けた準備を余裕をもって行えるため、不安なく次のステップに進むことができるでしょう。
ハッシュタグ転職介護では、介護現場で求められる専門的なスキルや資格をしっかりと評価し、それを活かせる職場をご紹介しています。
「どんな働き方をしたいか」「どんな職場環境が合っているか」といったあなたの想いを丁寧にヒアリングし、一人ひとりに適切なマッチングを行っています。
特に、産休や育休を安心感を持って取得できる職場や、復職後も柔軟に働ける環境の情報も豊富にご用意しています。
これからの働き方に少しでも不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
産休や育休中の給与とボーナスはどうなる?

産休・育休中は基本的に給料とボーナスの支給されない職場がほとんどです。ただし、雇用保険や健康保険からの給付金により、収入がゼロになることはありません。
労働基準法では、産休中に給料の支給は義務付けられていないため、会社の就業規則や福利厚生制度によって決まります。一部の企業では独自の制度として、産休や育休中にも一定の給与を支給するところもありますが、多くはありません。
ボーナスも同様で、休業期間中は基本的に支給されません。ただし、査定期間の一部で勤務していた場合は、日割りや月割りで計算して支給される場合があります。自分の職場の制度を、事前に担当者に確認しておくとよいでしょう。
産休や育休でもらえる給付金や手当金

産休と育休中は給付金により一定の収入を確保できます。ここでは、受け取れる給付金の種類と金額を詳しく説明します。
出産手当金
健康保険からもらえるお金です。出産予定日の42日前(双子なら98日前)から出産後56日までの間で、仕事を休んで給料をもらっていない期間が対象になります。手当金がもらえる条件は、以下のとおりです。
- 勤務先の健康保険に入っている
- 産休中に給料をもらっていない
- 本人が被保険者(配偶者の扶養の場合は対象外)
もらえる金額は、支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額(健康保険や厚生年金保険の保険料計算の基準となる月給)の平均額を30で割ります。
その3分の2が1日あたりの支給額です。したがって、普段の給料の約3分の2の収入を確保できます。
出産育児一時金

出産にかかる費用をサポートしてくれるお金です。健康保険や国民健康保険に入っている女性なら、ほぼ全員がもらえます。受給条件は、以下のとおりです。
- 健康保険か国民健康保険に入っている
- 妊娠85日以上での出産(流産や死産も含む)
金額は、赤ちゃん一人につき50万円で、双子なら100万円です。出産費用の負担軽減に大きく役立ちます。
育児休業給付金
雇用保険からもらえるお金で、育休中の生活をサポートしてくれます。給付金のもらえる条件は、以下のとおりです。
- 雇用保険に入っている
- 育休前の2年間で月11日以上働いた月(または月80時間以上)が12ヶ月以上ある
- 育休中はほとんど働いていない
支給額は、最初の6か月間は通常の給与の67%、それ以降は50%です。給与に上限(月47万円程度)はありますが、この制度で育児に専念しながらも一定の収入を確保できます。
また、厚生労働省により、2025年4月から新たに出生後休業支援給付金が創設されました。一定の条件を満たす場合、育児休業給付金(67%)と出生後休業支援給付金(13%)を合わせて、28日間は賃金の80%(手取り相当で約100%)を受給できるようになりました。
これらの給付金により、産休と育休中もある程度の収入を確保でき、経済的な不安を感じることなく、休むことができます。
介護職が産休や育休を取得するときの注意点

産休や育休を円滑に取得し、スムーズに復職するためには、いくつかの注意点があります。
まれに職場から人手不足だからと産休や育休の取得を断られることがありますが、法律上認められた権利のため無視できません。産休の拒否は労働基準監督署へ、育休の拒否はハローワークへ相談できます。
産休と育休中の給付金は申請が必要で、出産手当金は産休開始から2年以内、育児休業給付金は育休開始から2ヶ月以内に初回申請となっています。職場の担当者と連携し、申請漏れを防ぎましょう。
復職時は、法律で不利益な配置転換が禁止されており、元の部署や同等の職務に戻ることが原則です。子どもが3歳になるまでは時短勤務の制度や残業免除、深夜業制限などもあるため、事前に具体的な勤務時間を相談しておきましょう。
身体的負荷が大きい仕事のため、無理をせず母子健康管理指導事項連絡カードを活用して職場に配慮を求めることもできます。このカードは、医師が妊娠中の就業上の措置を指導した内容を記載する公的な書類です。
復職前研修や段階的復帰プログラムを用意している事業所もあるため、利用できる制度を確認してみましょう。休業中も適度に職場との連絡を続けておくと、お互いに情報交換でき、スムーズに戻れます。
ハッシュタグ転職介護では、医療・福祉業界に特化した専門知識と豊富なネットワークを活かし、介護職に特化した専門アドバイザーがあなたの理想の働き方や将来のキャリアビジョンに寄り添ってサポートします。
どの資格を選ぶべきか、どのような職場が自分に合っているかなど、一人では判断が難しいことも、経験豊富なアドバイザーが一緒に考え、適切なキャリア設計をご提案します。
将来に不安を感じている方や、今の働き方を見直したいと考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたにとってよい選択肢を一緒に見つけていきましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
産休後も復帰しやすく長く働ける介護職に転職するなら

現在の職場で産休と育休を取った方があまりいない、制度はあっても実際には取りにくい雰囲気がある場合は、転職の検討も選択肢の一つです。産休と育休をしっかり取れる職場を見つけるには、以下を確認するとよいでしょう。
- 職場の年齢層や女性の割合
- 過去の産休と育休取得実績
- 復職率の高さ
- 職場見学時の女性スタッフの様子
- 復職後の時短勤務制度の充実度
- 子育て支援制度の実際の利用状況
これらの情報を事前に収集することで、本当に働きやすい職場かどうかを判断できます。面接では産休と育休などを積極的に質問しましょう。
産休と育休の取得実績と復職率、時短勤務の実施状況などを確認できます。働く人の権利にあたるため、遠慮する必要はありません。具体的な質問によって、職場の本当の姿を知ることができます。
介護職専門の転職支援サービスを活用すると、子育てしながら働きやすい職場を効率的に見つけられるでしょう。専門アドバイザーが求職者の希望条件に合わせて、産休と育休実績のある職場を紹介してくれます。
自分や家族を大切にしながら、介護職としてのキャリアも築いていける職場を探すことは可能です。現在の職場で不安を感じている方は、よりよい環境での働き方を検討してみましょう。
介護職は慢性的な人手不足が課題となっていますが、専門性の高い職業として経験豊富な職員程、必要とされています。産休と育休を取得し、復職後も長く働ける職場を見つけることで、キャリアと家庭の両立が実現可能です。
ハッシュタグ転職介護では、介護職に特化した専門アドバイザーが、求職者一人ひとりの状況や希望に丁寧に寄り添い、ワークライフバランスを大切にした職場選びをサポートしています。
求職者と法人の両方に深く関わる一気通貫型のサポート体制により、産休・育休を安心感を持って取得でき、復職後も子育てと仕事を両立しやすい職場をご紹介しています。
業界に特化した専門知識とネットワークを活かし、精度の高いマッチング力で、あなたに本当に合った環境を一緒に見つけていきましょう。
まずは、無料相談からお気軽にお話を聞かせてください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼