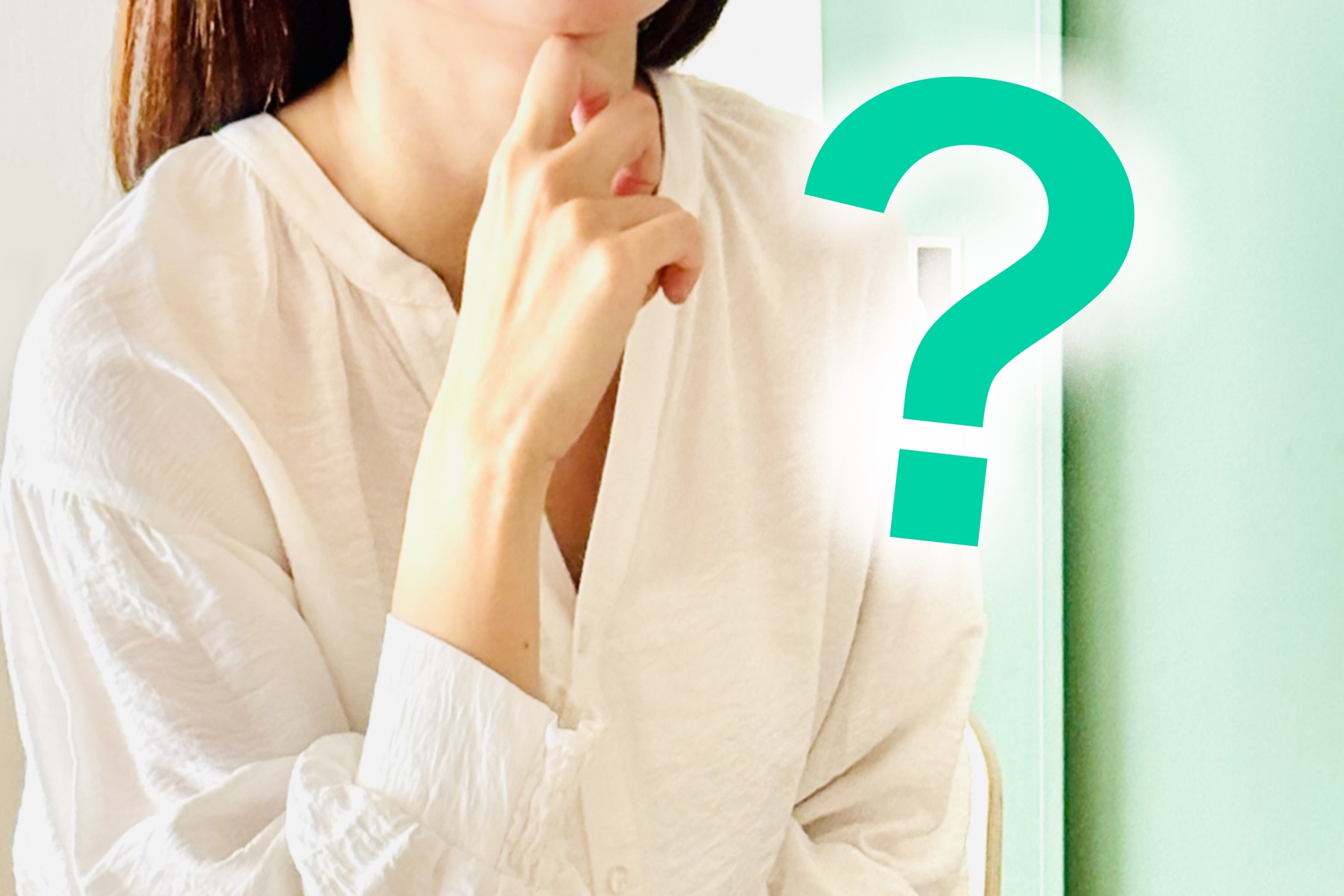介護業界は人手不足が当たり前?
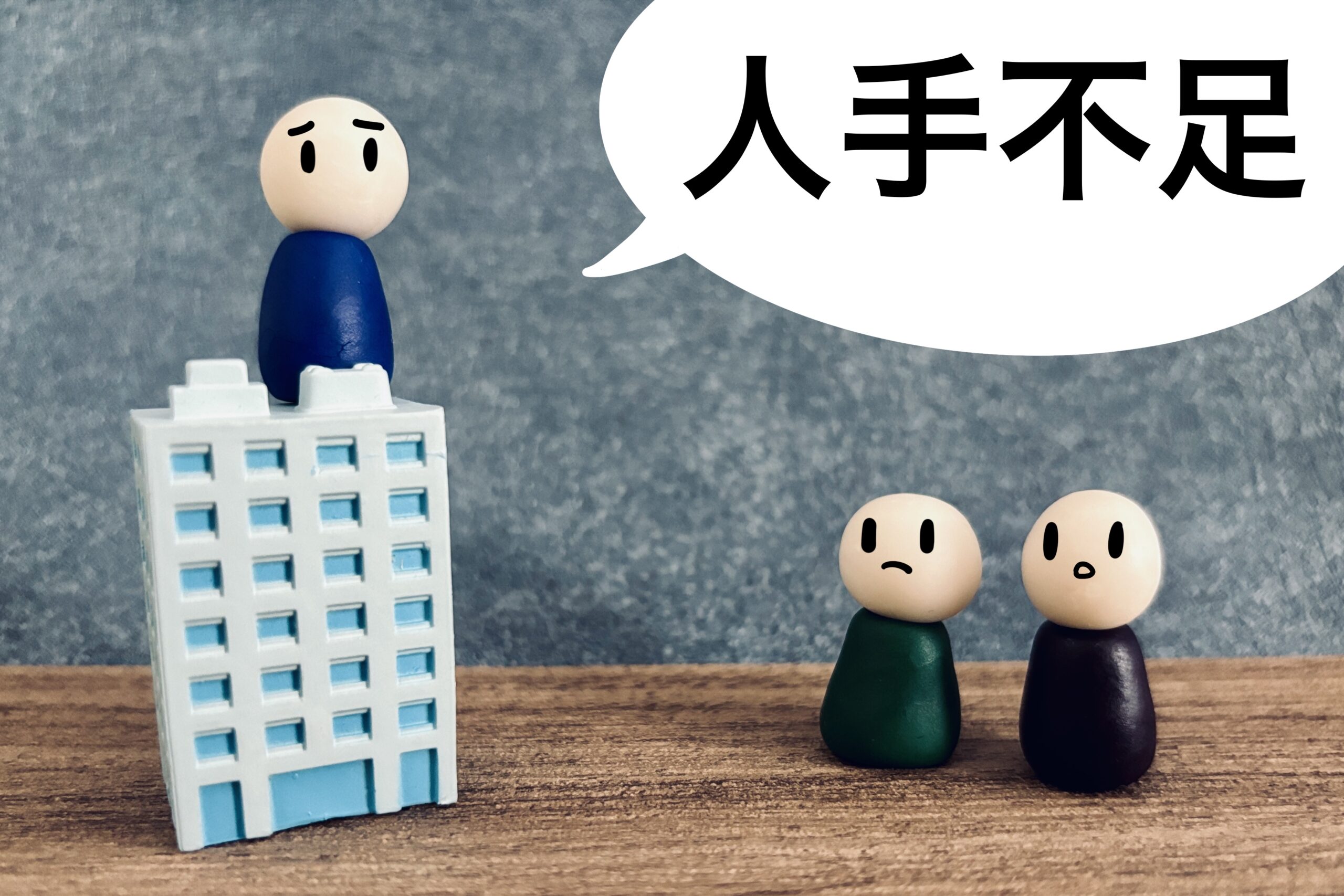
介護業界の人手不足は一時的な問題ではなく、長年にわたって続いている構造的な課題です。
厚生労働省の調査によると、介護職の有効求人倍率は全職種平均の2倍以上を常に記録しており、慢性的な人材不足の状態が続いています。
現場では、「採用しても定着しない」「新人が入っても経験者が辞めてしまう」といった声が聞かれ、多くの施設が常に人材確保に苦心している現状です。
また全国規模のアンケート調査では、介護施設の約7割が「現在人手が足りていない」と回答し、特に夜間帯や繁忙時間帯の人員確保に苦労している実態が明らかになっています。
こうした状況は地方や過疎地域でより深刻で、都市部と比べて給与水準が低い地域では人材の確保や定着がさらに難しくなっています。
特に専門的なスキルが求められる認知症ケアや医療的ケアの分野では、適切な研修を受けた人材の不足が顕著です。
介護業界の現状

日本の高齢化は世界に例を見ないスピードで進行しています。内閣府の統計によれば、2025年には65歳以上の人口が全体の30%を超える見込みです。
これに伴い介護サービスの需要も急増し、2040年には介護人材が約69万人不足すると予測されています。
一方で若年層の人口減少に加え、介護職への就業希望者も十分に増えていない状況です。それにより、需要と供給のバランスが大きく崩れています。
現場では人手不足を補うために一人あたりの業務量が増え、長時間労働や休憩時間の短縮など労働環境の悪化につながっています。利用者へのサービス低下を防ぐため職員が無理をする状況も珍しくなく、この悪循環が離職率の高さにも影響している現状です。
介護業界が人手不足になる原因

介護業界の人手不足には複合的な要因が絡み合っています。
単純に働き手が少ない問題ではなく、社会構造の変化やイメージの問題などさまざまな背景があります。主な原因を見ていきましょう。
高齢者の人口が増加しているため
日本は超高齢社会に突入しており、要介護者数も年々増加の一途をたどっています。
厚生労働省の資料によると、2000年に218万人だった要介護認定者数は2024年には約3倍に増加しました。
この需要の急増に人材の育成や確保が追いついていない状況です。今後も高齢者人口の増加は続くため、サービス需要はさらに高まると予測されています。
特に団塊の世代が後期高齢者となる2025年以降は、認知症患者さんの増加や医療ニーズの高い高齢者の増加が見込まれています。
これに伴い、単なる生活支援だけでなく、専門的な知識や技術を持った介護人材の需要がさらに高まるでしょう。
また高齢者の単身世帯や高齢者のみの世帯も増加しており、家族による介護の限界から公的サービスへの依存度が高まっています。地域によっては高齢化率が40%を超える自治体もあり、地域の支え手不足と介護ニーズの増大という二重の課題に直面しています。
労働人口が減少しているため

少子化の影響で日本の生産年齢人口(15〜64歳)は減少し続けています。全産業で人材獲得競争が激しくなるなか、介護業界も他業種と競合して人材を確保しなければなりません。
また若年層の流入が少ないことに加え、ベテラン職員の高齢化や退職も人手不足に拍車をかけています。
特に介護業界の現場を支えてきた中高年女性の層が徐々に退職年齢を迎えており、その穴を埋める若手の確保が急務となっています。
また外国人材の活用も進められていますが、言語や文化の壁、受け入れ体制の整備など課題も多く即効性のある解決策にはなっていません。
さらに、働き方改革による時間外労働の規制強化も、限られた人材での業務運営をさらに難しくしています。地方では若者の都市部流出も顕著で、すでに深刻な人材不足に陥っている地域も少なくありません。
業務内容がきついイメージがあるため
介護職は、3K(きつい・汚い・危険)というイメージが根強く残っています。たしかに身体介助や排泄ケアなど肉体的な負担を伴う業務が仕事です。
しかし、実際には利用者との心の交流やチームワークなど、やりがいを感じる側面も豊富です。
しかしメディアでは厳しい面が強調されることもあり、新規参入を躊躇させる一因となっています。
このネガティブなイメージは若者の就職先選択に大きく影響しており、介護職を選ぶ若者の減少につながっています。学校教育のなかで介護の仕事の魅力や社会的意義が十分に伝えられていないことも一因です。
また介護現場でのハラスメントやトラブルが報道されると、業界全体のイメージダウンにつながります。実際の現場では介護ロボットやリフトなどの機器導入により身体的負担の軽減が進んでいますが、そうした新しい職場環境や働き方の変化が社会に十分伝わっていません。
給与が安いイメージがあるため

介護職の賃金は他産業と比較して低いとされてきました。厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、介護職の平均月給は全産業平均より約50,000円低い水準にあります。
近年は処遇改善加算などの施策により改善傾向にあるものの、依然として厳しい状況が続いています。責任の重さや業務の専門性に見合った報酬が得られないと感じる方も少なくありません。
介護報酬は公的制度で決められており、施設が独自に大幅な給与アップを実現することが難しい構造的な問題もあります。
特に地方の小規模事業所では経営的な余裕がなく、都市部の大手事業所との給与格差が生じています。
また夜勤や休日出勤の多さに比べて手当が十分でないケースもあり、時間的・身体的な負担の割に収入が見合わないという不満につながることが原因です。
資格取得によるキャリアアップが給与アップに直結しないケースもあり、長期的なキャリア形成の動機付けが弱いという課題もあります。
介護業界の人手不足は、少子高齢化や慢性的な担い手不足などの構造的な要因によるもので、すぐに解決できる問題ではありません。だからこそ、自分にとって本当に合った働き方や職場環境を選ぶことが、長く安心感を持って働くために重要です。
「待遇がよくて無理なく続けられる」「人間関係が良好で安心できる」
そんな職場は、専門家のサポートを受けることで見つかる可能性が大きく広がります。
ハッシュタグ転職介護では、あなたの希望条件を丁寧にヒアリングし、厳選した求人の中から適切な選択肢をご提案します。まずは無料相談で、あなたの理想の働き方をお聞かせください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
介護業界によくある退職理由
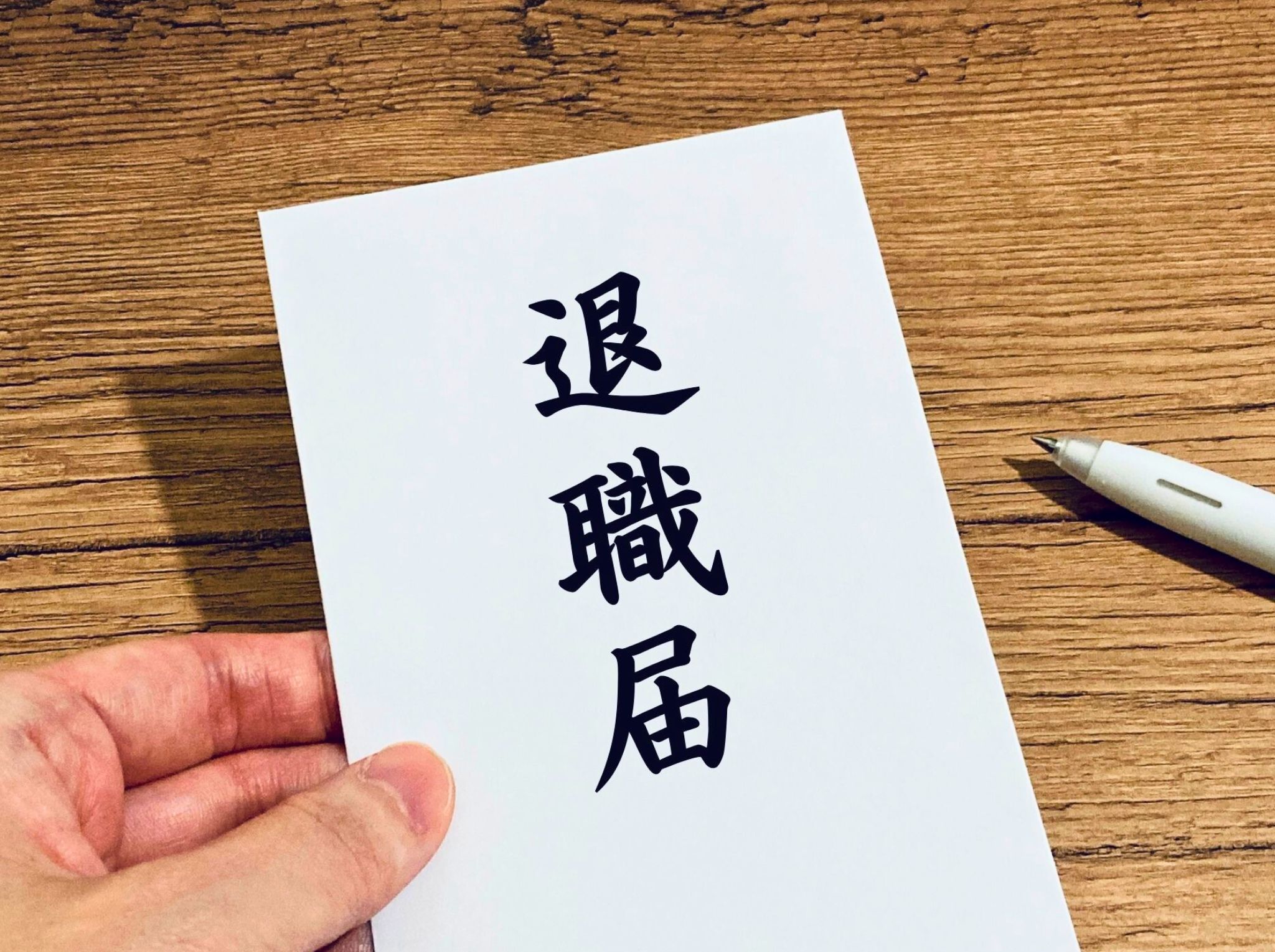
介護職の離職率は全産業平均と比べると高い傾向にあります。
どのような理由で介護職を離れる方がいるのでしょうか。主な退職理由を見ていきましょう。
身体的な負担が大きい
利用者の移乗介助や入浴介助など、身体に負担のかかる業務が日常的にあります。
適切な介助技術を習得できていなかったり、人手不足で一人で作業せざるを得なかったりすると腰痛や肩こりなどの身体的な不調を招きやすくなります。
これが長期間続くと仕事の継続が難しくなるケースの一つです。
精神的な負担が大きい

利用者やその家族との関わりは心理的な負担を伴います。認知症の方への対応や終末期ケアなど、精神的に消耗する場面も少なくありません。
また人手不足による業務の多忙さからくるストレスも大きな要因です。十分な休息を取れない状態が続くと燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥るリスクも高まります。
人間関係に問題がある
職場の人間関係は離職の大きな要因の一つです。チームケアが基本の介護現場では、スタッフ間の連携や信頼関係が重要です。
パワーハラスメントやコミュニケーション不足による摩擦が生じると、仕事への意欲が低下します。また管理者との関係が悪化すると改善が難しく、退職を選ぶ方もいます。
給与に不満がある

責任の重さや業務量に比べて給与が見合わないと感じる方は少なくありません。特に経験を積んでも給与が大きく上がらない場合、モチベーションの維持が難しくなります。
家族を養う立場になったときに収入面での不安から転職を考える方も少なくありません。
キャリアパスに不安がある
将来のキャリア展望が見えにくいことも離職理由の一つです。
介護職としてのスキルアップや昇進の道筋が明確でなかったり、研修制度が充実していなかったりすると、長期的な働きがいを見出しにくくなります。
自己成長を重視する方にとっては特に重要な要素です。
職場の経営方針に不満がある
施設の理念や方針が自分の介護観と合わない場合、仕事へのモチベーションが保ちにくくなります。
利用者本位と謳いながら実際は効率や利益を優先している職場では、介護職としての使命感を持って働くことが困難です。
また、経営の不安定さから将来に不安を感じて退職するケースもあります。
結婚や出産などライフスタイルの変化
ライフステージの変化に伴い退職を選ぶケースも少なくありません。結婚や出産、親の介護など家庭の事情で働き方の見直しが必要になることがあります。
夜勤や変則勤務がある介護職では、家庭との両立が難しいと感じる方もいるのが現状です。
これらの退職理由は、すべての職場に当てはまるわけではありません。働きやすい環境づくりに力を入れている施設も増えており、自分に合った職場を見つけることで長く活躍できる可能性は十分にあります。
転職を考えるときは、給与や勤務時間、職場の人間関係など、自分にとって「これだけは譲れない」という条件を明確にしておくことがとても大切です。それが、後悔のない転職につながります。
介護業界で新たなキャリアをスタートさせたい方は、ぜひハッシュタグ転職介護の無料相談をご活用ください。経験豊富なアドバイザーが、あなたの思いや希望を丁寧にお聞きし、適切な職場選びをサポートいたします。あなたに合った環境で、理想の働き方を実現しましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
人手不足が解消されない場合の問題点

介護現場の人手不足が続くと、さまざまな問題が発生します。
その影響は職員個人だけでなく、利用者や施設運営にまで及びます。
職員一人あたりの業務量が増える
スタッフが不足している状況では、一人あたりの担当業務が増加します。本来なら複数人で行うべき作業を一人で行わざるを得なくなったり、休憩時間を削って業務をこなしたりする状況が生まれます。
これにより身体的負担が増大し、ケアの質の低下にもつながりかねません。また時間に追われることでヒヤリハットや事故のリスクも高まるため注意が必要です。
長時間労働や休日出勤が常態化すると、心身の疲労が蓄積されていきます。プライベートの時間も十分に確保できなくなり、仕事と生活のバランスが崩れてしまいます。
その結果、新たな離職者が生まれるという悪循環に陥るケースも少なくありません。
何より懸念されるのは、利用者へのサービス低下です。
余裕をもったケアができなくなれば、本来なら気付けたはずの変化を見逃したり、コミュニケーションの時間が減ったりする可能性があります。介護の質を維持するためには、適切な人員配置が必要です。
施設が閉鎖になる可能性がある
人手不足が極端に進行すると、施設の存続自体が危ぶまれることもあります。介護保険制度では、サービス種別ごとに必要な人員基準が定められています。
この基準を満たせなくなると、新規利用者の受け入れができなくなったり、事業の継続が困難になったりする恐れがあるため注意しましょう。
実際に地方を中心に、人材確保ができずに事業縮小や閉鎖に追い込まれる事例も報告されています。施設が減少すれば地域の介護サービス提供体制が弱まり、必要な人に十分なケアが行き届かなくなる社会問題にも発展しかねません。
こうした状況を防ぐためには、個人レベルでは働きやすい環境を選ぶことも大切な選択肢です。あなた自身の健康を守り、長く介護職として活躍するためにも、職場環境の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
ハッシュタグ転職介護では、あなたの経験や希望を丁寧にヒアリングしたうえで、働きやすい職場をご紹介しています。介護の仕事を続けたいけれど環境を変えたいと考えているなら、ぜひ一度無料相談をご利用ください。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
人手不足の職場を見分ける方法

転職を考える際、次の職場選びは慎重に行いたいものです。
人手不足に悩まされない環境を選ぶための方法をご紹介します。
常に求人が出ている
同じ施設から頻繁に求人が出ていないかをチェックしましょう。長期間にわたって同じポジションの募集が続いていたり、募集職種が多岐にわたっていたりする場合は注意が必要です。
これは職員の定着率が低く、常に人が入れ替わっている可能性を示しています。
求人情報だけでなく、可能であれば直接施設に問い合わせて、職員の平均勤続年数や離職率などを質問してみるのもよいでしょう。
オープンな姿勢で回答してくれるかどうかも、その施設の透明性を判断する材料になります。また面接の際に現場を見学させてもらえれば、スタッフの表情や雰囲気からも多くの情報を得ることができます。
施設に清潔感がない
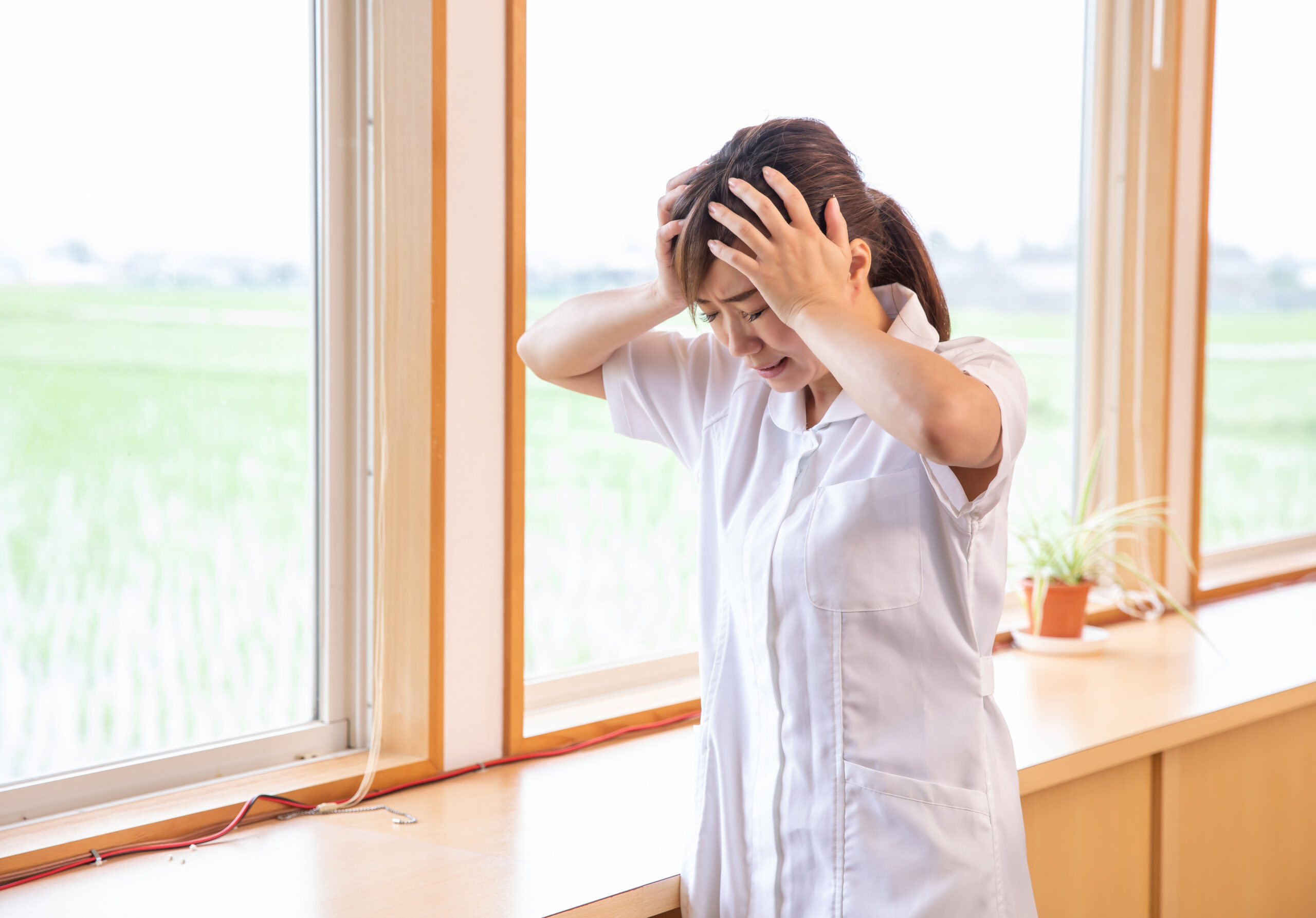
施設見学の際は、環境の清潔さにも注目しましょう。整理整頓が行き届いていない施設は、業務に追われて環境整備まで手が回っていない可能性があります。
利用者の居室やトイレ、共用スペースなどの清掃状況も確認したいポイントです。
また職員の表情や利用者との関わり方も重要な判断材料です。スタッフが余裕をもって利用者に接している姿が見られるか、職員同士のコミュニケーションは円滑かなど、人間関係の雰囲気も感じ取りましょう。
さらに職員の休憩スペースの有無や快適さも、働きやすさを左右する要素です。
転職を考えるときは、給与や勤務時間、職場の人間関係など、自分にとって「これだけは譲れない」という条件を明確にしておくことがとても大切です。それが、後悔のない転職につながります。
介護業界で新たなキャリアをスタートさせたい方は、ぜひハッシュタグ転職介護の無料相談をご活用ください。経験豊富なアドバイザーが、あなたの思いや希望を丁寧にお聞きし、適切な職場選びをサポートいたします。あなたに合った環境で、理想の働き方を実現しましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼
現在の職場に人手不足を感じているなら

今の職場環境に限界を感じているなら、新たな一歩を踏み出すことも選択肢の一つです。よりよい環境で自分の能力を発揮することは、介護のプロフェッショナルとしての成長にもつながります。
介護の仕事は本来、人の人生に寄り添い支える素晴らしい専門職です。適切な環境で働くことができれば、やりがいと誇りを持って長く続けることができるでしょう。
現在の状況に悩んでいるからこそ、自分に合った職場を見つけることが重要です。
介護業界では施設によって運営方針やケアの考え方、職場の雰囲気は大きく異なります。自分の価値観や働き方の希望にあった環境を選ぶことで、介護職としての可能性を広げることができます。
給与や休暇制度などの待遇面だけでなく、理念や教育体制など長く働くための土台となる部分も重視して選ぶことが大切です。
転職活動を始める際には、まず自分が大切にしたい条件を整理することがポイントです。給与や勤務地などの基本条件に加え、職場の雰囲気や教育制度などの働きやすさに関わる要素も明確にしておくとよいでしょう。
一人で情報収集や求人探しをするのは大変な作業です。特に介護業界は施設ごとの特性が異なるため、表面的な求人情報だけでは判断が難しい場合もあります。
そんなときは専門の転職アドバイザーに相談することで、効率的に理想の職場に出会える可能性が高まります。
まずは、ハッシュタグ転職介護の無料相談をご利用ください。介護業界に精通した経験豊富なアドバイザーが、あなたの希望や不安、現在の状況をじっくりとヒアリングし、条件に合った適切な求人をご提案いたします。
ハッシュタグ転職介護では、「とことん寄り添う支援」を大切にしており、求人紹介だけでなく、転職活動に伴うあらゆる悩みや迷いにも親身に対応しています。
「今のままでいいのかな」と感じている方も、一人で抱え込まずに、まずは私たちにご相談ください。あなたにとって納得できる選択を、一緒に見つけていきましょう。
「どんな職場がある?」「転職で迷っている」など、どんな小さな疑問でも大丈夫です。
専門アドバイザーがあなたの悩みに寄り添い、理想の職場探しをサポートします。
▼今すぐ無料で相談してみる▼